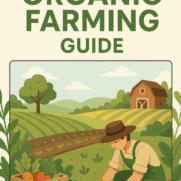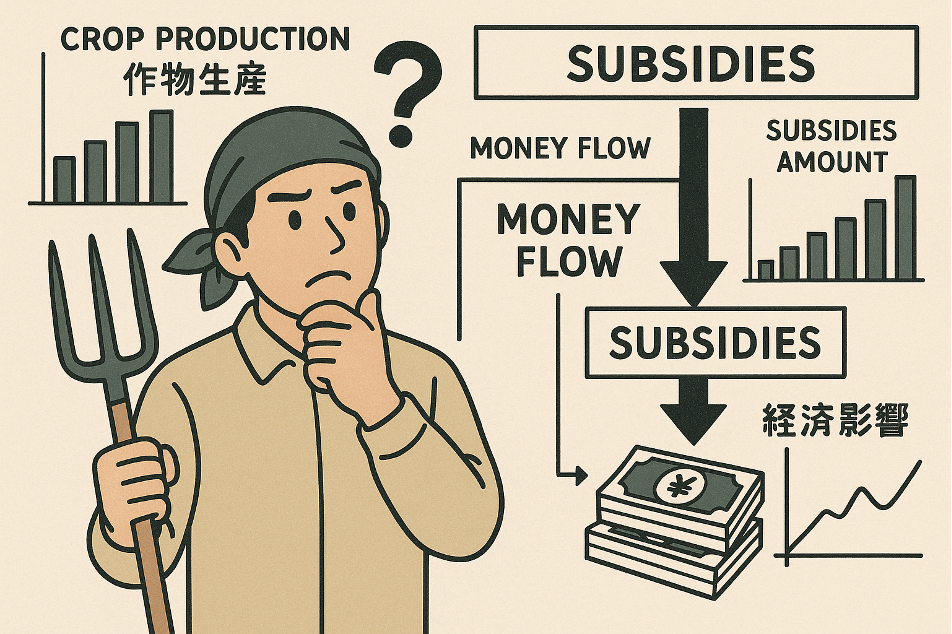本記事では、有機農業にまつわる多岐にわたる制度を徹底的に解説します。新規参入を検討している方、慣行農業からの転換を考えている既存の農業者はもちろん、流通・販売事業者、研究・行政関係者、そして「有機」の表示に信頼性を求める消費者まで、幅広い読者の方々が対象です。
「有機農業 制度 日本」の全体像を把握することは、持続可能な農業経営を実現する上で不可欠です。本記事を読むことで、有機JAS認証の取得方法、活用できる支援制度、有機農業の生産技術、市場動向、さらには国際的な制度との比較、そして将来的な展望に至るまで、網羅的な知見を得られるでしょう。
目次
有機農業制度の基本|定義・法律・推進法の概要
有機農業は、環境への負荷を低減し、持続可能な農業生産を目指す重要な営みです。その根幹を支えるのが、日本における有機農業制度です。この制度を理解することは、有機農業に携わるすべての人にとって不可欠です。
有機農業制度の定義
有機農業推進法における「有機農業」定義
有機農業は、単に化学農薬や化学肥料を使わないというだけでなく、法律に基づいた明確な定義があります。
日本の「有機農業の推進に関する法律」(通称:有機農業推進法)では、有機農業を以下のように定義しています。
「農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」
この定義は、単なる不使用だけでなく、自然循環機能の維持増進や環境負荷の低減といった理念に基づいている点が重要です。
特別栽培農産物との違い
有機農業と混同されやすいものに「特別栽培農産物」があります。これらは異なる制度に基づいており、消費者が農産物を選ぶ上で非常に重要なポイントです。
| 項目 | 有機農業(有機JAS) | 特別栽培農産物 |
| 定義 | 有機農業推進法に基づく化学肥料・化学農薬不使用等 | 各地域の慣行レベルから農薬・化学肥料を5割以上削減 |
| 認証制度 | 国が定めた有機JAS規格に基づき、第三者機関が認証 | 各地域の慣行レベルと比較し、表示ガイドラインを遵守 |
| 表示 | 有機JASマークが付与される | 「特別栽培農産物」と表示され、削減率などを明記 |
| 対象作物 | 農産物、加工食品、飼料、畜産物など幅広い | 主に農産物(精米、精麦、茶なども対象) |
| 生産方法 | 化学肥料・化学農薬、遺伝子組換え技術は基本的に不使用 | 農薬・化学肥料を基準に基づき使用を削減 |
有機JASは、化学的な合成物質を原則として使わないことに加え、土壌や環境への配慮まで踏み込んだ厳格な基準があります。一方、特別栽培農産物は、慣行栽培を基準として化学農薬や化学肥料の使用量を削減した農産物を指します。どちらの農産物も環境への配慮はしていますが、その基準と制度は大きく異なります。
法律・省令・ガイドラインの仕組み
日本の有機農業制度は、複数の法律、省令、ガイドラインによって成り立っています。これにより、有機農産物の生産から流通に至るまでの信頼性が確保されています。
JAS法と有機JAS制度の位置付け
日本の有機農業制度の中心にあるのが、JAS法(日本農林規格等に関する法律)に基づいた有機JAS制度です。JAS法は、農林物資の品質改善や生産の合理化を図るための法律で、その中に有機農産物の規格と表示に関するルールが定められています。
有機JAS制度は、農産物や加工食品が「有機」であると表示するために必要な、生産方法や品質に関する基準と、その基準を遵守しているかを確認する認証システムを規定しています。この制度があることで、消費者は「有機JASマーク」が付された食品を安心して選ぶことができます。
農林水産省ガイドラインの主要ポイント
農林水産省は、有機JAS制度を円滑に運用するための詳細なガイドラインを定めています。これらのガイドラインは、有機農業を行う生産者、認証機関、流通関係者にとって実務上の指針となります。
主要なポイントは以下の通りです。
- 生産行程管理基準: 農地の選定、資材の調達、病害虫対策、収穫、保管、輸送まで、有機農産物が有機性を損なわないように管理するための詳細な基準が定められています。
- 小分け業者・輸入業者の基準: 有機JAS認証を受けた農産物を小分けしたり、海外から輸入したりする際の取り扱いについても厳格なルールがあります。
- 表示基準: 有機JASマークの表示方法や、有機と表示できる条件などが明確にされています。これに違反すると、罰則の対象となる場合があります。
これらのガイドラインは、農林水産省のウェブサイトで公開されており、常に最新の情報を確認することが重要です。
日本の制度と国際基準の比較
日本の有機農業制度は、国際的な基準とどのような違いがあるのでしょうか。主要なEUや米国の基準と比較することで、日本の制度の特徴が見えてきます。
EU基準との違い
EU(欧州連合)は、世界でも先進的な有機農業推進地域の一つであり、厳格な有機基準と認証制度を持っています。
| 項目 | 日本(有機JAS) | EU |
| 法的位置づけ | JAS法に基づく | EU規則(EU Organic Regulation)に基づく |
| 認証対象 | 農産物、加工食品、飼料、畜産物、藻類など | 農産物、加工食品、飼料、畜産物、水産物など広範 |
| 移行期間 | 2年以上(多年生作物は3年以上) | 2年以上(多年生作物は3年以上) |
| 表示 | 有機JASマーク | ユーロリーフ(EUオーガニックロゴ) |
| 海外からの輸入 | 有機同等性協定に基づき、一部免除または個別審査 | EU規則に適合した輸入証明書が必要 |
EUの基準は、特定の農薬や肥料の使用に関する詳細なリストが定められており、土壌管理や動物福祉にも特に重点を置いています。また、EU域内での有機食品の流通には、統一されたユーロリーフの表示が義務付けられています。
米国NOP基準との違い
米国では、USDA(米国農務省)が所管するNOP(National Organic Program)が有機農業の基準を定めています。
| 項目 | 日本(有機JAS) | 米国(NOP) |
| 所管機関 | 農林水産省 | 米国農務省(USDA) |
| 認証対象 | 農産物、加工食品、飼料、畜産物、藻類など | 農産物、加工食品、畜産物、化粧品など |
| 移行期間 | 2年以上(多年生作物は3年以上) | 3年以上(多年生作物も同様) |
| 表示 | 有機JASマーク | USDAオーガニックシール |
| 海外からの輸入 | 有機同等性協定に基づき、一部免除または個別審査 | NOP基準に適合した認証が必要、同等性協定あり |
米国のNOP基準も、化学物質の使用制限や遺伝子組み換え技術の不使用など、基本的な考え方は日本の有機JAS制度と共通しています。ただし、一部の許可物質や詳細な運用ルールにおいて違いが見られます。例えば、米国では一部の加工食品において「有機成分95%以上」であれば「オーガニック」と表示できるなど、表示に関する規定に細かな違いがあります。
これらの国際基準との比較を理解することで、日本の有機農業が世界の中でどのような位置づけにあるのか、また、海外への輸出入を検討する際のポイントが明確になります。
有機JAS制度の全貌|認証制度・規格・申請手続き
有機農業を行う上で避けて通れないのが、有機JAS制度です。これは、生産された農産物や加工食品が「有機」として表示・流通するために不可欠な認証システムであり、その規格、申請手続き、そしてメリット・デメリットを理解することが成功への鍵となります。
有機JAS規格のポイント
有機JAS規格は、有機農産物の生産から出荷までの全行程において、どのような管理が行われるべきかを定めた基準です。
生産行程管理の要件
有機JAS規格では、以下の要件を満たすことが求められます。
- 種苗の管理: 有機的に生産された種苗を使用することが原則です。例外的に、有機種苗が入手困難な場合に限り、消毒されていない慣行種苗の使用が認められる場合があります。
- 土壌管理: 化学肥料や化学合成農薬を使用せず、堆肥など有機質肥料を中心に、土壌の肥沃度を維持・向上させるための管理を行います。連作障害の回避も重要です。
- 病害虫・雑草対策: 化学合成農薬は原則使用せず、耕種的防除、生物的防除、物理的防除など、自然の力を利用した方法で管理します。
- 資材の使用: 使用できる資材は、有機JAS規格で定められたポジティブリスト(使用可能物質リスト)に掲載されたものに限られます。
- 隔離・汚染防止: 周囲の慣行農地からの農薬飛散や、非有機資材の混入を防ぐための措置(緩衝帯の設置など)が求められます。
- 記録管理: 生産履歴、資材の使用記録、収穫量などの詳細な記録を継続的に保管する必要があります。これは、認証機関による検査の際に提出が求められます。
これらの要件を遵守することは、有機農産物の信頼性を確保し、消費者に安全で高品質な食品を提供するために不可欠です。
登録認証機関の役割
有機JAS認証は、農林水産大臣が登録した登録認証機関によって行われます。生産者や事業者自身が「有機」と名乗ることはできず、必ず第三者である認証機関の検査と認証が必要です。
登録認証機関は、以下の役割を担っています。
- 生産行程管理調査: 有機JAS規格に基づき、生産者のほ場や生産施設、管理体制が基準に適合しているかを調査します。
- 格付検査: 生産された農産物が、有機JAS規格に適合しているかを確認するための検査を行います。
- 認証書の交付: 調査・検査の結果、基準に適合していると認められた場合に、認証書を交付します。
- 定期検査: 認証後も、年に一度以上の定期的な検査を実施し、認証基準が継続して遵守されているかを確認します。
登録認証機関は、認証の公正性と信頼性を担保する重要な存在です。
認証制度のメリット・デメリット
有機JAS認証を取得することは、多くのメリットをもたらしますが、同時にデメリットも存在します。これらを理解し、総合的に判断することが重要です。
メリット:市場価値向上・消費者信頼性
有機JAS認証の取得は、以下のようなメリットをもたらします。
- 市場価値の向上: 有機JASマークは、消費者に「安心・安全」の象徴として広く認知されており、マークが付与された農産物は、一般的な農産物よりも高価格で取引される傾向にあります。これにより、農業者の収益性向上に繋がります。
- 消費者信頼性の獲得: 厳格な基準と第三者機関による認証があるため、消費者は安心して有機農産物を選ぶことができます。これはブランドイメージの確立にも寄与します。
- 販路の拡大: 有機JAS認証は、スーパーマーケットや生協、有機専門の流通チャネルなど、特定の販路への参入条件となることがあります。また、海外輸出を検討する場合にも不可欠な条件となることが多いです。
- 環境保全への貢献の可視化: 環境負荷の低減に取り組む有機農業の成果を、客観的な認証で示すことができます。
デメリット:コスト・手続きの複雑さ
一方で、有機JAS認証には以下のようなデメリットも存在します。
- 認証取得・維持にかかるコスト: 認証機関への手数料、検査費用、記録管理のための労力や資材費など、一定の費用が発生します。
- 手続きの複雑さ: 申請書類の作成、実地検査の対応、記録の管理など、遵守すべきルールが多く、手続きが複雑に感じられる場合があります。特に新規参入者にとっては大きな負担となる可能性があります。
- 生産量の制約: 化学肥料や化学農薬を使用できないため、慣行栽培と比較して収量が安定しない、あるいは減少するリスクがあります。
- 転換期間の存在: 慣行農地を有機農地として認証を受けるには、一定期間(畑作で2年以上、果樹で3年以上)化学肥料や化学合成農薬を使用しない「転換期間」が必要です。この期間中は有機JASマークを付与できないため、収益性が低下する可能性があります。
これらのメリットとデメリットを比較検討し、自身の経営状況や目標に合致するかどうかを慎重に判断することが求められます。
申請フローと必要書類
有機JAS認証を取得するためには、定められた申請フローに沿って手続きを進め、必要な書類を提出する必要があります。
申請書類一覧と記入例
有機JAS認証の申請には、多くの書類が必要です。主な必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 概要 | 備考 |
| 有機農産物生産行程管理認証申請書 | 認証を希望する旨を記載する基本書類。 | 認証機関のウェブサイトからダウンロード可能 |
| ほ場図 | 申請するほ場の位置、面積、周辺環境などを図示したもの。緩衝帯の記載も必要。 | Googleマップ等で作成し、詳細を追記 |
| 有機農産物生産行程管理マニュアル | 有機JAS規格に適合した生産管理方法を具体的に記述した文書。 | 有機農業の経験や知識に基づき、詳細に記述する |
| 年間生産計画書 | 栽培する作物の種類、作付け面積、収穫時期、予想収量などを記載。 | |
| 使用資材リスト | 栽培に使用する種苗、堆肥、病害虫対策資材などをリストアップ。 | 有機JAS規格のポジティブリストと照合して確認する |
| 購入資材の証明書 | 使用資材の有機JAS適合性を証明する書類(例:有機JAS認証資材の証明書)。 | |
| 農作業日誌 | 日々の作業内容、資材の使用状況、病害虫の発生状況などを記録した帳票。 | 定期的な記録が必須 |
| 誓約書 | 有機JAS規格を遵守することを誓約する書面。 |
これらの書類は認証機関によってフォーマットや詳細な記載内容が異なる場合があるため、申請先の認証機関の指示に必ず従ってください。
実地検査の準備と流れ
申請書類の提出後、認証機関による実地検査が行われます。これは、書類に記載された内容が実際にほ場や施設で適切に実施されているかを確認する重要なステップです。
実地検査の流れは以下のようになります。
- 検査日の調整: 認証機関と検査日を調整します。
- 検査前の準備:
- 提出したすべての書類(マニュアル、日誌、資材リスト、証明書など)をすぐに提示できるよう整理しておきます。
- ほ場や施設を整理整頓し、清潔に保ちます。
- 使用資材の保管場所や、非有機資材との隔離状況を確認します。
- 従業員がいる場合は、有機JAS規格に関する知識を共有しておきます。
- 実地検査の実施:
- 認証機関の検査員がほ場、作業場、保管場所などを視察します。
- 生産行程管理マニュアルの内容と実際の作業が一致しているかを確認します。
- 資材の管理状況、病害虫・雑草対策の実施状況などを細かくチェックします。
- 農作業日誌や資材の購入履歴などの記録類が適切に管理されているかを確認します。
- 検査員からの質問に的確に回答します。不明な点があれば、正直に伝え、改善策を検討する姿勢を示すことが重要です。
- 検査後の対応:
- 検査の結果、改善点や不適合事項が指摘された場合は、速やかに是正措置を講じ、その内容を認証機関に報告します。
- 是正が確認され、すべての基準を満たしていると判断されれば、認証となります。
実地検査は、有機JAS認証の信頼性を担保する上で最も重要なプロセスの一つです。入念な準備と誠実な対応が求められます。
取得方法・費用・更新手順
有機JAS認証の取得には、費用が発生し、また、一度取得すれば終わりではなく、定期的な更新が必要です。
認証取得にかかる費用項目
有機JAS認証の取得にかかる費用は、認証機関や農地の規模、作物の種類などによって異なりますが、主に以下の項目が含まれます。
- 申請手数料: 認証機関に支払う申請時の費用。
- 実地検査費用: 検査員がほ場を訪問して検査を行うための費用(旅費交通費などを含む場合が多い)。
- 登録料/認証料: 認証が認められた場合に発生する費用。
- 年間維持費: 認証を維持するために毎年支払う費用。
- (場合により)コンサルティング費用: 認証取得をサポートする専門家やコンサルタントに依頼した場合の費用。
- (間接費用): 記録管理のための帳票やITツールの導入費用、緩衝帯の設置費用など。
これらの費用は認証機関によって大きく異なるため、複数の認証機関から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。
更新申請のタイミングと注意点
有機JAS認証は、原則として1年ごとに更新が必要です。認証の有効期限が切れる前に、更新申請の手続きを行う必要があります。
更新申請のタイミングと注意点は以下の通りです。
- 更新期限の確認: 認証書に記載されている有効期限を必ず確認し、余裕をもって更新準備に取り掛かりましょう。一般的には、有効期限の2〜3ヶ月前には更新手続きの案内が認証機関から届きます。
- 年間検査の実施: 認証後も毎年、認証機関による定期検査(年間検査)が行われます。この検査で、引き続き有機JAS規格が遵守されているか確認されます。
- 変更事項の報告: ほ場の変更、栽培品種の変更、使用資材の変更など、認証内容に関わる変更があった場合は、速やかに認証機関に報告し、必要な手続きを行う必要があります。
- 記録の継続: 日々の作業日誌や資材の購入記録など、すべての記録を継続的に、かつ正確に管理し続けることが重要です。更新時にもこれらの記録が確認されます。
認証を維持するためには、継続的な自己管理と、認証機関との連携が不可欠です。
有機農業の支援制度|補助金・助成金・交付金の活用術
有機農業への新規参入や、既存の農業者が有機農業に転換する際には、初期投資や転換期間中の収益減といった課題に直面することが少なくありません。しかし、国や地方自治体は、これらの課題を克服し、有機農業の拡大を支援するための様々な補助金、助成金、交付金を用意しています。これらの支援制度を賢く活用することが、持続可能な有機農業経営を実現する上で非常に重要です。
国の補助金・助成金一覧
国(農林水産省)は、有機農業の推進を重点施策の一つと位置づけ、多様な支援制度を設けています。
令和7年度有機農業補助金の概要
毎年、農林水産省は有機農業の推進に関する予算を計上しており、年度ごとに詳細な補助金の内容が発表されます。具体的な名称や要件は年度によって変動する可能性がありますが、一般的に以下のような補助金が想定されます。
| 補助金名(例) | 目的・内容 | 対象者(例) | 補助率/上限額(例) |
| 有機農業産地づくり交付金 | 有機農業の団地化や産地形成を支援。共同利用機械の導入、土壌診断、研修会の開催など。 | 農業者グループ、市町村、農業協同組合など | 定額または定率、上限設定あり |
| 新規就農者育成総合対策 | 新規就農者の確保・育成。有機農業での就農を目指す者への経営開始資金等。 | 青年(原則49歳以下)で、有機農業で就農を希望する者 | 経営開始資金150万円/年など |
| スマート農業加速化実証プロジェクト | 有機農業におけるスマート農業技術の導入支援。ドローン、IoTセンサーなど。 | 農業者、研究機関、民間企業など | 事業費の1/2以内、上限設定あり |
| 強い農業づくり交付金 | 地域の特性に応じた農業振興。有機農業の導入・拡大も対象となる場合がある。 | 市町村、農業協同組合、民間事業者など | 事業費の1/2以内など |
これらの補助金は、有機農業への転換支援、生産性向上、販路拡大など、多様な側面から農業者をサポートすることを目的としています。詳細な情報は、農林水産省の公式ウェブサイトで確認できます。
参考: 農林水産省「有機農業に関する情報」https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/index.html
環境保全型交付金の対象要件
環境保全型農業直接支払交付金は、環境保全効果の高い農業生産活動に取り組む農業者に対して、直接的に交付金を支払う制度です。有機農業は、この交付金の主要な対象の一つとなっています。
主な対象要件は以下の通りです。
- 対象者: 環境保全型農業に取り組む農業者(個人、法人、特定農業団体など)。
- 対象活動:
- 有機農業: 有機JAS認証を取得している、または取得を目指すほ場で、化学肥料・化学農薬を使用しない栽培を行う。
- カバークロップ: 緑肥作物を栽培し、土壌侵食防止や有機物供給を行う。
- 堆肥利用: 化学肥料の使用量を削減し、堆肥などを活用して土壌の健全性を維持する。
- 地域特認の取組: 地域の実情に応じた独自の環境保全型農業の取り組み。
- その他: 生産数量要件、地域計画への位置付けなど、詳細な要件があります。
交付金額は、取り組む内容や面積によって異なります。有機農業に取り組むことで、この交付金を受け取れる可能性が高まるため、積極的に活用を検討すべきでしょう。
地方自治体の支援制度
国だけでなく、多くの地方自治体(都道府県、市町村)も、それぞれの地域の実情に応じた有機農業支援制度を設けています。
都道府県別助成金・研修制度例
各都道府県では、国の制度と連携しつつ、地域独自の有機農業振興策を展開しています。具体的な助成金や研修制度の名称、内容、募集時期などは、各自治体によって大きく異なります。
ここでは、参考として、過去に実施されたり、現在も継続されている可能性のある都道府県の助成金・研修制度の例を挙げます。最新かつ正確な情報は、必ず各都道府県の農業担当部署のウェブサイトや窓口でご確認ください。
- 鹿児島県:
- 鹿児島県農業者向け有機農業研修会:
- 有機農業の技術向上を目的としています。
- 情報交換や有機JAS認証の取得支援も行われます。
- 鹿児島県農業者向け有機農業研修会:
- 群馬県:
- 有機農産物の導入支援事業:
- 有機農業の新規導入や拡大を図る農業者が対象です。
- 土壌改良資材や機械導入などに対する助成が行われます。
- 有機農産物の導入支援事業:
- 滋賀県:
- 滋賀県有機農業推進交付金:
- 有機農業の拡大と推進を目的としています。
- 新規に有機農業に取り組む農業者等に対し、初期費用や研修費用の一部が助成されます。
- 滋賀県有機農業推進交付金:
- その他の都道府県における一般的な支援例:
- 有機農業関連の就農研修:
- 農業技術、経営、マーケティングなど、実践的な知識やスキルを習得するための研修です。
- 有機農産物の生産者への転換促進助成:
- 慣行農業から有機農業への転換を支援するための助成金です。
- 有機農業関連の就農研修:
各都道府県の農業担当部署は、これらの助成金や研修制度に関する詳細情報を提供しています。興味のある制度があれば、直接問い合わせてみましょう。また、多くの地域で、新規就農者向けの研修プログラムや、有機農業に関する相談窓口も設置されています。これらの制度を最大限に活用することで、有機農業への挑戦を力強く後押ししてくれるはずです。
申請方法・スケジュール比較
補助金・助成金の申請方法は、制度によって様々ですが、一般的には以下のステップで進行します。
- 情報収集: 募集期間、対象者、要件、補助率などを確認。
- 相談: 自治体や農業団体、地域の農業普及指導センターに相談し、制度の活用可能性や申請の方向性を確認。
- 申請書作成: 提出書類を確認し、必要な情報を正確に記入。事業計画書などが求められる場合が多い。
- 提出: 指定された期間内に、指定された方法で提出。
- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われる。必要に応じて面談や現地調査が行われることも。
- 採択・交付決定: 審査の結果、採択されれば交付決定通知が届く。
- 事業実施: 交付決定後、計画に沿って事業を実施。
- 実績報告: 事業完了後、実績報告書を提出。領収書など証拠書類の添付が必要。
- 補助金交付: 実績報告が承認されれば、補助金が交付される。
スケジュールは制度によって大きく異なるため、年度当初に各機関のウェブサイトや広報誌で情報を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。
補助金申請のコツと過去採択事例
補助金は競争率が高い場合もあり、採択されるためにはいくつかのコツがあります。
申請書類作成のポイント
採択される申請書を作成するためのポイントは以下の通りです。
- 目的・目標の明確化: どのような課題を解決し、どのような成果を目指すのかを具体的に記述します。有機農業の拡大や地域貢献など、制度の趣旨に合致する目的を強調しましょう。
- 事業計画の具体性: どのような活動を、いつ、誰が、どのように行うのかを具体的に記述します。予算の内訳も詳細に示し、必要性を論理的に説明します。
- 実現可能性と継続性: 事業が計画通りに進むことの根拠や、補助金終了後も事業が継続できる見込みがあることを示します。
- 波及効果: 自分の経営だけでなく、地域全体や環境への貢献など、事業がもたらす広がりをアピールします。
- 過去の実績: 過去に有機農業や環境保全型農業に取り組んだ実績があれば、具体的に記述することで信頼性が高まります。
- 相談と推敲: 申請前に、地域の農業普及指導員やコンサルタント、農業協同組合などに相談し、アドバイスをもらいながら申請書を推敲しましょう。
成功事例の共通点
過去の補助金採択事例には、いくつかの共通点が見られます。
- 明確なビジョンと計画: 有機農業を通じて何を達成したいのか、そのためにどのような具体的なステップを踏むのかが明確に示されている。
- 地域との連携: 地域内の他の農業者や、消費者、加工業者などと連携し、地域全体で有機農業を盛り上げていく姿勢が見られる。
- 環境保全への貢献: 単なる収益性だけでなく、生物多様性保全や土壌改善といった環境保全効果が具体的に示されている。
- 革新性・先進性: 新しい技術の導入や、未利用資源の活用など、従来の有機農業にとどまらない挑戦的な取り組みが含まれている。
- 情報収集と早期準備: 制度に関する最新情報を常に収集し、募集開始前から申請準備を着実に進めている。
これらの共通点を参考に、自身の事業計画を練り上げ、補助金の活用を目指しましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。