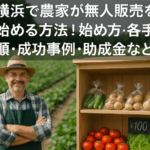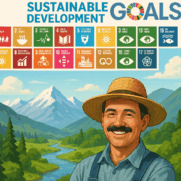「化学肥料や農薬を使わない農業って、本当に可能なの?」
食の安全や環境問題への関心が高まる一方で、実際に有機農業がどのように成り立っているのか、疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。日本の有機農業を語る上で欠かせない存在である金子美登氏は、その問いに生涯をかけて応え続けた人物です。
この記事では、有機農業の父と称される金子美登氏の人物背景から、彼が実践した究極の土づくり、循環型農業、そして農家と消費者の新しい関係を築いた「お礼(れい)制」や「お札(ふだ)制」「小川町モデル」といった革新的な取り組みまで、その全貌を徹底的に解説します。
この記事を読むことで、金子美登氏が日本の有機農業に与えた計り知れない影響を深く理解し、持続可能な農業や食への具体的なヒントを得られるでしょう。また、ご自身の家庭菜園に取り入れられる実践的なノウハウや、霜里農場の研修・見学情報も得られ、安心安全な食への第一歩を踏み出すきっかけになるはずです。
一方で、もしこの貴重な情報を知らないままだと、有機農業を「手間がかかるだけ」「特別なこと」と誤解したままになり、環境に優しいだけでなく、おいしくて安全な食を生活に取り入れるチャンスを逃してしまうかもしれません。さあ、金子美登氏の偉大な功績と、有機農業がもたらす持続可能な社会への可能性を一緒に探り、あなたの「食」と「農」への視野を広げていきましょう。
目次
金子美登氏の功績と有機農業の魅力
金子美登氏は、日本の有機農業を語る上で欠かせない存在です。その功績は多岐にわたり、単なる農家にとどまらず、有機農業の普及と発展に生涯を捧げました。彼が提唱し実践してきた土づくり、循環型農業、そして消費者との提携モデルは、今日の持続可能な農業の基盤を築いたと言っても過言ではありません。
この記事では、金子美登氏の人物背景から、彼が実践した具体的な有機農業技術、さらには地域を巻き込んだ小川町モデル、そして消費者との独自の提携スキームに至るまで、その全貌を徹底的に解説します。この記事を読むことで、金子美登氏の偉大な功績と、有機農業がもたらす持続可能な社会への可能性を深く理解できるでしょう。
本記事の目的と読みどころ
この記事のポイントは以下の通りです。
- 金子美登氏の生涯と功績を深く掘り下げ、日本の有機農業の歴史的背景を理解する
- 霜里農場で実践されてきた究極の土づくりや無農薬・無化学肥料栽培の技術を学ぶ
- 金子氏が提唱した「お礼(れい)制」「お札(ふだ)制」という消費者提携モデルの仕組みとメリットを知る
- 小川町モデルという地域全体での有機農業推進の成功事例から、地域活性化のヒントを得る
- 霜里農場の研修制度や見学会に関する最新情報を入手し、実践への第一歩を踏み出す
この項目を読むと、金子美登氏が日本の有機農業に与えた影響を深く理解し、持続可能な農業や食への関心をさらに高めることができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業が単なる願望で終わってしまうリスクや、その本質を見誤る可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。
金子美登氏がもたらした有機農業の新潮流
金子美登氏がもたらした有機農業の新潮流は、単に農薬や化学肥料を使わないというだけにとどまりません。彼の哲学は、自然の摂理に学び、地域社会との共存、そして食の安全と安心を追求することにありました。
金子氏は、戦後の効率と生産性を重視する農業から、環境保全型農業へと意識を転換させました。特に、微生物の力を最大限に引き出す土づくりや、合鴨農法などの自然の循環を利用した農法は、後の有機農業の指針となりました。また、消費者との直接的なつながりを重視した「お礼(れい)制」「お札(ふだ)制」は、食と農の新たな関係性を築き、地域経済にも貢献しました。
彼の提唱した「小川町モデル」は、一農家だけでなく地域全体で有機農業に取り組むという画期的なもので、自治体や住民を巻き込み、持続可能な地域づくりの模範となりました。これらの取り組みは、日本の有機農業が一部の特別なものから、社会全体に浸透していくための大きな推進力となったのです。
「有機農業の父」金子美登氏とは?人物背景・経歴・受賞歴を徹底解説
金子美登氏は、日本の有機農業界において「有機農業の父」と称される人物です。その生涯は、有機農業への情熱と挑戦に満ちています。彼の生い立ちから就農、全国有機農業推進協議会理事長としての活動、そして天皇杯受賞に至るまでの道のりは、まさに日本の有機農業の歴史そのものと言えるでしょう。
生い立ちから1971年就農まで
金子美登氏は、戦後の食糧難の時代に生まれ育ちました。幼い頃から自然に親しみ、農業への関心を深めていきます。
幼少期の自然体験と農業への思い
金子美登氏の幼少期は、豊かな自然に囲まれた環境で育ちました。この時期の体験が、彼の農業への根源的な思いを育んだと言われています。里山での遊びや食料の調達を通して、自然の循環や生命の尊さを肌で感じていました。
当時の日本は、化学肥料や農薬の使用が普及し始める転換期にありました。しかし、金子氏は、そのような近代農業のあり方に疑問を抱き、自然との調和を重視する農業の可能性を模索し始めます。この幼少期の原体験が、後の有機農業への道を歩むきっかけとなったのです。
大学・社会人時代の転機
大学では農業経済を学び、農業が抱える構造的な問題や社会とのつながりについて深く考察しました。しかし、理論だけでは農業の本質を捉えきれないと感じ、現場での実践を強く志すようになります。
卒業後は一般企業に就職しますが、農業への情熱は冷めず、有機農業の先駆者である一楽照雄氏との出会いが、彼の人生の大きな転機となります。一楽氏のもとで有機農業の基礎を学び、1971年に故郷である埼玉県小川町で就農することを決意します。この決断は、彼が有機農業の道を本格的に歩み始める第一歩となりました。
全国有機農業推進協議会理事長就任の軌跡
就農後、金子美登氏は自身の農場で有機農業を実践する傍ら、有機農業の普及と推進にも尽力します。その活動が認められ、全国有機農業推進協議会の理事長に就任することになります。
理事長としての主な活動内容
全国有機農業推進協議会理事長として、金子美登氏は多岐にわたる活動を展開しました。彼の主な活動内容は以下の通りです。
| 活動内容 | 詳細 |
| 政策提言 | 有機農業の法制化や普及に向けた政策を政府や国会に提言しました。特に、有機JAS規格の制定には中心的な役割を果たし、有機農産物の信頼性向上に貢献しました。 |
| 技術指導・研修 | 全国各地で有機農業の技術指導や研修会を開催し、新規就農者や転換を考える農家の育成に尽力しました。霜里農場を研修の場として開放し、実践的な知識と技術の習得を支援しました。 |
| 消費者啓発 | 有機農業の重要性や食の安全について、講演活動や執筆活動を通じて消費者に啓発を行いました。「お礼(れい)制」「お札(ふだ)制」といった消費者提携モデルの普及にも力を入れ、農家と消費者の結びつきを強化しました。 |
| 国際交流 | 海外の有機農業団体や研究者との交流を深め、日本の有機農業を世界に発信するとともに、国際的な有機農業の動向や技術を国内に導入することにも貢献しました。 |
これらの活動を通じて、金子氏は日本の有機農業が社会に認知され、広範囲に普及するための基盤を築き上げました。彼の情熱的なリーダーシップが、有機農業を一部の特別なものから、持続可能な社会を支える主要な要素へと変革させたのです。
農家・行政との連携強化
理事長としての金子氏の重要な功績の一つは、農家と行政との連携を強化したことです。これまでの有機農業は、一部の先進的な農家が孤立して実践する傾向がありましたが、金子氏はその壁を打破しようとしました。
彼は、行政に対して有機農業への理解と支援を強く求めました。その結果、有機農業を推進するための政策や補助金制度が整備されるなど、政府レベルでの支援が実現する大きなきっかけを作りました。特に、有機JAS規格の制定には、農林水産省との連携が不可欠であり、金子氏の尽力がなければ実現は困難だったでしょう。
また、全国の有機農家が情報交換や協力体制を築けるよう、研修会や交流会を積極的に開催しました。これにより、有機農家間の横のつながりが強まり、技術やノウハウの共有が進みました。このような連携強化は、有機農業の規模拡大と安定的な発展に大きく貢献したと言えます。
天皇杯受賞と小川町モデル創出
金子美登氏の功績の中でも特に注目すべきは、天皇杯受賞と、それに伴う小川町モデルの創出です。これは、彼の有機農業への貢献が全国的に評価された証であり、地域を巻き込んだ有機農業の成功例として広く知られることになります。
小川町モデルの概要
小川町モデルは、金子美登氏が埼玉県小川町で実践し、地域全体を巻き込んだ有機農業の成功モデルです。その概要は以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 目的 | 地域全体での有機農業の推進、持続可能な地域づくり、食料自給率の向上、地域経済の活性化。 |
| 中核 | 霜里農場を核とし、金子美登氏の有機農業技術と哲学を地域に展開。 |
| 構成要素 | 生産者(有機農家)、消費者(提携会員)、行政(小川町)、中間支援組織(全国有機農業推進協議会など)の連携。 |
| 主な取り組み | 有機農業技術の普及と指導、研修生の受け入れ、直売所の設置、消費者提携の促進(お礼制、お札制)、学校給食への有機野菜の導入、エコツーリズムの推進。 |
| 特徴 | 単なる有機栽培に留まらず、地域内での資源循環(堆肥の活用、バイオガス利用など)を重視し、地域の環境保全と経済活性化を両立させた点。 |
このモデルの特徴は、特定の農場や農家だけでなく、町全体で有機農業を推進しようとした点にあります。金子氏は、小川町の町議会議員も務め、行政の理解と協力を得ながら、有機農業を地域の基幹産業として位置づけました。これにより、有機農業が持続可能な地域社会を築く上での強力なツールとなりうることを全国に示しました。
受賞後の波及効果
金子美登氏が天皇杯を受賞したことは、彼の功績を全国的に知らしめる大きなきっかけとなりました。この受賞は、有機農業が単なる理想論ではなく、実践的かつ持続可能な農業として社会に認知される契機となったのです。
受賞後の波及効果は多岐にわたりました。
- 有機農業への関心向上: メディアによる報道が増え、有機農業に対する一般の関心が飛躍的に高まりました。有機農産物の需要も増加し、市場の拡大に貢献しました。
- 新規就農者の増加: 金子氏の成功事例に触発され、有機農業を志す新規就農者が増加しました。霜里農場への研修希望者が殺到し、金子氏の技術と哲学を学ぶ機会が増えました。
- 地域活性化のモデルケース: 小川町モデルは、地域活性化の成功事例として全国の自治体から注目を集めました。多くの自治体が小川町を視察し、地域での有機農業推進の参考にするようになりました。
- 政策への影響: 有機農業に対する政府や自治体の政策にも影響を与えました。有機農業の普及を支援する施策や補助金制度が強化される傾向が見られるようになりました。
このように、天皇杯受賞は金子氏個人の栄誉にとどまらず、日本の有機農業全体の発展と社会への浸透に計り知れないほどの貢献をもたらしました。
霜里農場に見る金子美登氏の有機農業技術と自給自足哲学
金子美登氏が営む霜里農場は、彼の有機農業技術と自給自足哲学の集大成とも言える場所です。ここでは、究極の土づくりから無農薬・無化学肥料栽培の実践、そしてバイオガス自給を含む循環型農業の仕組みまで、金子氏の独自の農法を詳細に解説します。
究極の土づくり:腐葉土と微生物の力で育む健康な畑
金子美登氏の有機農業の根幹をなすのは、土づくりへの徹底的なこだわりです。彼は、健康な土が健康な作物を育み、ひいては健康な人間の体を作るという信念を持っていました。そのために、腐葉土と微生物の力を最大限に活用する独自の土づくりを実践しました。
腐葉土づくりの工程とポイント
金子美登氏が霜里農場で実践した腐葉土づくりは、自然の恵みを最大限に活用し、健康な土壌を育むための重要な工程です。その工程とポイントは以下の通りです。
| 工程 | ポイント |
| 材料の選定 | 広葉樹の落ち葉を主原料とします。特に、コナラやクヌギなど、分解しやすい葉が理想的です。針葉樹は分解に時間がかかり、土壌を酸性にする傾向があるため、避けるか少量に留めます。また、周辺の山林や公園などから調達し、地域資源の有効活用を図ります。 |
| 積層と水分管理 | 落ち葉と米ぬか、油かすなどの窒素源を交互に積層します。米ぬかは微生物の活動を促進し、発酵を助けます。水分量は握って水がにじむ程度が理想的で、乾燥している場合は適度に水を加えます。過湿は嫌気性菌の繁殖を招き、腐敗の原因となるため注意が必要です。 |
| 切り返し | 定期的に切り返しを行います。これにより、酸素が供給され、好気性微生物の活動が活発になり、発酵が促進されます。切り返しの頻度は、堆肥の発酵状態や季節によって異なりますが、初期は頻繁に、安定してきたら間隔を開けて行います。切り返すことで、堆肥の均一な発酵を促し、未分解の部分をなくします。 |
| 熟成 | 切り返しを繰り返し、堆肥が黒くなり、土のような匂いがするようになったら完成です。完全に熟成した腐葉土は、作物の生育に最適な養分と微生物を含んでいます。半年から1年程度の期間をかけてじっくりと熟成させることが理想的です。 |
金子氏の腐葉土づくりのポイントは、微生物の活動を最大限に引き出すための環境づくりにありました。これにより、化学肥料に頼らずとも、作物が必要な養分を自然から吸収できる健康な土壌を実現したのです。
微生物多様性を高める管理法
金子美登氏の土づくりにおいて、腐葉土とともに重要視されたのが、微生物多様性を高めるための畑の管理法です。彼は、土中に多様な微生物が共存することで、土壌の健全性が保たれ、作物が病気に強くなり、栄養価の高い作物が育つと考えていました。
そのための主な管理法は以下の通りです。
- 有機物の継続的な投入: 腐葉土だけでなく、緑肥や堆肥、作物の残渣などを継続的に畑に投入することで、微生物の餌となる有機物を供給し続けます。これにより、微生物の種類と量を豊富に保ちます。
- 不耕起栽培や浅耕起: 深く耕さず、土壌の構造を壊さないことで、微生物の生息環境を守ります。ミミズなどの土壌動物の活動も促進され、土の通気性や排水性が向上します。
- 多様な作物の栽培: 単一作物の連続栽培を避け、輪作や混作、間作などを取り入れることで、土壌に偏りが生じるのを防ぎ、多様な微生物が共存できる環境を作ります。多様な作物の根から分泌される物質も、微生物の多様性に貢献します。
- 土壌診断による状態把握: 定期的に土壌診断を行い、土の栄養状態や微生物相を把握します。これにより、土の状態に合わせた適切な管理が可能となり、微生物のバランスを保つことができます。
- 化学物質の使用を避ける: 農薬や化学肥料は、土中の微生物に悪影響を与え、多様性を損なう可能性があります。金子氏はこれらを一切使用せず、自然の力で土壌を健全に保つことを徹底しました。
これらの管理法を通じて、金子美登氏は畑を生命の宝庫とし、作物が自らの力で育つような土壌環境を創り上げました。
無農薬・無化学肥料栽培の実践手法
金子美登氏の有機農業は、無農薬・無化学肥料栽培を徹底しています。これは単に使わないという選択ではなく、使わなくても、あるいは使わないからこそ、豊かな収穫を得るための実践的な手法に基づいています。
作物栽培サイクルと輪作計画
金子美登氏が霜里農場で実践した無農薬・無化学肥料栽培の要は、作物栽培サイクルと綿密な輪作計画にあります。連作障害を防ぎ、土壌の健全性を保つことで、病害虫の発生を抑制し、安定した収穫を実現しました。
彼の作物栽培サイクルと輪作計画のポイントは以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
| 輪作の原則 | 同じ場所で同じ作物や同じ科の作物を連続して栽培しないことです。これにより、特定の病害虫の土中での繁殖や、特定の養分の枯渇を防ぎます。異なる作物は異なる栄養素を吸収するため、土壌の養分バランスを保つ効果もあります。 |
| 作物の科の考慮 | ナス科、ウリ科、アブラナ科、マメ科など、異なる科の作物を計画的に配置します。例えば、マメ科作物(エンドウ豆、大豆など)は根粒菌によって空気中の窒素を土中に固定するため、土壌の肥沃化に貢献します。 |
| 緑肥の積極的利用 | 作物を収穫した後や、作物の生育期間中に緑肥作物(ヘアリーベッチ、クリムソンクローバーなど)を栽培し、土中にすき込みます。緑肥は土壌の有機物を増やすだけでなく、土壌構造を改善し、雑草の発生を抑制する効果もあります。 |
| 休閑期間の設置 | 畑の一部に作物を栽培しない休閑期間を設けることもあります。この期間に土壌を休ませ、自然の力で回復させることで、土壌微生物の活動が活発化し、土壌の健全性が向上します。 |
| 栽培記録の徹底 | どの作物をいつ、どの場所で栽培したかを詳細に記録し、次年度の輪作計画に役立てます。これにより、連作障害のリスクを最小限に抑え、計画的な栽培が可能になります。 |
金子氏の輪作計画は、土壌の持続性と作物の健全な生育を両立させるための知恵が詰まっています。自然の循環を理解し、作物と土壌の関係性を深く見つめることで、化学物質に頼らない農業を実現しました。
緑肥・堆肥の活用方法
金子美登氏の無農薬・無化学肥料栽培において、緑肥と堆肥は土壌の健全性を保ち、作物の生育に必要な養分を供給する上で不可欠な要素でした。
緑肥の活用方法
| 活用方法 | 詳細 |
| 土壌改善 | ヘアリーベッチやクリムソンクローバーなどの緑肥作物を栽培し、開花前に土中にすき込みます。これにより、有機物が土壌に供給され、土壌構造が改善され、水はけや通気性が向上します。特にマメ科の緑肥は、根粒菌により空気中の窒素を固定し、土壌を肥沃化させます。 |
| 雑草抑制 | 緑肥作物が畑を覆うことで、雑草の発芽や生育を抑制します。これにより、除草作業の負担を軽減し、作物と雑草との養分競合を防ぎます。 |
| 病害虫抑制 | 特定の緑肥作物は、根から分泌される物質によって土壌病害や線虫の発生を抑制する効果を持つものもあります。 |
堆肥の活用方法
| 活用方法 | 詳細 |
| 養分供給 | 腐葉土や家畜糞、米ぬかなどを発酵させた堆肥を畑に施用することで、作物の生育に必要な窒素、リン酸、カリウムなどの多様な養分を供給します。化学肥料とは異なり、緩やかに分解されるため、作物が長期間にわたって養分を吸収できます。 |
| 土壌微生物の活性化 | 堆肥には豊富な微生物が含まれており、土壌に投入することで土中の微生物相を豊かにし、微生物の活動を活性化させます。これにより、土壌の養分循環が促進され、作物の養分吸収効率が向上します。 |
| 土壌構造の改善 | 堆肥に含まれる有機物は、土壌粒子を団粒構造に結合させる役割を果たします。これにより、土の通気性、保水性、排水性が改善され、作物の根が健全に発達しやすい環境が整います。 |
金子氏は、これらの緑肥と堆肥を組み合わせることで、土壌の生命力を最大限に引き出し、外部からの化学物質に頼らない持続可能な農業を実現しました。
合鴨農法×有機JAS取得方法:バイオガス自給・自給自足のポイント
金子美登氏の霜里農場では、合鴨農法を実践し、さらに有機JAS認証を取得することで、有機農業の模範を示しました。また、バイオガス自給にも取り組み、自給自足の哲学を具現化しています。
合鴨農法の具体的手順
金子美登氏が霜里農場で実践した合鴨農法は、水田の生態系を活用した環境保全型農業の代表的な手法です。除草や害虫の駆除を合鴨に任せることで、農薬や除草剤に頼らない米づくりを実現しました。
合鴨農法の具体的な手順は以下の通りです。
| 手順 | 内容 |
| 合鴨の準備 | ヒナから育てた合鴨、または専門業者から購入した合鴨を水田に放鳥する時期に合わせて準備します。合鴨の種類は、水田での活動に適したアイガモ(カルガモとアヒルを交配したもの)が一般的です。 |
| 水田への放鳥 | 田植え後、稲がある程度育ち、合鴨に踏み荒らされない程度に成長した段階で、水田に合鴨を放鳥します。通常は田植え後1~2週間後が目安です。放鳥する密度は、広さや稲の生育状況に合わせて調整します。 |
| 合鴨の役割 | 合鴨は水田を泳ぎ回り、雑草を食べ、害虫(イネミズゾウムシ、ウンカなど)を捕食します。また、泳ぐことで水田の泥をかき回し、土中の酸素供給を促進し、稲の根の成長を助けます。排泄物は水田の養分となり、稲の生育を促進します。 |
| 管理と保護 | 合鴨が水田外に出ないよう、電気柵や防鳥ネットなどを設置し、囲いを設けます。また、キツネやカラスなどの外敵から合鴨を守るために、夜間は小屋に収容するなどの対策をとります。合鴨の健康状態にも注意し、適切な飼育管理を行います。 |
| 収穫と合鴨の利用 | 稲の収穫期が近づくと、合鴨を水田から引き上げます。合鴨は食肉として利用されることが多く、米と合鴨肉という二毛作のような形で収益を得ることも可能です。 |
金子美登氏の合鴨農法は、生態系のバランスを保ちながら米づくりを行う知恵が凝縮されており、持続可能な農業の象徴的な手法の一つと言えます。
有機JAS認証取得のステップ
有機JAS認証は、日本農林規格(JAS法)に基づき、有機農産物や有機加工食品の表示を許可する制度です。金子美登氏の霜里農場は、この認証を取得し、その信頼性を確立しました。
有機JAS認証取得の主要なステップは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
| 1. 圃場の準備 | 有機転換期間を設ける必要があります。過去2年以上(多年生作物の場合3年以上)、禁止された農薬や化学肥料を使用していない圃場であることが条件です。もし使用歴がある場合は、有機転換期間中に有機の基準で栽培し、期間が経過してから認証申請が可能になります。 |
| 2. 生産管理の記録 | 有機農産物の生産に関する詳細な記録を作成し、管理します。栽培履歴(播種日、品種、施肥、防虫対策など)、使用資材(種苗、堆肥、病害虫対策資材など)、収穫量、販売先などの記録が必要です。これらの記録は、認証機関による監査の際に重要な証拠となります。 |
| 3. 認証機関の選定と申請 | 農林水産大臣から登録された認証機関の中から、自分の農場に合った機関を選定し、必要な書類を提出して申請します。申請書類には、生産計画書、圃場図、栽培履歴などが含まれます。 |
| 4. 検査(実地検査) | 認証機関の担当者が農場を訪問し、実地検査を行います。圃場の状況、栽培方法、資材の管理、記録の適切性などが厳しくチェックされます。有機農産物と非有機農産物の混入防止対策なども確認されます。 |
| 5. 認証の取得 | 検査の結果、有機JAS規格に適合していると判断されれば、認証が付与されます。認証が付与されると、生産した農産物に有機JASマークを表示できるようになります。認証は毎年更新が必要で、定期的な監査が実施されます。 |
有機JAS認証の取得は、消費者への信頼性を高めるだけでなく、生産者自身が有機農業の基準を厳守し、持続可能な農業を追求するための重要な指標となります。金子氏は、この認証を通じて、有機農業の品質と信頼を確立することに貢献しました。
バイオガス発酵設備の導入メリット
金子美登氏の自給自足哲学は、エネルギーの自給にも及びました。霜里農場では、バイオガス発酵設備を導入し、環境負荷の低減と持続可能な農業を追求しました。
バイオガス発酵設備の導入メリットは以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
| エネルギーの自給自足 | 家畜糞尿や作物の残渣などの有機廃棄物を原料として、メタンガスを生成します。このメタンガスを燃料として、農場内の電力や熱を賄うことができ、外部からのエネルギー購入を削減し、自給自足の度合いを高めます。 |
| 廃棄物処理と環境負荷低減 | 農場で発生する家畜糞尿や作物残渣といった有機廃棄物を効率的に処理できます。発酵過程で温室効果ガスの発生を抑制し、水質汚染のリスクも軽減します。持続可能な農業に貢献します。 |
| 良質な液肥の生成 | バイオガスを生成した後の残渣は、高品質の液肥となります。この液肥は作物に直接施用できるだけでなく、土壌の養分を補給し、微生物の活動を促進する効果があります。化学肥料の使用をさらに減らすことが可能です。 |
| 悪臭の軽減 | 糞尿などの有機廃棄物を発酵させることで、悪臭の原因となる物質が分解され、悪臭が軽減されます。これにより、農場周辺の住環境が改善されます。 |
| 地域活性化への貢献 | 地域内で発生する有機廃棄物を活用することで、地域内での資源循環を促進します。また、バイオガスの生成や利用を通じて、地域のエネルギー自給率を高め、地域経済の活性化にも貢献する可能性があります。 |
金子氏は、バイオガス設備を導入することで、環境への配慮と経済性を両立させ、究極の自給自足型農業を実現しました。
「有機農業の父」金子美登氏が提唱した消費者提携モデル・お礼制の仕組みとメリット
金子美登氏の有機農業を語る上で欠かせないのが、消費者との提携モデルです。特に彼が考案した「お札(れい)制」「お札(ふだ)制」は、農家と消費者の新しい関係性を築き、有機農業の普及に大きく貢献しました。
提携スキームの歴史的背景
金子美登氏が考案した「お礼制」は、有機農業がまだ一般に普及していなかった時代において、農家と消費者が手を取り合い、持続可能な農業を支えるための画期的な仕組みでした。
会費制からお礼制への転換理由
金子美登氏の霜里農場では、当初、会費制の消費者提携を採用していました。これは、消費者が年間の会費を支払うことで、農産物の供給を受けるという形です。しかし、金子氏は会費制からお礼制へと転換する決断をします。
その主な転換理由は以下の通りです。
| 転換理由 | 詳細 |
| 農家と消費者の対等な関係の追求 | 会費制は農家が一方的に農産物を供給し、消費者が対価を支払うという形式的な関係になりがちでした。金子氏は、農家と消費者がより対等な立場で協力し、共に「食」と「農」を創造する関係を目指しました。「お礼制」は、消費者が感謝の気持ちを形にするという意味合いが強く、相互理解を深めることに貢献しました。 |
| 農業の不確実性への対応 | 農業は天候や病害虫の影響を受けやすく、毎年必ずしも安定した収穫が保証されるわけではありません。会費制では、不作の年に農家が一方的な負担を強いられる可能性がありました。「お礼制」は、豊作の年にはより多くのお礼を、不作の年には無理なく支え合うという、農業の不確実性に対応できる柔軟な仕組みでした。 |
| 金銭的価値観からの脱却 | 金子氏は、食や農業の価値を単なる「もの」や「金額」で測ることに疑問を抱いていました。「お礼制」は、農産物に対する「感謝」の気持ちを重視し、金銭的価値を超えた「いのち」のつながりを育むことを意図していました。これにより、消費者は単なる購入者ではなく、農業の営みを支える「パートナー」という意識を持つようになりました。 |
このように、会費制からお礼制への転換は、金子氏の農業哲学が色濃く反映された決断であり、農家と消費者の関係を深め、有機農業を持続可能にするための重要な一歩となりました。
お札制導入の狙い
「お礼(れい)制」の導入後、金子美登氏はさらに一歩進んで「お札(ふだ)制」というユニークな仕組みを導入しました。これは、消費者が金子氏の書いた「お札」を購入し、それを農産物の購入に充てるという制度です。
お札制導入の主な狙いは以下の通りです。
| 狙い | 詳細 |
| 共同体の意識強化 | 「お札」という共通の媒体を通じて、消費者は単なる顧客ではなく、霜里農場を共に支える「仲間」という意識を強く持つようになりました。これは、農場と消費者の間に心理的なつながりを生み出し、共同体としての結束を高める効果がありました。 |
| 農家の経営安定化 | お札を事前に購入してもらうことで、農家は種まきや栽培に必要な資金を前もって得ることができます。これにより、初期投資の負担が軽減され、経営の安定化に貢献しました。天候に左右されやすい農業において、資金繰りの安定は非常に重要です。 |
| 食の安心・安全の担保 | お札を通じて、消費者は自分たちが購入する農産物がどのように作られているか、農家の顔や哲学を知ることができます。これにより、食の安全や安心に対する信頼感が一層高まり、食のトレーサビリティが明確になりました。 |
| 地域通貨的な役割 | 「お札」は、霜里農場とその提携会員の間で流通する限定的な通貨のような役割を果たしました。これは、地域内での経済循環を促進し、地域コミュニティの活性化にも寄与しました。 |
| 有機農業の価値共有 | 「お札」という形で金子氏の哲学が込められたものを購入することで、消費者は単なる農産物だけでなく、有機農業の価値や思想を共に分かち合うことになります。これは、有機農業の普及と理解を深める上で重要な役割を果たしました。 |
「お札制」は、農家の経営を支えながら、消費者に食への深い理解と共感を促す、金子氏ならではの独創的な提携モデルでした。
提携10か条の詳細と実践事例
金子美登氏の消費者提携モデルの根幹をなすのが、「提携10か条」です。これは、農家と消費者が良好な関係を築き、有機農業を持続可能にするための約束事であり、哲学でもあります。
各条項の解説
金子美登氏の提唱した「提携10か条」は、農家と消費者が有機農業を共に支え、共生するための具体的な指針です。各条項とその解説は以下の通りです。
| 条項 | 解説 |
| 1. 契約と信頼 | 農家と消費者は契約に基づき、信頼関係を築く。互いの立場を理解し、誠実に対応することの重要性を示唆します。 |
| 2. お礼と共生 | 消費者は農産物に対して「お礼」の気持ちを込めて支払い、農家はその感謝に応える形で安全な農産物を提供する。単なる売買ではなく、共生の精神を重視します。 |
| 3. 多品目と旬 | 農家は多様な品目を栽培し、消費者は旬のものを受け入れる。自然の恵みを最大限に活かし、食生活を豊かにすることを目指します。 |
| 4. 共同作業 | 消費者は農作業の一部に参加する機会を持ち、農家はその協力を歓迎する。農業への理解を深め、農家の苦労を共有することで、より強いつながりを育みます。 |
| 5. 不作と豊作 | 不作の年には共に苦しみを分かち合い、豊作の年には共に喜びを享受する。農業の不確実性を理解し、相互に支え合うことを強調します。 |
| 6. 環境保全 | 農家は自然環境を守る農業を実践し、消費者はその活動を支持する。持続可能な社会を築くために、環境への配慮が不可欠であることを示します。 |
| 7. 地域の活性化 | 有機農業を通じて地域経済を活性化させ、地域社会に貢献する。食と農が地域の中心となる理想を追求します。 |
| 8. 次世代への継承 | 有機農業の技術や精神を次世代に継承する努力を怠らない。未来の食と環境を守るための責任を示唆します。 |
| 9. 食育と健康 | 食育を通じて健康な食生活を提案し、消費者の健康を守る。安心安全な食が心身の健康に繋がることを訴えかけます。 |
| 10. 対話と交流 | 農家と消費者は常に対話し、交流を深める。互いの声に耳を傾け、より良い関係を築くためのオープンな姿勢を促します。 |
これらの条項は、単なるルールではなく、金子氏の有機農業に対する深い哲学が凝縮されています。農家と消費者が一体となって食を守り、未来を創造していくための羅針盤と言えるでしょう。
消費者の声・成功事例
金子美登氏の消費者提携モデルは、多くの消費者から支持され、数々の成功事例を生み出してきました。提携会員となった人々は、単なる農産物の購入者にとどまらず、有機農業の実践者や応援団として積極的に関与しました。
消費者の声の例
- 「霜里農場の野菜を食べるようになってから、家族全員の健康状態が改善されました。野菜本来の甘みや旨みを知ることができ、食に対する意識が大きく変わりました。」(40代主婦)
- 「毎年の収穫祭や田植え体験に参加することで、農業の大変さと喜びを肌で感じています。金子さんたちの愛情がこもった野菜を食べられることに感謝しかありません。」(30代会社員)
- 「お礼制という仕組みは、農家と消費者が対等なパートナーとして支え合うという金子さんの哲学が凝縮されています。安心して食べられるだけでなく、地域を応援することにもつながる素晴らしいシステムです。」(50代自営業)
成功事例
- 地域コミュニティの形成: 提携会員同士が交流する機会が増え、地域の枠を超えたコミュニティが形成されました。共同購入や勉強会、イベント開催など、自発的な活動が活発に行われました。
- 食育活動の展開: 霜里農場と提携する消費者の中には、自らが食育の推進者となり、学校や地域で有機農業の大切さを伝える活動を始める人々も現れました。
- 農業体験を通じた理解促進: 農場での収穫体験や草取りなどの共同作業に参加することで、農業の現実や苦労を肌で感じ、農家への理解を深めました。これが有機農産物の価値を再認識するきっかけにもなりました。
- 新規就農者への支援: 提携会員の中には、霜里農場の研修生として有機農業を学び、自らも新規就農するケースも見られました。消費者が未来の有機農家を育てるという循環が生まれました。
これらの声や事例は、金子氏の提携モデルが単なる販売の仕組みではなく、農家と消費者が一体となって有機農業を支え、持続可能な社会を築くための強力なプラットフォームであったことを示しています。
農家と消費者の共創による地域循環型ビジネス
金子美登氏の消費者提携モデルは、単なる農産物の売買に留まらず、農家と消費者が共創する地域循環型ビジネスのモデルを確立しました。これは、地域の資源を有効活用し、経済と環境を両立させる持続可能な地域社会を目指すものです。
| 側面 | 内容 |
| 食の地産地消と地域経済 | 提携会員への農産物供給は、地元で生産されたものを地元で消費する地産地消を促進しました。これにより、地域内でのお金の循環が生まれ、地域経済の活性化に貢献しました。輸送コストや環境負荷の低減にもつながります。 |
| 有機資源の循環 | 農場で発生する有機廃棄物(稲わら、残渣、合鴨の糞など)は堆肥やバイオガスとして再利用され、土壌に還元されます。また、消費者からも野菜くずなどを回収し、堆肥化して農場で再利用する試みも行われました。地域全体での資源循環の仕組みが構築されました。 |
| 地域住民の関与と協働 | 提携会員は農作業体験や収穫祭などのイベントを通じて、農業に直接関与しました。これにより、農業への理解が深まり、農家との絆が強化されました。消費者のニーズが農家の生産に反映されるなど、双方向のコミュニケーションが活発に行われました。 |
| 多角的な事業展開 | 霜里農場では、農産物の生産だけでなく、加工品の製造や直売所の運営、農園レストランの展開など、多角的な事業を展開しました。これらの事業に地域住民や提携会員が関わることで、地域内での雇用創出や経済活動の多様化にも貢献しました。 |
| エコツーリズムの推進 | 霜里農場や小川町は、有機農業を核としたエコツーリズムの目的地としても注目されました。見学や研修に訪れる人々は、地域の宿泊施設や飲食店を利用し、地域全体の観光収入に貢献しました。 |
金子氏が築き上げた地域循環型ビジネスは、環境に配慮しながら地域経済を活性化させ、地域住民の生活を豊かにする持続可能な社会モデルとして、今日でも多くの地域で参考にされています。
「有機農業の父」金子美登氏が立ち上げた霜里農場の公開見学会&研修生受入れ情報
金子美登氏の有機農業の技術と哲学は、霜里農場で実践的に学ぶことができます。霜里農場は、未来の有機農家を育成するための研修生受入れ制度を設け、また一般の人々が有機農業の現場を体感できる公開見学会を定期的に開催しています。
研修生受入制度と育成哲学:匠から学ぶ有機農業
金子美登氏は、自身の有機農業技術と哲学を次世代に継承することに並々ならぬ情熱を注いでいました。霜里農場の研修生受入制度は、その育成哲学が色濃く反映されています。
研修コースの種類と期間
霜里農場の研修生受入制度では、実践的な有機農業を深く学ぶための複数の研修コースが用意されています。研修生は自身の目的や経験レベルに応じて、最適なコースを選択できます。
研修コースの種類と期間の例は以下の通りです。
| 研修コースの種類 | 期間 | 研修内容 | 想定される研修生 |
| 短期集中コース | 数日~1週間 | 特定のテーマ(例: 土づくりの基礎、堆肥づくりの実習、合鴨農法の概要など)に特化した実践的な研修。座学と農作業の組み合わせ。 | 有機農業に興味がある初心者、家庭菜園を実践している方、休職中などで短期間の集中学習を希望する方。 |
| 長期実践コース | 数ヶ月~1年 | 季節ごとの農作業(種まき、育苗、定植、管理、収穫など)を通年で経験し、有機農業の一連の流れを体得します。農場の経営や流通についても学びます。 | 新規就農を目指す方、将来的に有機農業を職業としたい方、既存の農家で有機農業への転換を検討している方。 |
| 特別研修コース | 期間は応相談 | 個々の研修生のニーズや関心に応じて、個別にカスタマイズされた研修プログラム。特定の作物の栽培技術、加工品づくり、消費者提携の運営など、より専門的な内容を深く学びます。 | 特定の技術や知識を習得したい経験者、既存の農場の課題解決を目指す方、研究目的の方。 |
これらの研修コースは、単なる技術の伝授にとどまらず、金子氏の有機農業に対する哲学や思想を肌で感じ、学び取ることができる貴重な機会です。研修生は、実際に農場で作業を行いながら、有機農業の奥深さを体験し、自らの手で食を育むことの喜びや難しさを学びます。
卒業後のフォローアップ体制
金子美登氏の霜里農場では、研修生が卒業した後も、有機農業の道を歩み続けられるよう、手厚いフォローアップ体制を用意していました。これは、単なる知識や技術の伝授だけでなく、有機農業に携わる人材を社会に送り出すことへの責任と情熱の表れでした。
主なフォローアップ体制は以下の通りです。
- 相談支援: 卒業後も、栽培に関する技術的な課題や経営に関する悩みなど、個別の相談に応じます。金子氏自身や霜里農場のスタッフが、長年の経験に基づいた実践的なアドバイスを提供します。
- ネットワーク形成: 霜里農場の卒業生同士の横のつながりを促進します。卒業生向けの交流会や勉強会を開催することで、情報交換や協力体制を築く機会を提供します。これにより、孤立しがちな新規就農者が互いに支え合うことができます。
- 情報提供: 有機農業に関する最新の情報や補助金制度、イベント情報などを定期的に提供します。卒業生が時代の変化に対応し、有機農業を発展させていくための支援を行います。
- 販路開拓支援: 新規就農者にとって重要な課題である販路開拓についても、農場のネットワークや経験を活かして支援を行います。直売所での販売機会の提供や、提携先の紹介など、具体的な支援を行います。
- 研修生の再受け入れ: 一度卒業した研修生が、特定の技術をさらに深めたい場合や、新たな課題に直面した場合に、短期の再研修を受け入れる体制も整っています。
これらの手厚いフォローアップは、霜里農場が単なる学びの場ではなく、有機農業の未来を担う人材を育み、社会に送り出す「揺りかご」のような存在であることを示しています。卒業生たちは、金子氏から学んだ技術と精神を受け継ぎ、全国各地で有機農業の実践者として活躍しています。
公開見学会・講演会スケジュール&申込方法
霜里農場では、有機農業への理解を深め、金子美登氏の哲学を体感してもらうため、定期的に公開見学会や講演会を開催しています。
見学会開催時期と内容
霜里農場の公開見学会は、有機農業の現場を直接見て、肌で感じることができる貴重な機会です。開催時期と内容は、季節や農場の作業によって異なりますが、一般的に以下のようになります。
| 開催時期の目安 | 内容 |
| 春(4月~5月) | 育苗作業、田植えの準備、畑の土づくりの様子を見学できます。堆肥や腐葉土の作り方など、有機農業の基礎となる作業の解説が行われます。新緑の季節で、農場全体が活気にあふれています。 |
| 夏(7月~8月) | 稲の生育状況、夏野菜の収穫の様子を見学できます。合鴨農法が実践されている水田では、合鴨が活躍する姿を間近で見ることができます。病害虫対策などの有機栽培の工夫について解説が行われることもあります。 |
| 秋(10月~11月) | 稲刈りや大豆の収穫など、実りの秋の農作業を見学できます。収穫祭などのイベントが開催されることもあり、農場の賑わいを体験できます。冬の準備としての土づくりや緑肥のすき込みなども見られます。 |
| 冬(1月~2月) | 露地栽培の野菜の冬越しや、温室での栽培の様子を見学できます。バイオガス発酵設備の仕組みや自給自足の取り組みについて、室内での講演や解説が中心となる場合もあります。 |
見学内容は、時期ごとの農場の状況に合わせて変わるため、最新の情報は霜里農場の公式ウェブサイトやSNSなどで確認することが重要です。スタッフの直接の解説が聞ける機会もあり、有機農業の奥深さと魅力を体感できる貴重な体験となるでしょう。
申込手続きの流れ
霜里農場の公開見学会や講演会に参加するには、事前の申込が必要です。スムーズな参加のために、以下の申込手続きの流れを確認しましょう。
| ステップ | 内容 |
| 1. スケジュール確認 | まず、霜里農場の公式ウェブサイトや関連団体のウェブサイト、または広報誌などで、開催される見学会や講演会の最新スケジュールを確認します。開催日、時間、内容、定員などをしっかりと把握しましょう。 |
| 2. 申込方法の確認 | 申込方法は、オンラインフォーム、メール、電話など、イベントによって異なる場合があります。各イベントの案内に記載されている申込方法を確認し、指示に従って手続きを行います。 |
| 3. 必要事項の記入・連絡 | 氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)、参加人数、参加希望日など、必要な情報を正確に記入または連絡します。質問事項や参加動機などの自由記述欄がある場合は、具体的に記入することで、主催者側の準備にも役立ちます。 |
| 4. 参加費用の確認と支払い | 参加費用が発生する場合は、金額と支払い方法(事前振込、当日現金支払いなど)を確認します。指示に従って期日までに支払いを済ませましょう。 |
| 5. 申込完了通知の受領 | 申込が完了すると、通常は主催者から申込完了の通知(メールなど)が届きます。参加証や詳細な案内が添付されている場合もありますので、必ず確認し、当日まで大切に保管しましょう。 |
人気のある見学会や講演会は定員に達するのが早い場合があるので、参加希望の場合は早めの申込がおすすめです。不明な点があれば、主催者に直接問い合わせることで、スムーズに申込を進めることができます。
参加費用と注意事項
霜里農場の公開見学会や講演会の参加費用は、イベントの内容や規模によって異なります。また、参加にあたってはいくつかの注意事項があります。
| 項目 | 詳細 |
| 参加費用 | 無料のイベントもあれば、資料代や昼食代、講師料などが含まれる有料のイベントもあります。金額は数千円程度の場合が多いですが、詳細は各イベントの案内で確認が必要です。事前に確認し、準備しておきましょう。 |
| 持ち物 | 屋外での見学が中心となるため、動きやすい服装と靴(長靴など)、帽子、タオル、飲み物、雨具などを持参しましょう。日差しが強い日は日焼け対策も忘れずに。筆記用具やメモをとるためのノートもあると便利です。 |
| 交通手段 | 霜里農場は公共交通機関でのアクセスが限られている場合があるため、自家用車での来場が推奨されます。駐車場の有無や場所についても事前に確認しておきましょう。電車やバスを利用する場合は、最寄りの駅からのアクセス方法や所要時間を調べておくことが重要です。 |
| 写真撮影 | 農場内での写真撮影は、他のお客様やプライバシーに配慮し、指定された場所やルールに従って行いましょう。無許可での撮影は控えるようにしましょう。 |
| 体調管理 | 見学会は屋外での活動が中心となるため、体調管理には十分に注意しましょう。熱中症対策や防寒対策をしっかり行い、体調が優れない場合は参加を見合わせるなど、無理をしないようにしましょう。 |
| 農場での行動 | 農場は生産の現場です。作物や施設を傷つけないよう注意し、指示された範囲での行動を心がけましょう。動物がいる場合は、触れる際には注意し、指示に従いましょう。 |
これらの注意事項を守ることで、安全に快適に見学会や講演会を楽しむことができます。金子氏の有機農業の世界を存分に体験し、学びを深めましょう。
「有機農業の父」金子美登氏のおすすめ書籍&インタビューリンク集
金子美登氏の有機農業技術と哲学は、彼の著書やメディアでの発言からも深く学ぶことができます。彼の言葉は、有機農業の実践者だけでなく、食や環境に関心を持つ全ての人々にとって貴重な示唆に富んでいます。
代表的著書一覧と要点解説
金子美登氏は、有機農業の普及と啓発のために、数多くの著書を執筆または監修してきました。彼の代表的な著書は、有機農業の技術や哲学を分かりやすく解説しており、実践者から初心者まで幅広く読まれています。
| 書籍名 | 要点解説 | 主なテーマ | おすすめ読者 |
| 『いのち育む有機農業』 | 金子美登氏の有機農業の集大成ともいえる一冊。土づくりの哲学から具体的な栽培技術、消費者提携、小川町モデルに至るまで、金子氏の有機農業の全てが網羅的に解説されています。有機農業の本質を深く理解したい人におすすめです。 | 有機農業の哲学、土づくり、循環農業、消費者提携、地域づくり | 有機農業を深く学びたい人、新規就農を目指す人、農業を生業とする人 |
| 『金子美登 有機農業の歩み』 | 金子美登氏の半生を振り返りながら、有機農業を志したきっかけ、苦労、喜び、そして日本の有機農業の歴史が語られています。人間金子美登の魅力に触れ、有機農業にかける情熱を感じられる一冊です。 | 自伝、有機農業の歴史、苦難と挑戦、人間性 | 金子氏の生き方に興味がある人、農業を志す若い人、食や環境に関心がある人 |
| 『無農薬・無化学肥料で育てる家庭菜園』 | 金子美登氏の有機栽培技術を、家庭菜園で実践できるよう分かりやすく解説しています。土づくりの基本、病害虫対策、コンパニオンプランツなど、家庭菜園で役立つ実践的な情報が満載です。家庭菜園から有機農業を始めてみたい人におすすめです。 | 家庭菜園、土づくり、無農薬栽培、病害虫対策、身近な有機農業 | 家庭菜園を始めたい人、初心者の有機栽培実践者、食育に関心がある人 |
これらの著書は、単なる技術書にとどまらず、金子氏の生命に対する敬意や、持続可能な社会への強い願いが込められています。有機農業の世界に足を踏み入れるための第一歩として、ぜひ手に取ってみてください。
テレビ出演・インタビューで読み解く課題解決策
金子美登氏は、著書だけでなく、テレビ番組や各種のインタビューにも数多く出演し、有機農業の重要性や課題、そして解決策について発信してきました。彼の言葉から、現代の農業が抱える問題点と、有機農業が示す未来の可能性を読み解くことができます。
主な出演番組と放送回
金子美登氏は、有機農業の啓発と普及のため、NHKをはじめとする数多くのテレビ番組に出演し、その活動や哲学を紹介してきました。
主な出演番組は以下の通りです。
| 番組名 | 放送局 | 内容の要旨 |
| プロフェッショナル 仕事の流儀 | NHK | 金子美登氏の農業への情熱、霜里農場での日々の挑戦、土づくりや循環型農業へのこだわり、後継者育成への思いなどがドキュメンタリー形式で紹介されました。多くの反響を呼び、金子氏の存在を全国的に知らしめるきっかけとなりました。 |
| NHKスペシャル 「食の未来を拓く」 | NHK | 日本の食料問題や環境問題と有機農業の関連性について、金子氏が専門家として解説しました。小川町モデルの成功例を通して、地域での有機農業推進の可能性や課題が議論されました。 |
| 報道ステーション(特集) | テレビ朝日 | 有機農業を実践する農家の現状と課題にスポットを当て、金子氏が現場の声として出演。消費者とのつながりや国の支援の必要性などについて語りました。 |
これらのテレビ出演は、有機農業が一部の専門家や関心層だけでなく、一般の視聴者にも広く認知されるきっかけとなりました。金子氏の飾らない人柄と、農業に対する真摯な姿勢は、多くの人々に感銘を与え、有機農業への関心を高めることに貢献しました。
インタビュー記事の要旨と学び
金子美登氏は、様々なメディアのインタビューに応じ、その農業哲学や社会への提言を発信してきました。これらのインタビュー記事からは、彼の多角的な視点から有機農業の課題解決策を読み解くことができます。
主なインタビュー記事の要旨と学び
- 有機農業の普及に関する課題と解決策:
- 課題: 有機農業は手間がかかり、収量が不安定であるため、規模拡大が難しいという認識がある。また、消費者への価格転嫁が難しいという課題も指摘されていました。
- 解決策: 金子氏は、有機農業の価値を消費者に正確に伝え、理解と共感を得ることが重要だと強調しました。また、国や自治体による政策的な支援(補助金、技術指導など)の必要性も訴えました。特に、有機JAS規格の普及と信頼性の向上が、有機農業の市場拡大に不可欠であると指摘しています。
- 食料自給率と地域活性化:
- 課題: 日本の食料自給率の低さは深刻な問題であり、食の安全保障の観点からも改善が急務であると警鐘を鳴らしました。
- 解決策: 小川町モデルに代表される地域ぐるみでの有機農業推進が、食料自給率の向上と地域経済の活性化を両立させる鍵であると提言しました。地域内での資源循環や加工品開発、エコツーリズムなどを組み合わせることで、地域の持続性を高められると主張しています。
- 環境問題と農業の役割:
- 課題: 現代農業が環境に与える負荷(農薬や化学肥料による土壌汚染、水質汚染など)は看過できない問題であり、地球規模の環境問題に直結していると認識していました。
- 解決策: 有機農業は、土壌の健全性を保ち、生物多様性を守ることで、環境負荷を低減できる唯一の農業であると力説しました。化学物質に頼らない自然との共生こそが、持続可能な未来を築くための道であると語りました。
金子氏のインタビューは、単なる農業技術の話にとどまらず、食、環境、地域社会、経済といった多岐にわたるテーマを横断し、本質的な課題解決策を示しています。これらの言葉は、現代を生きる私たちにとって貴重な羅針盤となるでしょう。
「有機農業の父」金子美登が築いた霜里農場の現在と次世代への継承
金子美登氏が生涯をかけて築いた有機農業のレガシーは、霜里農場の後継者たちによって確実に受け継がれ、現在も進化を続けています。彼の課題解決策は、現代の気候変動や人口減少といった農業が直面する困難にも適用可能であり、有機農業の未来を明るく照らす指針となっています。
霜里農場の今:後継者と現況レポート
金子美登氏の死去後も、霜里農場は彼の有機農業哲学と技術を継承し、発展させています。金子氏の息子である金子宗郎氏をはじめとする後継者スタッフが、農場の運営と有機農業の普及に尽力しています。
後継者スタッフの取り組み
金子美登氏の後継者である金子宗郎氏や他のスタッフたちは、霜里農場が築き上げてきた有機農業の伝統を守りつつ、時代の変化に対応するための新たな取り組みを進めています。
後継者スタッフの主な取り組みは以下の通りです。
- 金子美登氏の哲学の継承: 金子美登氏が提唱した究極の土づくり、循環型農業、消費者提携などの哲学を忠実に守り、実践しています。自然との共生、地域社会との連携といった根幹となる思想は、農場運営の基盤として受け継がれています。
- 伝統技術の維持と発展: 腐葉土づくりや合鴨農法など、金子美登氏が確立した有機栽培技術を継続して実践し、その技術の維持と向上に努めています。また、最新の知見や技術も取り入れながら、より効率的で持続可能な農法を追求しています。
- 消費者との関係強化: 「お礼(れい)制」「お札(ふだ)制」といった消費者提携モデルを継続し、提携会員との交流を大切にしています。収穫祭や農作業体験などのイベントを通じて、消費者との絆を深め、有機農業の価値を伝え続けています。
- 研修生の育成と支援: 金子美登氏の意思を継ぎ、有機農業を志す新規就農者や研修生の受け入れを継続しています。実践的な指導に加え、卒業後のフォローアップも行い、未来の有機農家の育成に貢献しています。
- 情報発信の強化: ウェブサイトやSNSなどを活用し、霜里農場の活動や有機農業の魅力を積極的に発信しています。金子美登氏のレガシーを広く伝え、有機農業への理解を深めるための努力を惜しみません。
これらの取り組みを通じて、霜里農場は単なる農場ではなく、有機農業の精神と技術を未来に繋ぐための拠点として、その役割を果たし続けています。
最新プロジェクト・イベント
霜里農場では、金子美登氏のレガシーを守りつつも、時代の変化に対応するために新しいプロジェクトやイベントを積極的に開催しています。これらの活動は、有機農業の可能性を広げ、より多くの人々に関心を持ってもらうための重要な取り組みです。
| プロジェクト・イベント名(例) | 内容 | 目的 |
| 若手有機農家支援プログラム | 新規就農者や若手有機農家を対象に、栽培技術の指導や経営相談、販路開拓支援などを提供するプログラム。霜里農場のベテラン農家がメンターとして伴走します。 | 次世代の有機農家の育成と定着、有機農業の拡大。 |
| オンライン農場見学&交流会 | 新型コロナウイルス感染症の影響で直接の来場が難しい状況でも、農場の様子をライブ配信し、質疑応答を通じて交流を図ります。オンラインならではの手軽さで、全国から参加できます。 | 地理的な制約を超えて、より多くの人々に霜里農場の取り組みを知ってもらう。 |
| オーガニック食材を使った料理教室 | 霜里農場で収穫された有機野菜を使って、プロの料理人がレシピを紹介する料理教室。食材の選び方から調理法まで、有機食材の魅力を最大限に引き出す方法を学びます。 | 有機食材の美味しさと価値を消費者に伝え、有機食材の消費拡大を促進する。 |
| 地域連携マルシェ | 小川町内外の有機農家や食品加工業者が集まり、有機農産物や加工品を販売するマルシェを定期的に開催。地域の食の魅力を発信し、生産者と消費者の交流の場を提供します。 | 地域の有機農業の活性化、生産者と消費者の直接的なつながりの創出。 |
| 環境教育プログラム | 小中学生を対象に、田植えや稲刈り、生き物観察などを通して、自然と農業のつながりを学ぶプログラム。持続可能な社会を支える人材を育みます。 | 次世代への食育と環境教育、有機農業への理解促進。 |
これらのプロジェクトやイベントは、霜里農場が単なる生産の場ではなく、有機農業の知恵を伝え、地域社会との絆を深めるための開かれた場所として機能していることを示しています。最新の開催情報は、霜里農場の公式ウェブサイトやSNSなどで確認できます。
金子氏の課題解決策が示す有機農業の未来
金子美登氏が生涯をかけて追求した有機農業の哲学と実践は、現代社会が直面する様々な課題に対する有効な解決策を示しています。気候変動、人口減少、食料問題といったグローバルな課題に対し、有機農業が果たすべき役割はますます大きくなっています。
気候変動・人口減少への対応策
金子美登氏の有機農業の哲学には、気候変動や人口減少といった現代の農業が直面する深刻な課題への示唆が含まれています。
気候変動への対応策
| 対応策の側面 | 金子氏の有機農業が示す解決策 |
| 土壌の炭素貯留 | 有機物を豊富に含んだ健康な土壌は、大気中の二酸化炭素を吸収し、炭素として土中に貯留する能力があります。金子氏の腐葉土づくりや緑肥の活用は、この炭素貯留機能を最大限に高めます。 |
| 生物多様性の保全 | 化学農薬や化学肥料を使用しないことで、土壌微生物や昆虫、鳥類など多様な生物が生息できる環境を育みます。生物多様性は、生態系のレジリエンス(回復力)を高め、気候変動による影響を緩和する役割を果たします。 |
| 水資源の有効活用 | 団粒構造が発達した有機的な土壌は、保水力が高く、干ばつ時にも作物が水分を利用しやすくなります。また、過剰な灌漑の必要性が減り、水資源の節約にも貢献します。 |
| エネルギー消費の削減 | 化学肥料の製造には大量の化石燃料が必要ですが、有機農業では堆肥や緑肥など自然由来の資材を活用するため、エネルギー消費を大幅に削減できます。バイオガス自給の取り組みは、再生可能エネルギーへの転換を示唆します。 |
人口減少への対応策
| 対応策の側面 | 金子氏の有機農業が示す解決策 |
| 地域活性化と雇用の創出 | 小川町モデルが示唆するように、有機農業は地域経済を活性化させる核となりえます。加工品製造、直売所、エコツーリズムなどを組み合わせることで、地域内に新たな雇用を生み出し、若者の定着を促します。 |
| 農業の多面的機能の評価 | 有機農業は食料生産だけでなく、景観形成、水資源涵養、生物多様性保全など多面的な機能を持ちます。これらの機能を地域住民や都市住民に評価してもらい、農業を支える「共助」の精神を育みます。 |
| 消費者との共創 | 「お礼(れい)制」「お札(ふだ)制」のような消費者提携モデルは、農家と消費者が単なる売買関係を超えてパートナーとして農業を支え合うことを可能にします。人口減少で農業従事者が減る中でも、消費者の支えによって持続可能な農業を実現できます。 |
| 次世代への技術・哲学の継承 | 研修生受入制度を通じて、有機農業の技術と哲学を次世代に継承する努力は、人口減少で懸念される担い手不足の解決に貢献します。地域に根差した有機農業の担い手を育成し、農業の持続性を確保します。 |
金子氏の有機農業は、短期的な収益だけでなく、長期的な視点で地球環境と人間社会の持続可能性を追求する姿勢が貫かれていました。彼の残した知恵は、未来の農業のあり方を考える上で不可欠なものとなるでしょう。
スマート農業・DXとの融合可能性
金子美登氏が提唱した有機農業は、自然との調和を重視する伝統的な農法を基盤としていますが、現代のスマート農業やDX(デジタルトランスフォーメーション)といった最新技術との融合にも大きな可能性を秘めています。
| 融合の可能性 | 具体例 | 金子氏の哲学との関連 |
| 精密な土壌管理 | 土壌センサーを活用し、土壌の水分量、養分量、温度などをリアルタイムで計測することで、土壌の状態を詳細に把握できます。データに基づき、適切なタイミングで堆肥を施用したり、緑肥をすき込んだりすることで、金子氏が目指した「究極の土づくり」をより効率的に実現できます。 | 土壌の生命力を最大限に引き出すという哲学を、データによって可視化し、最適化する。 |
| 病害虫の早期発見・対策 | AIを活用した画像解析やドローンによる監視で、作物の病害虫の発生を早期に発見し、ピンポイントで対策を講じることができます。これにより、無農薬栽培における病害虫リスクを低減し、収量の安定化に貢献します。 | 化学物質に頼らない病害虫対策の精度を高め、作物の健全な生育を促進する。 |
| 栽培環境の最適化 | 温室や施設栽培において、IoTセンサーで温度、湿度、光量などを制御し、作物の生育に最適な環境を自動で維持できます。これにより、安定した品質と収量を確保し、労働力不足の解消にもつながります。 | 作物の生命力を最大限に引き出すという哲学を、科学的なデータと技術でサポートする。 |
| 流通・販売の効率化 | ブロックチェーン技術を活用して、有機農産物の生産履歴を透明化し、消費者への信頼性を高めます。また、ECサイトやマッチングプラットフォームを通じて、生産者と消費者が直接つながる機会を増やし、流通コストを削減できます。 | 消費者との信頼関係を重視する提携モデルを、デジタル技術でさらに強化し、販路を拡大する。 |
| 研修・教育の効率化 | オンライン学習プラットフォームやVR/AR技術を活用することで、有機農業の研修や教育をより多くの人々に提供できます。金子氏の哲学や技術を体系的に学び、実践する機会を広げます。 | 次世代への技術継承と人材育成を、デジタル技術で加速させる。 |
スマート農業やDXは、有機農業が抱える労働力不足や生産性の課題を解決し、より多くの人々に有機農業の恩恵を届ける可能性を秘めています。金子氏の有機農業哲学と最新技術の融合は、持続可能な未来の農業を創造するための新たな道を切り拓くでしょう。
行動の第一歩を踏み出そう!金子美登氏の有機農業ライフを手に入れるコツ
金子美登氏の有機農業の世界に触れることで、食や環境に対する意識が高まったことでしょう。ここからは、あなたが有機農業を生活に取り入れ、素敵な有機農業ライフを手に入れるための具体的な第一歩を提案します。
霜里農場見学を活用して実践ノウハウを体感しよう
金子美登氏の有機農業の神髄を理解する最も良い方法の一つは、霜里農場に足を運び、実際にその現場を見学することです。百聞は一見に如かず、写真や文章だけでは伝わらない空気感や土の感触、作物の生命力を五感で体感することで、有機農業の本質を深く理解できます。
見学前の準備とポイント
霜里農場の見学を最大限に有意義なものにするためには、事前の準備が重要です。ポイントを押さえて、充実した見学に臨みましょう。
| 準備・ポイント | 内容 |
| 目的を明確にする | 何を知りたいのか、何を学びたいのかを具体的にしておきましょう。例えば、「土づくりの具体的な方法を知りたい」「消費者提携の仕組みを深く理解したい」「農場の雰囲気を感じたい」など、目的を明確にすることで、見学中の集中力が高まります。 |
| 予備知識を身につける | 金子美登氏の著書や関連記事を事前に読み、霜里農場の基本的な情報や有機農業の概念を把握しておきましょう。予備知識があることで、説明の理解度が深まり、より踏み込んだ質問ができるようになります。 |
| 質問事項を準備する | 見学前に疑問点や知りたいことをリストアップしておきましょう。直接、農場のスタッフや関係者に質問できる貴重な機会です。質問を通じて、より深い学びを得ることができます。 |
| 服装と持ち物を確認する | 屋外での活動が中心となるため、汚れても良い動きやすい服装と靴(長靴など)が必須です。季節に応じて帽子、タオル、飲み物、雨具、防寒具などを持参しましょう。メモをとるための筆記用具やノートも忘れずに。 |
| 交通手段と時間を確認する | 霜里農場は公共交通機関でのアクセスが限られている場合があるため、自家用車での来場が推奨されます。駐車場の有無や場所、最寄りの駅からのアクセス方法や所要時間を事前に確認し、時間に余裕を持って行動しましょう。 |
| 最新情報をチェックする | 見学会のスケジュールや内容は変更になる可能性があります。公式ウェブサイトやSNSなどで最新情報を必ず確認し、トラブルを避けるようにしましょう。 |
これらの準備をしっかり行うことで、霜里農場での見学はあなたの有機農業ライフを始める上で貴重な経験となるでしょう。
当日の回り方と質問リスト
霜里農場の見学当日は、効率的に回り、疑問点を解消するために、以下のポイントを意識して行動しましょう。
当日の回り方
- 全体像を把握する: まずは、案内図や説明を聞き、農場の全体像を把握しましょう。各エリアの役割やつながりを理解することで、個々の施設や作業が持つ意味がより深く理解できます。
- 「土」に注目する: 金子氏の有機農業の根幹である土づくりに注目しましょう。畑の土を触ってみたり、腐葉土や堆肥の積んである場所を観察したりして、その違いを体感してみてください。微生物の活動を感じられるかもしれません。
- 循環を意識する: 作物の栽培エリア、合鴨のいる水田、家畜小屋、バイオガス設備など、各要素がどのように循環し、一体となって機能しているかを意識しながら見て回りましょう。
- 農場スタッフの話を聞く: 案内をしてくれる農場スタッフの話に耳を傾け、疑問に思ったことは積極的に質問しましょう。現場の生の声は、書物では得られない貴重な情報源です。
- 直売所や加工品を見る: 霜里農場で収穫された農産物や加工品が販売されている直売所があれば、ぜひ立ち寄ってみましょう。実際に購入して味わうことで、有機農産物の美味しさを体験できます。
質問リストの例
- 土づくりについて:
- 腐葉土や堆肥は、年間でどのくらいの量を作っていますか?
- 土壌診断はどのくらいの頻度で行い、結果をどのように栽培に活かしていますか?
- 土の状態を健康に保つために、最も重要視している点は何ですか?
- 栽培技術について:
- 特定の病害虫が発生した場合、どのように対処していますか?
- 緑肥はどの時期にどの種類をすき込んでいますか?
- 無農薬・無化学肥料栽培で、収量を確保するための工夫は何ですか?
- 消費者提携について:
- 「お礼(れい)制」や「お札(ふだ)制」の具体的な運用はどのように行われていますか?
- 提携会員との交流で、印象的なエピソードはありますか?
- 今後、消費者提携をどのように発展させていきたいですか?
- 経営・後継者について:
- 有機農業を持続可能にするための経営的な工夫は何ですか?
- 新規就農者や研修生を受け入れる上で、大切にしていることは何ですか?
- 金子美登氏の哲学を今後どのように継承し、発展させていきたいですか?
これらの質問を参考に、あなた自身の疑問をぶつけてみましょう。きっと、有機農業の奥深さと魅力を再発見できる貴重な経験となるはずです。
関連書籍購読&オンラインコミュニティ参加のすすめ
金子美登氏の有機農業に関心を持ったなら、霜里農場への見学だけでなく、関連書籍の購読やオンラインコミュニティへの参加も有効です。これにより、知識を深め、情報交換を行い、有機農業ライフをより豊かにすることができます。
おすすめコミュニティ3選
有機農業に関する知識を深め、同じ志を持つ仲間と交流を図るためには、オンラインコミュニティへの参加が非常に有効です。ここでは、おすすめの有機農業関連コミュニティを3つ紹介します。
| コミュニティ名(例) | 特徴 | おすすめポイント |
| 日本有機農業研究会 | 有機農業に関する研究と実践を行う学術団体。年次大会や研究会を開催し、最新の研究成果や技術が共有されます。専門家や研究者との交流も可能です。 | 体系的な知識と最新の研究動向を学びたい人に最適です。プロの有機農家や研究者が多く参加しており、専門的な議論が活発です。 |
| 有機JAS認証取得者コミュニティ | 有機JAS認証を取得している農家や企業、または取得を目指す人々が情報交換を行う非公開のオンライングループ(Facebookグループなど)。認証制度に関する疑問や課題、実践的なノウハウが共有されます。 | 有機JAS認証の取得や維持に関わる実践的な情報を得たい人、認証を取得している仲間とつながりたい人におすすめです。 |
| 有機農業実践者の会(地域限定型) | 各地域に存在する小規模な有機農業者や家庭菜園愛好家の集まり。定期的な勉強会、農場見学、情報交換会などを開催しています。オンラインとオフラインの両方で活動している場合が多いです。 | 地域密着型で、身近な有機農業者と直接交流したい人、地域の気候風土に合わせた実践的なノウハウを学びたい人に最適です。新規就農を考えている人にとっても心強い存在となるでしょう。 |
これらのコミュニティは、オンラインで情報を得られるだけでなく、同じ目標を持つ仲間とつながり、互いに支え合うことで、有機農業ライフをより充実したものにできるでしょう。あなたに合ったコミュニティを見つけて、ぜひ参加してみてください。
書籍購読後の学びを深める方法
金子美登氏の著書を購読したら、単に読み終えるだけでなく、その学びをさらに深めるための工夫をしましょう。実践と考察を繰り返すことで、知識が本当の知恵へと変わっていきます。
| 学びを深める方法 | 内容 |
| 実践と検証 | 書籍で学んだ土づくりや栽培技術などを、実際に家庭菜園や小さな畑で試してみましょう。実践することで、理論だけでは分からない感覚や難しさを体感できます。結果を記録し、何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかを検証することで、より深く理解が進みます。 |
| 疑問点の深掘り | 書籍を読みながら疑問に思った点や、さらに詳しく知りたいことをリストアップしましょう。そして、インターネットで追加の情報を調べたり、専門家に質問したりすることで、知識の穴を埋め、理解を深めます。 |
| アウトプットの機会を作る | 学んだことを誰かに話したり、ブログやSNSで発信したりする機会を作りましょう。アウトプットすることで、自分の理解度を確認できるだけでなく、他者からのフィードバックや新たな視点を得られる可能性があります。オンラインコミュニティでの発言も有効です。 |
| 関連書籍や資料との比較読書 | 金子氏の著書だけでなく、同じテーマの他の有機農業の専門家の著書や論文なども比較して読んでみましょう。異なる視点やアプローチを知ることで、金子氏の哲学が持つ独自性や普遍性をより明確に理解できます。 |
| ワークショップやセミナーへの参加 | 書籍だけでは得られない実践的なスキルや体験を得るために、有機農業関連のワークショップやセミナーに積極的に参加しましょう。金子氏の教えを受け継ぐ農家が開催しているものも多くあります。 |
これらの方法を組み合わせることで、金子美登氏の著書から得た学びを単なる知識にとどめず、あなた自身の有機農業ライフを豊かにするための実践的な知恵へと変えていきましょう。
家庭菜園で始める無農薬栽培のポイント
有機農業に興味はあるけれど、いきなり大規模な畑を始めるのはハードルが高いと感じる方もいるでしょう。そんな方には、まずは家庭菜園から無農薬栽培を始めてみることをおすすめします。金子美登氏の土づくりの哲学や栽培技術は、小規模なスペースでも実践可能です。
小規模スペースでの土づくり
家庭菜園のような小規模スペースでも、金子美登氏の有機農業の核である土づくりは非常に重要です。健康な土が健康な作物を育むという基本は変わりません。
小規模スペースでの土づくりのポイントは以下の通りです。
| ポイント | 内容 |
| 腐葉土や堆肥の活用 | 購入した市販の腐葉土や堆肥を積極的に使用しましょう。自宅で生ゴミを利用したコンポストを作ることも可能です。土に混ぜ込むことで、有機物を増やし、土壌構造を改善し、微生物の活動を促進します。 |
| 土壌の団粒構造化 | 手で土を握ってみて、塊になるけれど軽く崩れる程度が理想的です。固すぎる土は水はけや通気性が悪く、根が伸びにくいため、腐葉土や堆肥を多めに混ぜて耕しましょう。定期的な土の観察を行い、状態に合わせて有機物を補充します。 |
| 微生物の育成 | 土中の微生物を活性化させるために、化学肥料や農薬の使用は避けます。米ぬかや油かすなどの有機質肥料を少量与えることで、微生物の餌となり、土の生命力を高めます。落ち葉や枯れ草を土の表面に敷くマルチングも、微生物の生息環境を整えるのに役立ちます。 |
| 深耕を避ける | 土中の微生物層や土壌構造を壊さないために、必要以上に深く耕すのは避けましょう。作物の根が伸びる範囲で軽く耕す程度で十分です。根菜類を栽培する場合は、深く耕す必要がありますが、基本的には微生物が頑張る力を信じましょう。 |
| コンパニオンプランツの活用 | 相性の良い植物を一緒に植えることで、病害虫を寄せ付けにくくしたり、生育を助け合ったりする効果があります。例えば、トマトとバジル、マリーゴールドと野菜など、組み合わせを工夫してみましょう。 |
小規模な家庭菜園でも、これらのポイントを実践することで、金子氏の有機農業哲学に基づいた健康で豊かな土を育むことができます。自分で育てた安心安全な野菜を収穫する喜びをぜひ体験してみてください。
手軽に取り入れられる有機JASレベルの技術
家庭菜園で有機JAS認証を取得することは現実的ではありませんが、有機JAS規格が求めるレベルの高い栽培技術を手軽に取り入れることは可能です。金子美登氏の有機農業哲学に基づいて、安心安全な野菜を育てるためのポイントを紹介します。
| 技術ポイント | 内容 | 家庭菜園での応用 |
| 無農薬・無化学肥料栽培の徹底 | 合成農薬や化学肥料は一切使用しないという基本原則を守ります。病害虫の発生を抑えるために、土づくりや適切な栽培管理を行います。 | 市販の農薬や化学肥料の使用をやめ、堆肥や有機質肥料に切り替えます。てんとう虫やカマキリなど、益虫が集まる環境を整えることも有効です。 |
| 輪作の実施 | 同じ場所で同じ作物を連続して栽培せず、異なる科の作物を計画的に栽培します。連作障害を防ぎ、土壌の養分バランスを保ちます。 | プランターや小さな区画でも、栽培記録をつけ、来年は違う種類の野菜を植えるように工夫しましょう。夏野菜の後に葉物野菜を植えるなど、簡単な輪作から始められます。 |
| 緑肥の活用 | 作物を収穫した後や、作物の生育期間中に緑肥作物を栽培し、土中にすき込みます。土壌の有機物を増やし、構造を改善し、雑草を抑制します。 | 小規模なスペースでも、利用できる緑肥(例えば、マメ科のクローバーなど)を活用しましょう。収穫後にすぐに種をまくことで、土を休ませずに有効活用できます。 |
| 病害虫対策 | 物理的防除(手で取り除く、防虫ネットなど)や生物的防除(益虫の活用、コンパニオンプランツなど)を中心に行い、化学農薬には頼りません。 | 虫が見つかったら、手で取り除いたり、木酢液などを薄めて散布したりする方法も有効です。防虫ネットは手軽で効果的な対策です。多様な植物を植えることで、特定の害虫が大量発生するリスクを減らせます。 |
| 種苗の選択 | 有機栽培の種苗を優先的に使用します。農薬処理されていない種子や、遺伝子組み換えでない種子を選びましょう。 | ホームセンターやオンラインストアで、「有機種子」「固定種」「在来種」などの表示がある種子や苗を選んでみましょう。安心して栽培を始められます。 |
これらの技術を家庭菜園に取り入れることで、有機JAS認証の取得はしなくとも、金子美登氏が目指した安心安全で持続可能な野菜づくりを体験できます。自分の手で育てた美味しい野菜は、きっと食卓を豊かにしてくれるでしょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。