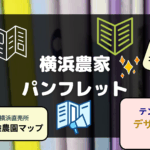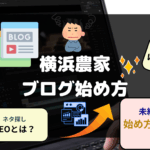農家や農園経営者は、横浜市と神奈川県の補助金・助成金制度を活用すれば、設備投資費用を大幅に抑えつつ生産性向上と持続可能な農業経営を実現できます。初期投資や機械導入の費用に不安を抱える新規就農者や既存農家の方も多いでしょう。
本記事で解説する主な項目は以下のとおりです。
- 横浜市・神奈川県の農家向け補助金制度の概要と対象事業
- 新規就農者向け補助金の支給額・申請条件・手続き
- 各助成金の補助率と上限額(例:補助率50%、上限300万円/1,200万円)
- 申請書類から交付決定、実績報告、精算払いまでの流れと必要書類
- 相談窓口(市役所・県庁・オンライン・電話)と民間サポート、スマート農業・環境保全型支援制度
これらの情報を把握しないと、利用可能な支援を見落とした結果、多額の自己負担を強いられ、事業計画の実行が困難になります。制度要件や申請手続きを今すぐ確認し、農業経営をスムーズに進めましょう。
目次
横浜市・神奈川県の農家・農園向け補助金とは?支援制度の全体像と対象事業
横浜市と神奈川県は、市内の農家向け補助金や農業助成金を通じて、新規就農者の設備投資負担を軽減し、既存農園の機械導入や施設整備による事業拡大・生産性向上を支援しています。そこで、横浜市・神奈川県の農家が対象の農園補助金を賢く使えるよう、以下の2点を解説します。
- 横浜市独自の農家・農園向け補助金制度にはどんなものがある?
- 神奈川県の農業助成金・支援制度とは?
これらの補助金・助成金制度を把握することで、農業経営の初期投資コストを抑えつつ、持続可能な収益モデルを構築できます。制度活用の機会を逃すと、活用可能な支援を見落として余分な費用を負担することになりかねません。支援制度を見逃して後悔しないよう、次の項目から詳細を見ていきましょう。
横浜市独自の農家・農園向け補助金制度にはどんなものがある?
横浜市・神奈川県の農家・農園が利用できる独自の補助金・助成金制度は以下のように多岐にわたります。これらの支援制度を活用すると、農業経営の初期投資を軽減し、事業拡大を効率的に進められます。
| 制度名 | 補助対象者 | 支援内容 |
| 新規就農支援(横浜チャレンジファーマー) | 農業を始める市民・認定新規就農者 | 営農に必要な設備・農地取得費用の50%補助 |
| 既存農家向け設備投資助成 | 経営拡大を目指す農家・農園 | ビニールハウス改修・高性能農業機械導入費用の助成 |
| 環境保全型直接支払交付金 | 環境配慮型農業実践者 | 化学肥料・農薬低減取り組みへの10aあたり単価交付 |
横浜市の農家・農園向け補助金制度の特徴は、新規就農者から既存農業経営者まで幅広い農業者を対象とした支援体制にあります。
横浜チャレンジファーマー制度では、農業未経験者でも2年間の研修を経て認定新規就農者となり、市内農地の借り受けが可能になります。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/20250401hojo.html
また、既存農家・農園向けの設備投資助成では、経営規模拡大や生産性向上を目的とした機械・施設導入を支援し、持続可能な農業経営を推進しています。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/hozyo/hojosyourei.html
神奈川県の農業助成金・支援制度とは?
神奈川県の農家・農園が活用できる助成金・支援制度は以下のように多彩な支援体制を整えています。これらの制度を活用すると、経営多角化や人材育成、技術革新を効率的に進められます。
| 制度名 | 対象者 | 補助額・補助率 |
| 農業経営新規アイデア実現支援 | 販売金額250万円以上・就農4年以上の農家 | アイデア導入:100万円まで(1/3補助)施設整備:500万円まで(1/3補助) |
| 新規就農者育成総合対策(次世代人材投資資金) | 50歳未満の新規就農者・認定新規就農者 | 就農準備:150万円×最長2年間経営開始:150万円×最長3年間 |
| スマート農業推進事業 | 販売農家・農業者団体 | 個人:100万円まで(1/3補助)団体:500万円まで(1/3補助) |
神奈川県の農家・農園向け助成金制度の特色は、経営発展段階に応じた体系的な支援と、先進技術導入への積極的な後押しにあります。
農業経営新規アイデア実現支援では、新品種導入や販売手法革新に加えて施設整備までカバーし、農家・農園の企業経営体への成長を支援します。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/ideajitsugenshien.html
新規就農者育成総合対策では、研修段階から経営安定まで一貫した資金支援を行い、49歳以下の若手農業者の定着を促進しています。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f420464/index.html
スマート農業推進事業では、IoT・自動化機器導入により農作業効率化と労働力不足解決を図り、神奈川県の農業競争力向上を目指しています。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/2023smart_suisinzigyou.html
横浜市の新規就農者が受けられる補助金はいくら?申請条件と手続き方法を解説
横浜市と神奈川県は、市内の農家や農園経営者向けに、初期投資負担を軽減する各種補助金・助成金制度を用意しており、新規就農者の設備導入から既存農家の機械・施設更新まで幅広い支援を行っています。
そこで、まずは横浜市独自の補助金について以下の項目を解説します。
- 横浜市で認定新規就農者になるための条件とは?
- 補助率50%・上限300万円(1,200万円)など、助成金の内訳とは?
- 横浜市の農家補助金申請に必要な書類・提出方法
これらの制度を正確に理解することで、自己資金を抑えながら効率的に農業経営を立ち上げ、持続可能な収益モデルを構築することができます。一方、支援制度を確認せずに申請を進めると、利用可能な補助金を取りこぼして多額の自己負担となってしまう可能性があります。支援制度を見逃して後悔しないよう、次の項目から詳細を見ていきましょう。
横浜市で認定新規就農者になるための条件とは?
横浜市で農家・農園を始めるための認定新規就農者とは、以下のような条件を満たし青年等就農計画の認定を受けた農業者を指します。この認定は横浜市の補助金・助成金制度の基本要件となっています。
| 対象者カテゴリ | 年齢要件 | 主な条件 |
| 新規参入者(認定新規就農者) | 18歳以上45歳未満 | 営農開始5年後に年間農業所得200万円以上の計画策定 |
| 横浜チャレンジファーマー | 18歳以上63歳未満 | 2年間の市研修修了後に青年等就農計画の認定取得 |
| 特定知識・技能者 | 65歳未満 | 3年以上の商工業経営経験または農業関連業務経験 |
横浜市の農家・農園向け補助金申請で最も重要なのは、青年等就農計画の認定を受けることです。この計画では5年以内に農業で安定収入を得られる具体的な営農戦略を示し、市による審査を通過する必要があります。
横浜チャレンジファーマー制度を利用する場合、農業未経験の横浜市民が2年間の実地研修を受講し、修了後に認定新規就農者として農地貸借権を取得できます。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/center/event/challengefarmer.html
認定取得後は、営農開始から5年以内であれば横浜市の設備投資助成金や機械導入補助金の対象となり、農業経営の初期投資負担を大幅に軽減できます。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/20250401hojo.html
補助率50%・上限300万円(1,200万円)など、助成金の内訳とは?
横浜市・神奈川県の農家・農園向け補助金・助成金の補助率と上限額は、以下のように制度ごとに詳細が定められています。多くの制度で補助率50%・上限300万円を基準としつつ、対象経費や申請者の状況により金額が変動します。
| 制度名 | 補助率 | 上限金額 | 対象経費 |
| 横浜市新規就農者農業経営改善支援事業 | 50%以内 | 1事業者300万円 | 農業機械・設備・生産施設・農業生産資材等 |
| 横浜市認定農業者経営改善支援事業 | 50%以内 | 年額50万円 | 農業用機械・設備・生産用施設資材等 |
| 神奈川県新規就農者育成総合対策 | 1/3〜3/4 | 1,200万円 | 機械・施設導入・経営開始資金 |
横浜市の農家・農園向け補助金では、農業生産資材(農薬・肥料等)について年度あたり20万円の補助上限額が別途設定されています。
農業機械・設備の導入補助では、ビニールハウス、灌水設備、トラクター、耕運機といった営農に直接必要な機械・施設が補助対象となります。一方で、土地取得費用や個人の生活費、汎用性の高い機械は補助対象外となることに注意が必要です。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/20250401hojo.html
神奈川県の農業経営新規アイデア実現支援では、アイデア導入で100万円(1/3補助)、施設整備で500万円(1/3補助)と、事業内容に応じて上限額が設定されています。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/ideajitsugenshien.html
補助金額は公募年度の予算状況により変動するため、申請前に最新の募集要項で補助率・上限額を必ず確認することが重要です。
横浜市の農家補助金申請に必要な書類・提出方法
横浜市の農家・農園向け補助金申請に必要な書類は、以下のように事業内容に応じて詳細が定められています。書類不備は審査遅延の要因となるため、提出前のチェックリストによる確認が重要です。
| 書類分類 | 必須書類 | 記載内容と注意点 |
| 基本書類 | 事前審査申込書・事業計画書・見積書の写し | 申請者情報、事業目的・収支計画・資金調達方法を具体的記載 |
| 証明書類 | 認定新規就農者証明書・身分証明書・農地証明書 | 運転免許証等による本人確認(写真なし証明書は2点必要) |
| 参考資料 | カタログ・図面・位置図・工事施工予定地の写真 | 施設整備の場合は現状と計画後の詳細図面が必須 |
横浜市の農業補助金申請では、事前審査と本申請の2段階手続きが基本となっており、それぞれ提出書類が異なります。
事前審査申込では、認定新規就農者・横浜チャレンジファーマーは4月1日〜17日、親元就農者・経営継承者は4月21日〜5月16日が受付期間となっています。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/20250401hojo.html
提出方法は農地の所在区に応じて以下の農政事務所へ直接持参または郵送で行います。
北部農政事務所(都筑区茅ケ崎中央32-1 都筑区総合庁舎4階)
対象区:鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑
電話:045-948-2477 FAX:045-948-2488
南部農政事務所(戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎8階)
対象区:中・西・南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉・瀬谷
電話:045-866-8491 FAX:045-862-4351
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/nouseiannai/nouseibu.html
事前予約制のため、持参時は必ず電話でアポイントメントを取ることが推奨されています。
神奈川県・横浜市の補助金公募期間はいつ?締切を逃さないためのポイント
神奈川県・横浜市の農家・農園向け補助金・助成金の公募期間は、以下のように制度ごとに異なるスケジュールで実施されています。締切を逃さないためには、年間スケジュールの把握と早期準備が重要です。
| 制度名 | 公募期間 | 注意点 |
| 横浜市新規就農者農業経営改善支援事業 | 認定新規就農者:4月1日〜4月17日親元就農・経営継承:4月21日〜5月16日 | 対象者により受付期間が異なる |
| 神奈川県農業経営新規アイデア実現支援 | 8月25日〜10月10日(再募集) | 第1次募集終了後の再募集 |
| 神奈川県スマート農業推進事業 | 通年(予算終了次第締切) | 早期申請で優先審査の場合あり |
横浜市の農業補助金では、認定新規就農者・横浜チャレンジファーマーは4月上旬、親元就農・経営継承者は4月下旬から5月中旬と、対象者カテゴリにより申請期間が分かれています。
事前審査申込は本申請の必須条件となっており、期限内の提出がなければ補助金申請自体ができません。交付決定前の発注・購入は補助対象外となるため、スケジュール管理が重要です。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/20250401hojo.html
神奈川県農業経営新規アイデア実現支援事業では、第1次募集で定員に達しない場合に再募集が実施され、2025年度は8月25日〜10月10日が再募集期間となっています。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/ideajitsugenshien.html
最新の公募情報は各制度の公式サイトで随時更新されるため、申請を検討している農家・農園は定期的な情報確認と、締切1ヶ月前からの書類準備開始が成功のポイントとなります。
横浜市・神奈川県の既存農家・農園がスマート農業導入で受けられる助成金とは?
横浜市と神奈川県は、既存農家や農園がIoT機器やロボット技術を導入する際の初期投資を補助する多様な助成金制度を設けています。これらの助成金を活用することで、農業機械やデータ分析システムへの投資負担を抑え、作業省力化や収益性向上を実現できるので、ここでは以下の内容を解説します。
- 神奈川県のIoT・自動化設備導入で受けられる補助金額はいくら?
- 横浜市の農家向け農業機械導入助成金の対象範囲と補助率
- 神奈川県の農業法人が機械導入する際の特別要件とは?
これらの助成金制度を把握することで、スマート農業導入のコストを最小化し、将来にわたって安定した農業経営を維持できます。一方、支援制度を利用せずに導入を進めると、大規模機器への投資負担が重くなり、労働力不足や生産性低下による競争力の喪失につながる可能性があります。後悔しないよう、次の項目から詳細を確認しましょう。
神奈川県のIoT・自動化設備導入で受けられる補助金額はいくら?
神奈川県の農家・農園が「スマート農業推進事業」で受けられるIoT・自動化設備導入補助金額は、以下のように申請者の規模により設定されています。この制度は農業の省力化・生産性向上を目指す神奈川県の農業者を幅広く支援しています。
| 対象者区分 | 補助率 | 上限金額 | 対象設備・機器 |
| 農業者団体(先進的産地育成事業) | 1/3以内 | 500万円 | 栽培・集出荷・調整作業のスマート化機器データ分析システム等 |
| 個人販売農家(小型機械電動化・自動化支援) | 1/3以内 | 100万円 | 小型農業機械の電動化・自動化機器ロボット技術活用機器 |
| 横浜市スマート農業技術導入支援 | 50%以内 | 50万円 | ICT活用販売支援システム農畜産物販売システム |
神奈川県スマート農業推進事業では、農業者団体が最大500万円、個人農家が最大100万円の補助金を受けられ、導入費用の1/3が補助されます。
対象となるスマート機器は「かながわスマート農業・水産業推進プログラム」のロードマップに記載された機器のほか、栽培・集出荷・調整作業のスマート化に資する機器が幅広く対象となります。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/2023smart_suisinzigyou.html
具体的な補助対象機器には、自動運転トラクター、ドローン、環境制御システム、収穫ロボット、選果・選別機械などがあり、農作業の効率化と労働力不足解決に直結する技術導入を重点的に支援しています。
横浜市独自の「スマート農業技術の導入支援」では、ICT活用販売支援システムの初期導入・設置費用の50%(上限50万円)が補助され、農産物の販路拡大と経営効率化を同時に推進できます。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/hozyo/smartnogyo.html
横浜市の農家向け農業機械導入助成金の対象範囲と補助率
横浜市の既存農家・農園向け農業機械導入助成金は、経営規模拡大や作業効率向上を目的に高性能機械の導入費用を部分的に助成します。以下の範囲と補助率を参考にしてください。
| 機械区分 | 補助対象機械例 | 補助率 | 上限金額 |
| 大型機械 | トラクター、コンバイン、田植え機 | 50%以内 | 300万円 |
| 小規模機械 | 耕運機、草刈り機、選果機 | 50%以内 | 100万円 |
| 施設・設備 | ビニールハウス、灌水設備 | 50%以内 | 200万円 |
助成率はすべて導入費用の50%以内で、上限額は機械区分に応じて設定されています。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/hozyo/hojosyourei.html
大型機械導入では、経営規模や売上高の要件を満たす必要がある場合があります。助成金申請前に、最新の公募要領で対象機械・補助率・上限額を必ず確認しましょう。
神奈川県の農業法人が機械導入する際の特別要件とは?
神奈川県の農業法人が自社の経営規模を拡大して機械導入する際には、個人農家とは異なる支援要件が適用されます。以下の特別要件を満たすと、加算補助や法人向け支援が受けられます。
| 特別要件 | 内容説明 |
| 法人化後の支援フロー | 法人設立後、事務機器導入費用や経営コンサル費用も補助対象となる場合あり |
| 経営規模拡大の加算項目 | 従業員雇用や新農地取得などにより、補助額が上乗せされる制度 |
農業法人向け制度では、法人格取得を契機としたIT機器やコンサルティング費用まで幅広く助成します。また、従業員を追加雇用したり、新たな農地を確保したりすると、加算項目によって基本補助金に上乗せ支援が可能です。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/ideajitsugenshien.html
横浜市・神奈川県の農家が環境保全型農業に取り組むと補助金がもらえる?制度内容と申請方法
横浜市と神奈川県は、環境負荷を抑えた農業技術を導入する農家や農園経営者を対象に、化学肥料・農薬低減や有機農業導入、水田湛水管理などの取り組みを支援する補助金・交付金制度を整備しています。これらの制度を活用すると、持続可能な農業経営を実現しながら農産物のブランド価値を高めることができます。
そこで、以下の制度内容と申請方法を解説します。
- 神奈川県の環境保全型農業支援で対象となる取り組みとは?
- 横浜市の農園経営者向け10aあたりいくら交付される?補助要件と交付単価
環境保全型農業支援制度を正しく把握することで、実施コストを抑えつつ生態系保全と収益性向上を両立できます。制度を知らずに取り組みを進めると、本来得られるはずの補助金を受け取れず、自己負担が増えてしまうおそれがあります。後悔しないよう、次の項目から詳細を確認しましょう。
神奈川県の環境保全型農業支援で対象となる取り組みとは?
神奈川県の環境保全型農業支援は、環境負荷を抑えながら農産物の安全性とブランド価値を高めるための施策です。以下の取り組みが対象となります。
| 施策項目 | 内容 |
| 化学肥料・農薬使用低減 | 化学肥料や化学合成農薬の使用を50%以上削減 |
| 有機農業導入 | 有機JAS認証取得を前提に有機農産物の生産 |
| 温室効果ガス排出削減 | 省エネ機器導入やバイオマス利用でCO₂排出量を削減 |
| 水田湛水管理 | 水田に常時湛水を維持し、湿地環境を活かした生物多様性保全 |
これらの取り組みは、持続可能な農業を実現するだけでなく、消費者に対して安全で環境配慮型の農産物を提供するメリットがあります。ブランド価値向上や新規販路開拓にもつながるため、農家・農園経営者は積極的に導入を検討しましょう。
※参考:環境保全型農業直接支払交付金 – 神奈川県ホームページ
横浜市の農園経営者向け10aあたりいくら交付される?補助要件と交付単価
環境保全型直接支払交付金は、施策ごとに10aあたりの交付単価で支給されます。実際の交付額は年度ごとに公募要領で確定するため、申請前に最新情報を必ずご確認ください。
| 取り組み内容 | 交付単価(10aあたり) |
| 化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組み | 6,000円 |
| 有機農業の導入 | 10,000円 |
| 炭素貯留効果の高い被覆作物の導入 | 8,000円 |
交付要件として、全施策共通で「一定面積以上(例:10a以上)の圃場にて対象施策を実施すること」が求められます。また、作物の種類や栽培方法によって適用条件が異なる場合があるため、公募要領で対象面積・作物区分を確認してください。
※参考:環境保全型農業直接支払交付金 – 横浜市
神奈川県の助成金申請から交付までにかかる期間はどのくらい?
神奈川県の農業助成金は、申請書類の受付から交付決定まで通常2〜3か月程度かかります。提出された書類は農政担当部署で審査され、要件を満たすと交付決定通知が送付されます。この通知を受領してから事業着手できます。
| フロー | 所要期間の目安 |
| 書類受付から審査開始 | 2週間以内 |
| 審査期間 | 4〜8週間 |
| 交付決定通知発送 | 審査完了後1週間以内 |
審査完了後の交付決定通知を受け取るまでは、発注や施工を開始しないでください。通知前に事業を行うと補助対象外となるため、スケジュール管理に留意しましょう。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f420464/index.html
横浜市・神奈川県の農業補助金申請から受給までの流れは?必要な手続きを時系列で解説
横浜市と神奈川県の農家や農園経営者が農業補助金を受給するには、事前審査から本申請、審査、交付決定、実績報告まで、一連の手続きを正確に遂行する必要があります。申請手順をあらかじめ把握することで、申請書類の不備による審査遅延や交付決定後の交付取り消しリスクを回避できます。
ここでは、以下の手続きを時系列に沿って解説します。
- 横浜市の補助金における事前審査の申込方法・必要書類
- 神奈川県における助成金の本申請で提出すべき書類
- 横浜市の補助金審査期間と交付決定の流れ
- 神奈川県の農家向け実績報告書の作成方法と精算手続き
これらの申請・報告手続きを正確に理解することで、補助金を確実に受給し、事業計画どおりに農業経営を進展させることができます。一方で、申請フローを把握せずに手続きを進めると、書類の再提出や期限超過によって補助金を受け取れない事態に陥る可能性があります。次の項目から詳細を確認し、スムーズに補助金を活用しましょう。
横浜市の補助金における事前審査の申込方法・必要書類
横浜市の農業補助金申請では、本申請前に事前審査を受ける必要があります。事前審査の合格が本申請への必須条件です。
| 手続き内容 | 詳細 |
| 申込方法 | 所管の農政推進課窓口への直接持参または郵送※一部制度はオンライン申込も可 |
| 受付期間 | 制度ごとに公募要領で指定(例:4月1日~4月17日) |
| 必要書類 | ・事業計画概要(目的・スケジュール・効果)・設備・機械の正式見積書・認定新規就農者証明書(該当者のみ) |
申込書類に不備があると事前審査に時間がかかるうえ、審査落ちのリスクも高まるため、以下を確認しておきましょう。
- 事業計画概要には、農園規模や生産見込を具体的に記載する
- 見積書は機器・設備の品番や仕様が明記された正式版を使用する
- 認定新規就農者証明書は写しではなく原本確認が必要な場合がある
また、郵送の場合は必ず簡易書留等の追跡可能な方法で送付し、受付期間内に到着するよう余裕を持って手配してください。
これらの注意点を守り、書類を正確に揃えることで、スムーズに事前審査を完了でき、補助金本申請へ円滑に進むことができます。
申込窓口:
横浜市環境創造局 農政推進課 (都筑区茅ケ崎中央32-1 都筑区総合庁舎4階)
電話:045-948-2477/FAX:045-948-2488
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/20250401hojo.html
神奈川県における助成金の本申請で提出すべき書類は何?
事前審査をクリアした後、本申請では審査で不足していた詳細情報や補足書類の提出が求められます。以下の書類を必ず用意してください。
| 書類名 | 記載内容・注意点 |
| 事業計画書 | 事業の目的、実施体制、収支計画を詳細に記載 |
| 資金計画書 | 自己資金・借入金の内訳、返済計画を明確に記述 |
| 施設の図面 | 現状図と改修後図を対比して掲載 |
| 導入機器の見積書 | 品番・数量・単価が明示された正式見積書 |
| 農地賃貸契約書の写し | 賃貸期間・面積が確認できる契約書のコピー |
これらの書類は、制度ごとの交付要綱に基づき要件が細かく定められています。事前に最新の公募要領で必要書類を再確認し、提出漏れや記載不備を防ぎましょう。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f420464/index.html
横浜市の補助金審査期間と交付決定の流れ
横浜市の農家や農園向け補助金を申請した場合、提出した書類をもとに事業計画の妥当性や実現可能性、制度目的との整合性を横浜市環境創造局農政推進課が総合的に審査します。
| フェーズ | 内容 | 目安期間 |
| 書類受理・形式審査 | 提出した申請書類の記載要件や添付書類の確認 | 1週間以内 |
| 本審査 | 事業計画の詳細検討、農園や農業機械導入の現地調査(必要時) | 4~8週間 |
| 交付決定 | 審査合格後、補助金交付決定通知書を郵送 | 審査完了後1週間 |
補助金交付決定通知書には、補助率や助成金上限額、事業完了報告の提出期限などが記載されています。通知を受領してから農家や農園の事業着手が可能となり、交付決定日以降に発注・支払いを行った費用から補助金の対象となります。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/annai/20250401hojo.html
神奈川県の農家向け実績報告書の作成方法と精算手続き
神奈川県の農家が環境保全型農業支援やスマート農業推進事業などの助成金を受け取り後、実績報告書を提出して精算払いを申請します。
| 手続き内容 | 詳細 |
| 実績報告書の作成 | 事業完了後に実施状況・発生経費・事業効果を記載 |
| 添付書類 | 導入機器・設備の領収書コピー施工前後の写真 |
| 提出先 | 神奈川県農政担当部署(郵送またはオンライン提出) |
| 精算払い手続き | 実績報告書審査後に補助金額を算出し、指定口座へ振込 |
実績報告書には補助率・交付単価に基づく経費内訳を明記し、証拠書類として領収書と写真を揃えます。神奈川県が報告書を確認して減額や不備がないと判断すると、交付決定時の補助金額に基づく精算払いが行われます。
※参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f420464/index.html
横浜市の農業補助金はどこに相談すればいい?農家・農園向け窓口一覧と連絡先
横浜市と神奈川県では、農家や農園経営者向けの補助金制度に関する相談窓口を市役所や県庁の公的窓口、さらに専門知識を持つ民間機関で提供しており、申請手続きや事業計画の策定まで幅広くサポートを受けられます。
ここでは、以下の相談先と連絡方法を詳しく解説します。
- 横浜市役所窓口の受付時間と農家向け連絡先
- 神奈川県の補助金オンライン相談は可能?電話・WEBでの問い合わせ方法
- 横浜市の農園経営者向け民間サポートサービスの費用相場と選び方
これらの窓口やサービスを活用することで、補助金制度の適用条件や必要書類、申請スケジュールの疑問を迅速に解消でき、申請ミスや手続き遅延を防げます。逆に、相談先を把握せずに手続きを進めると、不明点を放置して申請書類に不備が生じたり、補助金の受給機会を逃してしまうリスクがあります。安心して補助金申請を進めるために、次の項目から詳細を確認しましょう。
横浜市役所窓口の受付時間と農家向け連絡先
横浜市の農家や農園経営者は、補助金や助成金に関する最新情報を横浜市役所の窓口で確認すると確実です。
| 窓口名称 | 受付時間 | 電話番号 |
| 環境創造局 農政推進課(本庁舎) | 平日 8:45~17:15 | 045-948-2477 |
| 北部農政事務所(都筑区庁舎4階) | 平日 8:45~17:15 | 045-948-2488 |
| 南部農政事務所(戸塚区庁舎8階) | 平日 8:45~17:15 | 045-866-8491 |
各区役所の農政担当部署でも農地に関する補助金や助成金の相談を受け付けています。電話で事前にアポイントを取ると、担当窓口でスムーズに相談できます。
※参考:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/nouseiannai/nouseibu.html
神奈川県の補助金オンライン相談は可能?電話・WEBでの問い合わせ方法
神奈川県の農家や農園経営者は、直接窓口に行かなくてもオンラインや電話で補助金に関する相談ができます。
| 相談手段 | 詳細 | 問い合わせ先 |
| 公式ウェブフォーム | 24時間受付の問い合わせフォームで質問を送信可能回答は数日程度かかる場合あり | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f420464/ |
| コールセンター | 補助金制度ごとに専用番号を設置平日9:00~17:00に対応 | 農政担当部署直通:045-210-3722 |
WEBフォームでは、制度名や質問内容を選択して送信できるため、必要な情報を整理して問い合わせすると回答がスムーズです。電話相談では、担当窓口へ直接つながるため、急ぎの確認や詳細な質問に向いています。
横浜市の農園経営者向け民間サポートサービスの費用相場と選び方
横浜市の農園経営者は、補助金申請や事業計画策定を支援する民間サービスを利用できます。
| サポート機関 | 主なサービス内容 | 費用相場 |
| JA横浜 | 組合員向け補助金情報提供・申請書作成支援 | 無料〜5万円程度 |
| 農業コンサル事業者 | 事業計画立案・申請代行・実績報告支援 | 10万円〜30万円程度 |
| 補助金アドバイザー | 公募要領解説・書類チェック・面談支援 | 5万円〜15万円程度 |
民間サービスを選ぶ際は、以下を参考に検討してください。
- サービス範囲:申請書作成のみか、現地ヒアリングや事業計画策定まで含むか
- 実績・専門性:農業分野での支援実績や専門知識の有無
- 費用体制:固定料金か成功報酬型か
- サポート方法:オンライン対応や訪問サポートの可否
複数の事業者と面談・見積りを比較することで、自分の農園経営に最適なサポートを選べます。
横浜市・神奈川県の農業補助金でよくある質問
Q. 複数の農家補助金を併用できる?※横浜市の新規就農者からよくある助成金関連の質問
A. 横浜市の農業補助金は、原則として同一の導入機器や同一の事業について複数制度を併用できません。ただし、農地取得と農業機械購入など、別々の事業費用であれば複数の補助金を活用できる場合があります。併用可否については、各制度の公募要領をご確認の上、横浜市環境創造局農政推進課へお問い合わせください。
横浜市環境創造局農政推進課
電話:045-948-2477
受付時間:平日 8:45~17:15
Q. 農業関連の機械補助金と設備補助金の違いは?※神奈川県の既存農家・農園からよくある助成金の質問
A. 機械補助金はトラクターや耕運機などの可搬性の高い農業機械導入を支援するもので、農作業の自動化・省力化を目的とします。設備補助金はビニールハウスや灌水システムなどの定置型農業施設導入を支援し、生産環境の整備や品質向上を図ります。
助成金の具体的な適用範囲や補助率については、神奈川県農政部農業施策課へお問い合わせください。
神奈川県農政部農業施策課
電話:045-210-3722
受付時間:平日 9:00~17:00
Q. 農家補助金の審査に落ちた場合、再度申請する方法はありますか?※横浜市の農園補助金申請・実績報告に関する疑問
A. 審査で不採択となった場合でも、翌年度以降に再申請できます。不採択の理由は交付決定通知に記載されるため、その指摘事項を踏まえて事業計画書や添付書類を改善し、再度横浜市環境創造局農政推進課へ申請してください。
横浜市環境創造局農政推進課
電話:045-948-2477
受付時間:平日 8:45~17:15
横浜市・神奈川県の農業補助金を活用して理想の農家・農園経営を実現しよう
横浜市は新規就農者向けに設備投資費用の50%を補助し、上限300万円まで支給する制度を実施しています。神奈川県は既存農家を対象にトラクターやビニールハウス導入費用を助成しています。農家や農園経営者はIoT機器の導入や有機農業への取り組みに対する補助金も利用できます。
横浜市役所や神奈川県庁の窓口、オンライン相談、民間サポート機関を活用して、事前審査から本申請、実績報告までの手続きを正確に進めることで、補助金受給を確実にし、生産性向上と持続可能な農業経営を実現できます。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。