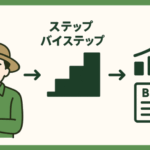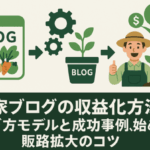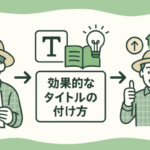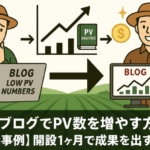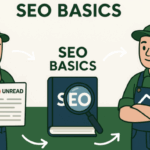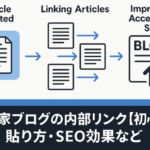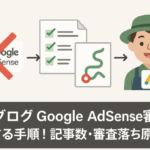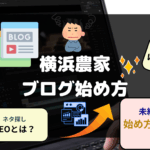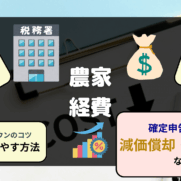日々忙しい農作業の合間を縫ってブログを更新しているのに、「次は何を書こう…」とネタ切れに悩んでいませんか? 頑張って書いたのにアクセス数が伸びず、「このまま続けても意味があるのかな?」とモチベーションが下がってしまうこともあるかもしれません。
この記事では、そんな農家のあなたが抱える悩みを解決するため、ネタ切れの原因から具体的なアイデア、継続するためのツールやコツまで、ブログ運営に役立つ情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、明日からすぐに使えるアイデアが手に入り、ネタ切れの悩みから解放されるでしょう。
逆に、これらの解決策を知らないままだと、貴重な時間を使ってブログを書いても、読者に届かず、せっかくの努力が無駄になってしまうかもしれません。今日からブログ運営を改善し、あなたの想いや農作物の魅力を多くの人に届けましょう。
目次
農家ブログ ネタ切れの原因と根本解決策
農家ブログのネタ切れには、大きく分けて3つの根本原因があります。1つ目は、日々の忙しさからブログに割く時間がないこと。2つ目は、「完璧な記事を書かなければ」というプレッシャーから更新が止まってしまうことです。そして3つ目は、自分の視点だけで記事を書いてしまい、読者が本当に知りたいことが何かを見失っている点です。
これらの原因を放置しておくと、更新が途絶え、せっかく始めたブログが放置されてしまうだけでなく、ファンを獲得する機会や、将来的な収益化のチャンスを失ってしまいます。
このセクションでは、これらの原因を深掘りし、今日から実践できる具体的な解決策を解説します。
なぜネタ切れになるのか?原因分析ワークシート
農家ブログのネタ切れは、「時間がない」「書くことがない」という表面的な理由だけでなく、もっと深いところに原因が潜んでいます。自身のブログ運営を客観的に見つめ直すために、まずは以下の3つの原因と照らし合わせてみましょう。
時間不足と情報整理のギャップ
農作業で1日が終わってしまい、ブログを書く時間がないと感じていませんか?これは、記事のアイデアを「書く直前」に考えていることが原因かもしれません。日々感じたことや、作業の記録をスマホのメモ機能やノートにストックする習慣がないと、いざ書こうと思った時にゼロから考えなければならず、時間だけが過ぎてしまいます。
完璧主義が生む更新停滞
「もっと良い写真がないと」「文章を完璧に仕上げないと」という気持ちから、記事を公開できずにいませんか? 読者はプロのライターが書いた完璧な記事を求めているわけではありません。農家ならではのリアルな声や、人柄が伝わる情報にこそ価値を感じます。完璧主義を手放し、「まずは公開する」というスタンスに切り替えることが重要です。
| 原因 | 具体的な状況 | 解決のヒント |
| 時間不足 | 畑作業で忙しく、ブログを書くまとまった時間がない。 | 休憩時間や移動中にスマホでメモを取る習慣をつける。 |
| 完璧主義 | 記事の質にこだわりすぎて、公開まで時間がかかってしまう。 | 「60点の記事でも公開する」というマイルールを設定する。 |
| 読者視点の欠如 | 自分の日記のような内容ばかりで、読者の反応が薄い。 | 読者のペルソナ(具体的な読者像)を再設定してみる。 |
完璧主義を手放す思考法
完璧な記事を目指すあまり、ブログ更新が停滞してしまうのはもったいないことです。読者はあなたの完璧さよりも、継続して発信される「リアルな情報」を求めています。「まずは60点」の精神で記事を公開することには、多くのメリットがあります。
「まずは60点」で公開するメリット
記事を書き上げるハードルが下がるため、ブログの更新頻度が自然と上がります。継続は力なり。更新頻度が上がれば、読者に忘れられることなく、ブログへのアクセス数も安定します。
PDCAサイクルによる改善フロー
公開した記事にコメントや問い合わせがくれば、それが次の記事ネタになります。読者からの反応は、記事を改善するヒントになるだけでなく、ブログ運営のモチベーションにもつながります。記事を公開し、読者の反応を見る。そして改善点を洗い出し、次の記事に活かす。このPDCAサイクルを素早く回すことで、ブログはどんどん成長していきます。完璧主義を手放し、まずは「伝える」ことを優先してみましょう。
ペルソナ(読者像)を再設定して視点チェンジ
ネタ切れの根本原因の一つに、読者視点の欠如があります。誰に向けて書いているのかが曖昧なままでは、書くべきテーマもぼやけてしまいます。ブログの読者像(ペルソナ)を具体的に再設定することで、ネタ切れを根本から解決できます。
30~50代農家の具体的ペルソナ例
たとえば、あなたの農園で採れた野菜を使ったレシピを紹介するブログなら、「30代、共働きの主婦」をペルソナに設定してみましょう。彼女は、仕事や子育てに忙しく、手軽に作れる健康的で美味しいレシピを探しています。このようなペルソナ像を明確にすることで、「時短でできる野菜レシピ」「子どもの好き嫌いをなくす調理法」など、具体的な記事ネタがどんどん浮かんできます。
アンケート・コメントから得るインサイト
すでにブログを運営しているなら、読者からのコメントやアンケートは宝の山です。寄せられた質問や感想を分析することで、読者が本当に知りたいこと、抱えている悩みが明らかになります。
例えば、「この野菜、どうやって保存すれば長持ちしますか?」という質問が多ければ、「野菜の鮮度を保つ保存法」という記事を作成できます。読者の声に耳を傾けることで、ネタは尽きなくなります。
農家 ブログ ネタ アイデア8選|農作業~地域イベントまで
ネタ切れの根本原因を理解したところで、次は具体的な記事ネタのアイデアを見ていきましょう。ブログネタは、特別な出来事だけでなく、普段の農作業の中に隠されています。ここでは、すぐに実践できる8つのアイデアと、それぞれのネタを魅力的な記事にするためのポイントをご紹介します。
栽培・野菜・作物の生育記録をネタ化
日々変化する野菜や作物の様子は、農家ならではの貴重なコンテンツです。写真や動画を使い、種まきから収穫までの成長過程を記録することで、読者はあなたの作物に愛着を持ってくれます。
| フォーマット | 記載内容 | 読者が得られるメリット |
| 生育日誌 | 日付、天候、生育状況(大きさ、色など)、作業内容(水やり、追肥など) | 作物の成長を一緒に見守る体験ができる。農作業の年間スケジュールを把握できる。 |
| 作業記録 | どんな農機具を使ったか、作業の工夫、苦労した点など | リアルな農作業の様子が分かり、共感が生まれる。 |
季節ごとの農作業ルーティン紹介
読者は「季節によってどんな作業をしているのか?」という農家の日常に興味を持っています。春の種まき、夏の水やり、秋の収穫、冬の土づくりなど、季節ごとのルーティンを解説することで、読者は農作業への理解を深め、あなたのブログのファンになってくれるでしょう。
| 季節 | 記事ネタの例 | 盛り込むべきポイント |
| 春 | 種まき、苗の定植、土づくり | 使う道具、種まきから発芽までの期間、土づくりのコツ |
| 夏 | 水やり、草取り、病害虫対策 | 水やりのタイミング、効果的な草取りの方法、自然な病害虫対策 |
| 秋 | 収穫、次期作の準備 | 収穫のサイン、保存方法、収穫祭などのイベント情報 |
| 冬 | 畑の片付け、来年の計画、農閑期の過ごし方 | 冬の間にやるべきこと、休むことの重要性、農家としての目標 |
失敗談・トラブル体験で共感を呼ぶ
失敗談は、読者からの共感を呼ぶ最高のコンテンツです。失敗の原因、そこから学んだ教訓、再発防止策などを正直に語ることで、読者はあなたに親近感を抱き、応援したいと思ってくれるでしょう。
たとえば、「台風でせっかく育てた作物が…」といった失敗談は、読者の心を動かす力があります。
収穫イベント・地域行事レポート
収穫体験イベントや地域の祭りなど、農園で行われるイベントの様子をレポートするのも良いアイデアです。イベントの告知だけでなく、当日の様子を写真や動画で伝えることで、イベントに参加できなかった人にも雰囲気を伝えられます。
また、告知記事を書く際には、イベント内容、日時、場所、参加費などを明確にし、検索されやすいキーワードを含めることで、集客にもつながります。
農機具・おすすめツールの使い方解説
あなたが普段使っている農機具や便利なツールのレビュー記事は、同じ悩みを持つ農家にとって非常に役立つ情報です。新旧ツールの比較、選び方のポイント、実際の使用感などを詳しく解説することで、専門性の高いブログとして評価されます。
料理・レシピ(野菜レシピ)投稿で幅を広げる
あなたの農園で採れた野菜を使ったレシピは、読者の食卓に直結する人気のコンテンツです。簡単なレシピから本格的なレシピまで、幅広く紹介することで、読者は「この野菜を買ってみたい」と感じ、購買意欲につながります。
Q&A形式で読者の悩みを直接解決
読者から寄せられる質問をQ&A形式でまとめて記事にすることで、読者の悩みを直接解決できます。質問は、ブログのコメント欄やSNS、アンケートなどで収集しましょう。質問と回答をセットで掲載することで、読者は知りたい情報を素早く見つけられます。
農業ニュースを農家目線で切り取る
農業に関するニュースやトレンドを、農家ならではの視点で解説する記事も有効です。政府の補助金制度、新しい栽培技術、食の安全に関するニュースなど、世間の関心が高いテーマを扱うことで、読者の注目を集められます。
農家ブログ ネタ帳の作り方|更新 継続のルーティン設計
ネタのアイデアはたくさんあっても、それをどうやって管理し、日々のブログ更新につなげていくかが重要です。このセクションでは、ネタ切れを未然に防ぎ、ブログ更新を習慣化するための「ネタ帳の作り方」と「更新継続のルーティン」を解説します。
週次/月次のネタ会議フォーマット
一人でブログを運営している場合でも、「ネタ会議」と称して、週に一度や月に一度、ブログのアイデアを考える時間を設けてみましょう。これは、行き当たりばったりな更新を防ぎ、計画的にコンテンツを作成するために非常に有効です。
| 項目 | 内容 | 目的 |
| 議題設定 | 読者からのコメントや問い合わせ、SNSで話題になっていること、季節のイベントなど、テーマの候補を洗い出す。 | 記事ネタの方向性を決める。読者のニーズに沿った企画を立てる。 |
| アイデア出し | 候補の中から、どんな記事が書けるか、見出しはどんなものが良いかなどを自由に書き出す。 | 多くのアイデアを出すことで、記事の幅を広げる。 |
| 優先順位付け | 公開したい時期や、書くのにかかる時間、読者の関心度などを考慮して、公開する記事を決める。 | 計画的なブログ運営を可能にする。 |
記事ネタカレンダー(畑の日常・収穫イベント)
ネタを思いついただけでは、いつ公開するのかが曖昧になり、結局は書かずに終わってしまうことがあります。そこで役立つのが、「記事ネタカレンダー」です。
ExcelやGoogleカレンダーなどを使い、1年間の農作業やイベントの予定を書き込み、それに合わせてブログの公開スケジュールを立てていきましょう。
| 期間 | 畑の日常のネタ | 収穫・イベントのネタ |
| 春 | 種まきのコツ、育苗の様子、土作りの重要性 | タケノコ掘り体験、春野菜の収穫祭り |
| 夏 | 水やりや草取りの苦労話、夏野菜の成長記録 | トマト狩り、夏祭りへの出店 |
| 秋 | 収穫の喜び、新米の紹介 | 稲刈り体験、地域の物産展 |
| 冬 | 来年の作付け計画、農閑期の過ごし方 | 冬野菜の収穫、地域の伝統行事 |
このようにカレンダーに書き込んでおくことで、常に先のネタがストックされている状態になり、ネタ切れの心配がなくなります。
読者アンケートで欲しいテーマを掘り起こす
ネタ帳が尽きてしまったら、読者に直接聞いてみるのが一番です。
ブログのコメント欄、SNS、メールマガジンなどで「どんな記事が読みたいですか?」とアンケートを取ってみましょう。GoogleフォームやTypeformといった無料ツールを使えば、簡単にアンケートを作成・集計できます。
「野菜のおすすめの保存方法は?」「〇〇の育て方をもっと詳しく知りたい」といった具体的な意見は、読者が本当に求めている記事につながります。
アイデアストック術(ツール&思考法活用)
アイデアは、いつどこで生まれるか分かりません。思いついた時にすぐにメモできるように、自分に合った「アイデアストック術」を確立しましょう。
| 方法 | おすすめツール | ポイント |
| メモ | Evernote、Notion | スマホ、PCなど複数の端末で同期できるツールを使う。写真や音声も一緒に保存できると便利。 |
| マインドマップ | XMind、MindMeister | 一つのキーワードから連想ゲームのようにアイデアを広げていく。思考の整理に役立つ。 |
農作業中に思いついたことはスマホに音声メモとして記録し、家に戻ってからEvernoteにテキストとして整理するなど、複数のツールを組み合わせるのも効果的です。
ブログネタ探し ツール比較|キーワード選定に役立つ無料サービス
ブログネタのアイデアはたくさんあるものの、「本当に読者に読まれるネタなのか?」と悩んでしまうこともありますよね。そこで役立つのが、キーワード選定ツールです。これらのツールを使えば、読者が実際に検索しているキーワードを見つけ出し、需要のある記事を書くことができます。
ラッコキーワードなどサジェストツール活用術
「ラッコキーワード」や「関連キーワードツール」のようなサジェストツールは、Googleで検索したときに表示される予測キーワード(サジェスト)を大量に取得してくれる便利なツールです。
- キーワード深掘りの手順
- まず、中心となるキーワード(例:「農家 ブログ」)を入力します。
- ツールが自動で表示する関連キーワード(例:「農家 ブログ 稼ぐ」「農家 ブログ 収益化」)を確認します。
- さらに、その関連キーワードを再検索して、より具体的なネタを探していきます(例:「農家 ブログ 収益化 アフィリエイト」)。
このようにして、読者の悩みを深掘りしていくことで、具体的な記事ネタが見つかります。
Googleキーワードプランナーで検索ボリューム調査
キーワードプランナーは、Googleが提供する無料ツールで、キーワードの検索ボリューム(月間の検索回数)を調べることができます。
- 効果的な絞り込みフィルタ設定
- 検索ボリューム: 検索ボリュームが大きすぎるとライバルも多いため、初心者のうちは検索ボリュームが少ないキーワードを狙うのがおすすめです。
- 競合性: 競合性が低いキーワードは、上位表示されやすいため、積極的に狙っていきましょう。
キーワードプランナーを活用することで、効率的に読者のニーズに応える記事を作成できます。
共起語リスト(悩み・初心者・アクセス・収益化など)の抽出方法
「共起語」とは、特定のキーワードと一緒に頻繁に使われる言葉のことです。共起語を記事に含めることで、記事の網羅性が高まり、Googleからの評価も上がりやすくなります。
- 共起語取得ツールの使い方
- 中心となるキーワード(例:「ブログ ネタ切れ」)をツールに入力します。
- ツールが抽出した共起語(例:「悩み」「解決」「対策」「方法」「初心者」など)をリストアップします。
- これらの共起語を、見出しや本文に自然な形で組み込んで記事を執筆します。
共起語リストを作成することで、読者が知りたい情報を網羅した、質の高い記事が作れます。
SNS/YouTubeトレンド検索で新鮮ネタをキャッチ
キーワードツールだけでは見つからない、今まさに話題になっているネタを探すには、SNSやYouTubeが最適です。
- ハッシュタグ・トレンドワードの選定基準
- Twitter(X): 「#農業」「#農家と繋がりたい」といったハッシュタグをチェックし、リアルタイムで話題になっていることを探します。
- YouTube: 農業系のチャンネルをいくつか登録しておき、人気の動画やコメント欄からネタのヒントを得ます。
これらの情報を活用することで、読者の関心が高い、新鮮なネタを素早く見つけることができます。
農家 ブログ SEO 対策|検索ニーズを満たす記事構成の基本
せっかく良い記事を書いても、読者に見つけてもらえなければ意味がありません。ここでは、検索エンジンで上位表示されやすくなる「SEO(検索エンジン最適化)対策」の基本について解説します。読者の検索ニーズを深く理解し、それに応える記事構成を意識することが重要です。
ペルソナ設定とターゲット読者像の明確化
SEO対策の第一歩は、記事を読む「ペルソナ」を具体的に設定することです。誰に向けて書くのかを明確にすることで、読者の心に刺さる記事が書けます。
- ペルソナシート記入例| 項目 | 内容例 | なぜ重要なのか ||—|—|—|| 名前 | 佐藤 花子 | 読者を具体的な個人としてイメージするため。 || 年齢・職業 | 35歳・共働き主婦 | ライフスタイルや課題を想定するため。 || 悩み | 「仕事が忙しく、子供に安心して食べさせられる野菜の選び方がわからない」 | 読者が検索するキーワードや解決策を考えるヒントになる。 || 情報ニーズ | 「簡単で健康的な野菜レシピ」「有機野菜の選び方」 | 記事のテーマや内容を決定する上で最も重要な要素。 |
ペルソナを設定することで、読者がどんなキーワードで検索し、何を知りたいのかが明確になります。
記事タイトルに含めるサジェストキーワード・再検索キーワード
記事のタイトルは、検索結果でクリックされるかどうかの重要な要素です。読者の興味を引き、かつ検索エンジンに評価されるタイトルをつけましょう。
- 魅力的な数字・ベネフィット表現
- サジェストキーワードの活用: 「農家 ブログ ネタ切れ 解消方法」のように、読者が検索するキーワードをタイトルに含めます。
- 再検索キーワードの盛り込み: 「農家ブログのネタ切れを防ぐ8つのアイデア」のように、記事の内容を具体的に伝えることで、クリック率が向上します。
- ベネフィットを伝える: 「誰でもできる!」や「初心者向け」といった言葉を入れることで、読者が記事を読むメリットを提示します。
h2・h3見出しへのキーワード組み込みテクニック
記事の見出しは、読者が記事全体の内容を把握するために使います。また、Googleも記事の内容を理解するために見出しを読みます。
- 見出し最適化のチェックリスト
- 見出しにキーワードを入れる: 見出しにキーワードを含めることで、読者の検索意図に沿った記事であることが伝わります。
- 見出しだけで内容がわかるようにする: 見出しを読むだけで、記事に何が書かれているのかがわかるように構成しましょう。
- 階層構造を意識する: h2→h3→h4と、論理的な階層構造を守ることで、読みやすさが向上し、SEO評価も高まります。
内部リンク・外部リンクでサイト滞在時間を伸ばす
記事内で関連する他の記事へのリンクを貼ることを「内部リンク」、他の信頼できるサイトへのリンクを貼ることを「外部リンク」といいます。
- 関連コンテンツマップ作成法
- 内部リンク: 「このテーマについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください」のように、読者の興味を引く形で関連記事へ誘導します。
- 外部リンク: 記事の内容を補足するような公的機関のデータや信頼性の高い情報源にリンクを貼ることで、記事の信頼性が高まります。
内部リンクを最適化することで、読者がブログ内を回遊し、サイトの滞在時間が伸びるため、SEOに良い影響を与えます。
農家ブログ 成功事例&収益化|稼ぐアフィリエイト戦略
ブログを継続するモチベーションの一つに、「収益化」がある人もいるのではないでしょうか。ここでは、農家ブログならではの強みを活かした収益化の方法と、ブログを成功させるための具体的な戦略をご紹介します。ただ商品を売るのではなく、ファンを増やしながら収益につなげる方法を解説します。
直販サイト・EC連携でファンを育てる方法
農家ブログ最大の強みは、生産者が直接情報を発信できることです。収益化の最もシンプルで強力な方法は、ブログから直接、自身が育てた野菜や加工品を販売することです。
- 導線設計とCTA配置ポイント
- 導線設計: 記事の中で商品の魅力(美味しさ、安全性など)を伝え、自然な流れで直販サイトやECサイトへ誘導します。例えば、収穫の様子を伝えた記事の最後に「採れたて野菜のご購入はこちらから」といった一文を添え、リンクを貼ります。
- CTA(Call to Action): 読者の行動を促すボタンやテキストを配置します。「今すぐ購入する」「旬の野菜セットを見てみる」といった、具体的で分かりやすい言葉を使いましょう。
アフィリエイト農業商材の選び方と掲載ポイント
自分の農産物だけでなく、アフィリエイトを活用して関連商品をブログで紹介することも収益化につながります。
- ASP選定基準と報酬比較
- ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ): 農機具、種、肥料、作業着など、農業に関連する商品を扱っているASPを選びます。
- 報酬比較: 同じ商品でもASPによって報酬額が異なる場合があるため、複数のASPを比較検討しましょう。
- 選び方と掲載ポイント: 実際に自分が使って「本当に良い」と思った商品だけを紹介することが重要です。正直な感想やレビューを交えることで、読者からの信頼を得られます。
読者コミュニティ運営で収益化を加速
ブログでファンになった読者と、より深い関係性を築くためにコミュニティを運営するのも良い方法です。
- LINE公式・Facebookグループ活用術
- LINE公式アカウント: 新商品の販売開始やブログ更新情報など、最新情報をいち早くファンに届けられます。
- Facebookグループ: コミュニティ内でしか話せない情報や、メンバー限定のイベントなどを企画することで、ファンのエンゲージメント(結びつき)を高めることができます。
- コミュニティ限定商品: コミュニティのメンバーだけが購入できる限定商品を用意することで、収益化とファン化の両方を加速させることが可能です。
ブログを通じて得た信頼をコミュニティでさらに深めることで、長期的な収益につながる関係性を築くことができます。
素敵な未来を手に入れるための農家ブログ運営のコツを意識して、うまく困難を乗り越えよう!
ここまで、農家ブログのネタ切れ解消法から収益化まで、さまざまな角度から解説してきました。最後に、これらの知識を活かし、ブログ運営を楽しみながら継続していくためのマインドセットと具体的なコツをお伝えします。ブログは単なる情報発信ツールではなく、あなたと読者をつなぐ大切な財産です。
記事更新を習慣化し、アクセスと収益化を両立するロードマップ
ブログの成長には「継続」が不可欠です。しかし、忙しい農作業の合間に更新を続けるのは容易ではありません。そこで、無理のない範囲で続けられるロードマップを作りましょう。
- 30日チャレンジプランの例
- 【1~7日目】:ネタ出しとキーワード選定に集中する。
- 【8~14日目】:記事の構成案を作成し、見出しを書き出す。
- 【15~21日目】:本文の執筆に集中する。
- 【22~28日目】:推敲、画像の挿入、装飾を行う。
- 【29~30日目】:記事を公開し、SNSで告知する。
このように、作業を細分化することで、一つの記事を完成させるまでのハードルが下がり、継続しやすくなります。
今日から始めるネタ帳作成+ツール活用ステップ
ネタ切れを防ぐ最も効果的な方法は、日々の生活からネタをストックする習慣をつけることです。今すぐに始められる具体的なステップをご紹介します。
- 初期セットアップチェックリスト
- ツールを選ぶ: スマートフォンのメモアプリ、Evernote、Notionなど、自分が使いやすいツールを一つ選ぶ。
- ルールを決める: 「毎日、寝る前にその日の出来事を3つメモする」「毎週日曜日にメモを見返して整理する」など、簡単なルールを設定する。
- カレンダーと連携する: Googleカレンダーに「ブログネタ出しの日」として予定を入れ、強制的にネタを考える時間を作る。
迷ったら戻る「ブログネタ切れ解消フロー」の活用法
ブログを運営していると、必ず「何を書けばいいか分からない」という壁にぶつかります。そんな時は、このフローチャートに戻って、今やるべきことを見つけ出しましょう。
- フローチャート&テンプレートダウンロード案内
- STEP 1: ネタ切れの原因を特定する
- 「時間がない?」→「ネタ帳」をチェック
- 「書くことがない?」→「キーワードツール」で検索
- 「読者がわからない?」→「ペルソナ」を再設定する
- STEP 2: 具体的なアイデアを出す
- 農作業、失敗談、レシピ、ツールレビューなど、8つのアイデアを参考に、書けそうなネタを探す。
- STEP 3: 記事を書き始める
- 完璧主義を手放し、「60点」でもいいので、まずは書き始める。
- STEP 1: ネタ切れの原因を特定する
これらのフローを定期的に見直すことで、あなたはもうネタ切れで悩むことはなくなるはずです。農家ブログの運営は、あなたの思いを読者に届ける素晴らしい旅です。ぜひ、楽しみながら続けていってください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。