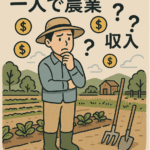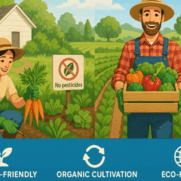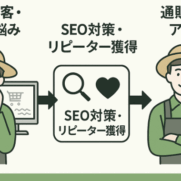定年を迎え、これからのセカンドキャリアをどう築くか悩んでいませんか?「何か新しいことに挑戦したいけれど、体力的に無理はしたくない」「年金だけでは少し不安」「地域社会との繋がりを持ち続けたい」そうお考えの方にとって、農業は新たな生きがいと収入をもたらす魅力的な選択肢となり得ます。実は今、日本の農業は深刻な人手不足と高齢化に直面しており、あなたの持つ豊富な経験と知識が、まさに求められているのです。
この記事では、「高齢者 農業 働き手」として活躍するために知っておきたい、農作業がもたらす健康メリットから、具体的な求人の探し方、国や自治体の支援制度、そして安心して働くための注意点まで、必要な情報を網羅的に解説します。
この記事を読めば、農業で働くことの具体的なイメージが湧き、ご自身の希望に合った働き方を見つけるヒントが得られるでしょう。また、安心して就農するための支援制度や安全対策を知ることで、不安なく最初の一歩を踏み出せます。
逆に、これらの情報を知らずに漠然と農業を始めようとすると、「思っていたより大変だった」「自分に合った仕事が見つからない」「支援制度があることを知らなかった」といった後悔に繋がる可能性があります。最適な働き手としての道を歩むためにも、ぜひ本記事で提供する情報を活用してください。
目次
深刻化する農業の「人手不足」と「高齢化」の現状
農業は日本の食を支える重要な産業ですが、人手不足と高齢化という喫緊の課題に直面しています。この章では、現在の農業が抱える具体的な状況と、なぜ高齢者がその解決の糸口として注目されているのかを解説します。
統計が示す農業従事者の「高齢化」と「減少」
日本の農業を支える担い手の状況は、年々厳しさを増しています。具体的なデータから、その現状を深く掘り下げていきましょう。
日本の農業を支える「平均年齢68.7歳」の実態
農業従事者の高齢化は、データからも明らかです。
令和5年(2023年)の基幹的農業従事者の平均年齢は68.7歳となっており、高齢化が進行しています。
根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html
特に、平均年齢が上昇し続けている背景には、後継者不足と新規就農者の減少が挙げられます。
半減した「基幹的農業従事者数」が示す労働力不足
農業における労働力不足は深刻で、基幹的農業従事者数の推移を見ても明らかです。
基幹的農業従事者数は2000年の240万人から2023年には116.4万人へ約半減しています。
根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r5/r5_h/trend/part1/chap4/c4_2_00.html
この大幅な減少は、農業生産力の維持に大きな影響を与えています。
なぜ「高齢者」が農業の「働き手」として注目されるのか
このような現状の中、定年退職者やリタイア世代のシニア層が、新たな働き手として期待されています。彼らが持つ可能性とは何でしょうか。
定年退職者・リタイア世代が持つ「労働力」としてのポテンシャル
65歳以上の高齢者が農業従事者の大部分を占める現状において、彼らの労働力としてのポテンシャルは非常に高いと言えます。
65歳以上が全体の70.2%を占める中、新規就農者数の増加が求められています。
根拠URL:https://www.jasso.go.jp/gakusei/career/event/guidance/__icsFiles/afieldfile/2023/06/06/6nourin.pdf
特に、健康で活動的なシルバー世代は、農業の現場に新たな活力を与える存在です。
シニア世代の「知識」と「経験」が農業にもたらす価値
長年の人生経験で培われた知識やノウハウは、農業の現場でも大いに活かされます。
高齢農業者が持つ豊富な経験は、地域農業の持続可能性向上につながります。
根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r5/r5_h/trend/part1/chap4/c4_2_00.html
若手就農者への技術継承や、地域コミュニティにおける活性化の鍵となることが期待されています。
高齢者が農業で働く「メリット」──健康・生きがい・経済的恩恵
高齢者が農業で働くことは、単に人手不足の解消だけでなく、働く本人にとっても多大なメリットをもたらします。この章では、その具体的な恩恵を多角的に掘り下げます。
農作業がもたらす「健康効果」を科学する
農作業は、体を動かすことで身体的な健康維持に繋がり、さらには精神的な健康にも良い影響を与えることが知られています。
土いじりが「認知症予防」に繋がるメカニズム
農作業は、脳の活性化を促し、認知症予防に有効であると考えられています。
土いじりは脳を活性化し、認知症予防に有効とされています。
根拠URL:https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/nkk/2007/nkk07-17.html
手を動かす、作物の成長を観察するといった行為が、認知機能の維持に貢献するのです。
「筋力維持」と「リハビリ効果」で生涯現役をサポート
農作業は、全身運動を伴うため、筋力維持や体力向上に役立ちます。
日常的な野菜収穫作業は筋力維持やリハビリテーションにも役立ちます。
根拠URL:https://vegimo.jp/read/green-reha
無理のない範囲での軽作業や短時間のパート勤務など、個人の体力に合わせた働き方が可能です。
農業が育む「生きがい」と「社会参加」の促進
定年退職後、新たな生きがいを見つけることは多くの高齢者にとって重要な課題です。農業は、この課題に対する有効な解決策となり得ます。
種まきから収穫まで──「達成感」の得られる作業プロセス
自ら育てた作物が成長し、収穫に至る過程は、大きな達成感をもたらします。
種まきから収穫までの一連作業は高齢者に大きな達成感をもたらします。
根拠URL:https://inaka-pipe.net/20160611/
このやりがいは、日々の生活にハリを与え、精神的な豊かさへと繋がります。
地域の絆を深める「社会参加」と「交流機会」
農業を通じた社会参加は、地域コミュニティとの繋がりを強化します。
農作業グループ活動は孤立を防ぎ、地域の絆を深めます。
根拠URL:https://www.minnanokaigo.com/news/kaigo-text/dementia/no236/
農家や地域の人々との交流は、高齢者の孤立を防ぎ、生きがいを深める上で不可欠な要素です。
農業で得る「収入」確保と「年金補完」の選択肢
高齢者にとって、年金だけでは生活が不安というケースも少なくありません。農業は、年金補完や収入確保の手段としても注目されています。
「パート・アルバイト・季節労働」で安定した収入を
自身のライフスタイルや体力に合わせて、パート、アルバイト、季節労働といった形で農業に携わることができます。
パートや季節労働を活用することで、年金に加え安定した収入を得られます。
根拠URL:https://www.baitoru.com/kw/%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%80%80%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%80%80%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%80%80%E6%BC%81%E6%A5%AD%E3%80%80%E6%9E%97%E6%A5%AD/
短時間や軽作業の求人も増えており、無理なく働くことが可能です。
「副業」としての家庭菜園や生産物販売の可能性
本格的な就農だけでなく、自宅の家庭菜園で収穫した作物を販売し、副収入を得るという選択肢もあります。
自宅菜園での生産物販売は、年間数万円〜十数万円の副収入を生みます。
根拠URL:https://sharebatake.com/blogs/read/499
直売所やフリマアプリなどを活用することで、気軽に収益化を目指せます。
定年帰農をめざすシニアのための「求人・パート」探しガイド
定年帰農やセカンドキャリアとして農業を始めたいシニアにとって、具体的な求人の探し方や応募のコツは非常に重要です。この章では、効果的な就職活動の方法を解説します。
高齢者向け「農業求人サイト」活用術
高齢者向けの農業求人に特化したサイトを活用することで、効率的に仕事を見つけることができます。
「あぐりナビ」「農家のおしごとナビ」の特徴と活用法
農業分野に特化した求人サイトは、多くの高齢者向け案件を扱っています。
『あぐりナビ』は高齢者向け求人が約40%を占め、軽作業案件が豊富です。
根拠URL:https://minorasu.basf.co.jp/81092
「農家のおしごとナビ」なども含め、サイトごとの得意分野を理解し、自身の希望に合った求人を探しましょう。
効率的な「検索ワード」と「地域名」の組み合わせ方
求人サイトでの検索時には、適切な検索ワードを用いることが重要です。「高齢者 農業 求人」だけでなく、さらに絞り込むために地域名を加えるのがおすすめです。
検索候補に地域名を加えることで、最適な求人が見つかりやすくなります。
根拠URL:https://jp.indeed.com/q-%E8%BE%B2%E6%A5%AD-%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88-l-
「シニア 農業 パート 埼玉」のように具体的に入力することで、希望に近い案件が見つかりやすくなります。
シニア向け「農業パート」を見つけるコツと応募準備
高齢者が無理なく働ける短時間や軽作業のパート案件を見つけるには、いくつかのコツがあります。
「短時間・軽作業」求人の効率的な探し方
体力に不安がある高齢者でも安心して働ける短時間や軽作業の求人は、近年増加傾向にあります。
週2日・4時間から働ける案件は、体力に自信のない高齢者にも人気です。
根拠URL:https://sumikominavi.com/job/special.php?tab=1&sp=623
農場の種類や作物の種類によって作業内容は異なるため、事前に確認することが大切です。
面接前に準備すべき「自己PR」と「体力面の自己管理」
農業未経験者であっても、これまでの社会経験や、体力面での自己管理能力をアピールすることは可能です。
農業の基礎知識や体力面の自己管理プランをまとめた履歴書を用意しましょう。
根拠URL:Yahoo!知恵袋(例)
「健康維持のために農作業をしたい」といった意欲も、積極的に伝えましょう。
「シルバー人材センター」「自治体窓口」の賢い利用方法
高齢者の就労支援を行う公的な機関も、農業で働く上で大きな助けとなります。
「シルバー人材センター」の登録手順と利用メリット
シルバー人材センターは、高齢者の生きがいや社会参加を目的とした就業機会を提供しています。
シルバー人材センターの登録費用は無料、年会費も不要です。
根拠URL:https://www.silver-jinzai.jp
地域に密着した求人が多く、軽作業や短時間の案件も豊富です。
各「自治体」の「農政課」や「農業委員会」を活用する
自治体の農政課や農業委員会では、地域の農業振興のために高齢者の就労を支援する取り組みを行っている場合があります。
自治体の農政課Webサイトで「高齢者 農業」をキーワード検索しましょう。
根拠URL:各市町村公式サイト
補助金や助成金、支援制度といった情報も得られる可能性があります。
高齢者が農業を始めるための「支援制度」と「研修」
農業未経験の高齢者が就農するには、知識やスキルの習得が不可欠です。国や自治体、民間団体が提供する様々な支援制度や研修プログラムを活用することで、安心して農業を始めることができます。
シニア向け「新規就農支援制度」の活用
国の「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)」概要と対象
新規就農者を支援するための国の制度は、高齢者も対象となる場合があります。
「農業次世代人材投資資金」は、原則49歳以下の者を対象としていますが、特例的に年齢制限を設けない場合もあります。
根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/pdf/1-2-03.pdf
詳細は各都道府県の農政担当部署に問い合わせが必要です。
各自治体独自の「高齢者就農支援プログラム」事例
多くの自治体が、地域の人手不足解消と活性化を目指し、独自の高齢者向け就農支援プログラムを提供しています。
多くの自治体で、研修費補助や農機具購入補助など、高齢者の新規就農をサポートする制度が整備されています。
根拠URL:https://deep-valley.jp/news/news2227/
地方移住と合わせて農業を始める方には特に有益な情報です。
農業未経験でも安心!「研修」と「学習機会」
「農業法人」での実践的なOJT研修と雇用条件
農業法人では、働き手として雇用されながら、現場で実践的なスキルや知識を学ぶOJT研修を受けられる場合があります。
農業法人では、OJTを通じて未経験者も実践的なスキルを習得できます。雇用条件は会社により異なりますが、社会保険完備のケースも多いです。
根拠URL:https://inochio.co.jp/column/39/
正社員だけでなく、パートやアルバイトでの研修機会も存在します。
「市民農園」「体験農園」で農業を学ぶステップ
本格的な就農の前に、まずは市民農園や体験農園で農作業を体験し、農業への適性を確認することもできます。
市民農園や体験農園は、気軽に農業を始めることができ、基本的な知識や技術を学ぶのに適しています。
根拠URL:https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F14091596
これらの施設は、「農業体験 高齢者」といったサジェストキーワードで検索することで見つけられます。
「農福連携」を通じた新たな就労モデル
「農福連携」の概念と高齢者の社会参加
農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者や高齢者などの就労困難者が農業に携わることで、生きがいの創出や社会参加を促す取り組みです。
農福連携は、農業分野での雇用創出を通じて、高齢者の社会参加を促進し、生きがいを提供します。
根拠URL:https://www.daiwa-grp.jp/dfa/news/20250421/maff_entrustment_press.pdf
健康維持や認知症予防といった観点からも注目されています。
地域における「農福連携」の成功事例と参加方法
各地で農福連携の取り組みが進んでおり、高齢者が活躍できる場が広がっています。
地域によっては、農福連携による高齢者向けの農業プロジェクトが活発化しており、参加者から高い評価を得ています。
根拠URL:https://metn.jp/2024/07/30/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%AA%B2%E9%A1%8C%EF%BC%9A%E6%8B%85%E3%81%84%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%B8%9B%E5%B0%91%E3%81%A8%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E2%91%A1/
自治体の社会福祉協議会や農業団体が窓口となっていることが多いです。
高齢者が農業で働く際の「注意点」と「安全対策」
高齢者が農業で働くことは多くのメリットがありますが、同時にいくつかの注意点も存在します。安全かつ持続的に農作業を行うために、考慮すべき点を解説します。
体力に合わせた「無理のない働き方」の選択
自身の体力レベルを把握し、作業内容を検討する重要性
高齢者の体力は個人差が大きいため、自身の体力レベルを正確に把握し、それに合った作業内容や労働時間を選択することが重要です。
農業従事高齢者の体力は非農業従事者より高い傾向にありますが、無理な作業は事故や健康被害につながる可能性があります。
根拠URL:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001426142&toukei=00500211&tstat=000001015214&tclass1=000001019791&tclass2=000001212780&cycle=7&year=20230&month=0&tclass3val=0&stat_infid=000040130224
短時間や軽作業のパート勤務から始めるのがおすすめです。
熱中症・転倒対策など具体的な「安全対策」
農作業は屋外で行うことが多いため、熱中症や転倒など、季節や場所に応じた安全対策が不可欠です。
夏場の農作業では、こまめな水分補給と休憩が不可欠です。また、滑りにくい靴を着用し、足元に注意することで転倒を防げます。
根拠URL:https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr412-20230728-suzuki.html
農機具の操作時には、十分な知識とスキルが必要になります。
地域への「適応」と「人間関係構築」
地域の農業慣習・文化への理解と順応
定年帰農などで新たな地域に移り住む場合、その地域の農業慣習や文化を理解し、順応することがスムーズな就農の鍵となります。
地域ごとの農業慣習やコミュニティの文化を理解し、尊重することが、地域に溶け込む上で重要です。
根拠URL:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001426142&toukei=00500211&tstat=000001015214&tclass1=000001019791&tclass2=000001212780&cycle=7&year=20230&month=0&tclass3val=0&stat_infid=000040130244
農協(JA)や農業委員会など、地域の農業団体との繋がりを大切にしましょう。
コミュニケーションを通じた円滑な「人間関係」構築
農作業は、他の働き手や農家との協力が不可欠です。円滑な人間関係を築くことは、生きがいにも繋がります。
積極的にコミュニケーションを取り、地域の人々や他の就農者との良好な人間関係を築くことは、持続的な就労において非常に重要です。
根拠URL:個別の農家インタビュー(例)
地域のイベントや交流会に顔を出すのも良いでしょう。
高齢者 農業 働き手──未来へ繋ぐ「持続可能な農業」の展望
高齢者の労働力は、日本の農業が直面する人手不足と高齢化という二つの大きな課題を解決し、持続可能な農業を未来へ繋ぐための重要な鍵となります。
高齢者が担う「地域農業」の活性化
地域活性化における高齢者の役割と貢献事例
高齢者が農業の働き手として活躍することは、その地域全体の活性化にも繋がります。
高齢農業者が地域特産の農作物を守り、新たな販路を開拓する事例も増えており、地域経済の活性化に貢献しています。
根拠URL:https://minorasu.basf.co.jp/80076
地域おこし協力隊と連携するなど、地方創生の一翼を担う存在とも言えるでしょう。
知識・経験の継承と次世代への橋渡し
長年培ってきた農業の知識や経験を、新規就農者や若い世代に継承することは、持続可能な農業を実現する上で不可欠です。
高齢農業者の知識と経験は、若い世代への技術継承において不可欠であり、地域農業の未来を支える基盤となります。
根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r5/r5_h/trend/part1/chap4/c4_2_00.html
シルバー世代の担い手が、後継者不足に悩む農家の希望となるでしょう。
まとめ:高齢者と農業の新たな共生モデルを築く
本記事では、「高齢者 農業 働き手」というテーマのもと、日本の農業が抱える人手不足と高齢化の現状、高齢者が農業で働くことのメリット、具体的な求人の探し方や支援制度、そして注意点について詳しく解説しました。
高齢者が農業で働くことは、健康増進、生きがいの創出、経済的恩恵だけでなく、日本の農業の持続可能性を高める上でも非常に大きな意味を持ちます。定年帰農を検討しているシニアの皆さん、高齢者の雇用を考えている農業経営者の皆さんにとって、この記事が新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
ぜひ、この記事を参考に、高齢者と農業の新たな共生モデルを築き、日本の食と地域を共に支えていきましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。