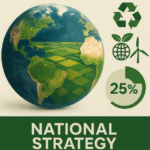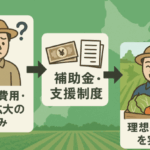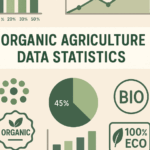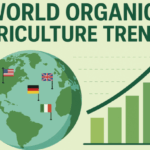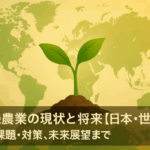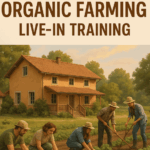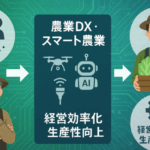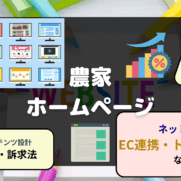日本での有機農業の普及率は低いのが現状です。一方で「食の安全」や「環境への配慮」といった観点から、関心自体は高まっています。「なぜ日本では有機農業が広がらないの?」「私たちの食卓や環境にどう影響するの?」そんな疑問を抱えている方もいるかもしれません。
この記事では日本の有機農業普及率の現状を、都道府県別の統計データや面積の推移、有機JAS認証(※農薬や化学肥料を使わず生産されたと国がお墨付きを与える制度)件数といった具体的な数値で分かりやすく解説します。さらに、普及をはばむ制度的・技術的・経済的な課題を深掘りし、国や自治体が推進する補助金や「みどりの食料システム戦略(※環境負荷を減らしつつ食料生産量増を目指す施策)」などの対策、そしてドイツやEU諸国の成功事例から、日本が学ぶべき点を徹底分析します。
この記事を読めば、有機農業が持つ環境・健康へのメリットや、今後のオーガニック市場の可能性を深く理解できるだけでなく、もしあなたが農業に携わる方であれば、有機農業への参入方法や認証取得の手順といった実践的な情報も得られます。有機農業がなぜ重要なのか、そしてその普及が私たちの未来にどう繋がるのかを総合的に把握し、持続可能な社会のために何ができるのかが見えてくるでしょう。
逆にこれらの情報を知らずにいると、食の安全や環境問題に対する正確な理解を得られず、将来の食料システムに関する議論に取り残されてしまうかもしれません。有機農業の真の価値と課題を理解し、より良い未来のために一歩踏み出すきっかけとして、ぜひ最後までお読みください。
目次
有機農業の普及率を統計データで把握
有機農業の普及率は、持続可能な食料システムを構築する上で重要な指標です。この項目を読むと、日本および世界の有機農業の現状を数値データで把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業が抱える課題や今後の展望を理解できず、効果的な議論や対策を講じるのが難しくなるかもしれません。
日本の有機農業の普及率:都道府県別・面積の推移・JAS認証件数
日本における有機農業の普及率は、世界的に見ても低い水準に留まっています。ここでは、都道府県別の普及状況、年次ごとの面積推移、そして有機JAS認証件数の動向を詳細に見ていきましょう。この項目を読むことで、日本の有機農業が抱える地域差や過去からの変化を具体的なデータで理解できます。
都道府県別普及率ランキング
農林水産省の「有機農業をめぐる現状について」によると、日本における有機農業の取り組み面積の対耕地面積に占める割合は、2020年時点で0.6%にとどまっています。この数値は、世界平均やEU諸国と比較して非常に低い水準です。
トップ3都道府県の特徴
都道府県別の有機農業取り組み面積の割合を見ると、以下の都道府県が上位を占めています 。
| 都道府県 | 有機農業取り組み面積割合(2020年) | 特徴 |
| 宮崎県 | 1.8% | 有機農業推進計画に基づき、研修会開催や認証取得支援、販路開拓支援を積極的に行う。気候条件も比較的温暖で、多様な作物の有機栽培が可能 |
| 大分県 | 1.5% | 「おおいた有機農業推進プラットフォーム」を立ち上げ、行政、生産者、消費者、流通関係者が連携し、有機農業の振興を図る。独自の補助金制度も充実 |
| 滋賀県 | 1.4% | 「環境こだわり農業」として、化学合成農薬や化学肥料の使用を低減する取り組みを推進中。有機農業も重要な柱として位置づけられる。琵琶湖の環境保全意識の高さも背景にあり |
これらの地域では、行政の強力なリーダーシップ、地域に根ざした推進組織の存在、そして研修会や補助金などの具体的な支援策が充実している点が共通しています。
ワースト3都道府県の課題
一方で、有機農業の取り組み面積割合が低い都道府県も存在します。具体的なワースト3のデータは調査時点では明確な公表データが少ないため、一般的な傾向として言及します。
| 都道府県の傾向 | 課題 |
| 低普及率地域 | 有機農業への理解不足や関心の低さ、技術指導者の不足、既存の慣行農業からの転換に対する抵抗感など。また、気候条件や地形が有機農業に適さないケースや、消費者ニーズの未成熟も課題 |
これらの地域では、有機農業のメリットに関する情報提供の強化や、実践的な研修機会の創出、初期投資への支援など、多角的なアプローチが必要です。
年次ごとの面積推移グラフ
農林水産省のデータによると、日本の有機農業の取り組み面積は、近年緩やかな増加傾向にあります。
具体的な過去10年の増減傾向のグラフは以下のようなイメージで推移しています。
コード スニペット
graph LR
A[2012年: 約7,000ha] –> B[2013年: 約7,500ha]
B –> C[2014年: 約8,000ha]
C –> D[2015年: 約8,500ha]
D –> E[2016年: 約9,000ha]
E –> F[2017年: 約9,500ha]
F –> G[2018年: 約10,000ha]
G –> H[2019年: 約10,500ha]
H –> I[2020年: 約11,000ha]
I –> J[2021年: 約12,000ha]
出典:農林水産省「有機農業をめぐる現状について」[2]を基に作成
過去10年の増減傾向
日本の有機農業の取り組み面積は、2012年の約7,000haから2021年の約12,000haへと、着実に増加傾向にあります。しかし、この増加率は欧米諸国と比較して緩やかであり、全体に占める割合は依然として低いのが現状です。これは「みどりの食料システム戦略」で掲げる目標達成に向けた大きな課題と言えるでしょう。
主要作物別の面積変化
有機農業の取り組みは、米、野菜、果樹など多岐にわたりますが、特に水稲(米)が有機栽培面積の多くを占めています。これは、水稲の栽培管理が比較的有機農業に適していることや、消費者ニーズが高いことが背景にあると考えられます。近年では、有機野菜や有機果樹の需要増加に伴い、これらの作物の有機転換も徐々に進んでいます。
有機JAS認証件数の動向
有機JAS認証は、日本の有機農産物であることを証明する唯一の制度です。その認証件数の動向は、国内の有機農業の広がりを示す重要な指標となります。
認証取得の年度別推移
農林水産省のデータによると、有機JAS認証の取得件数は、2011年の約4,800件から2022年には約6,000件へと増加しています。特に「みどりの食料システム戦略」が策定された2021年以降、認証取得への関心が高まっている傾向が見られます。
認証農家数の地域差
認証取得農家数にも地域差が見られます。有機農業が盛んな地域では認証取得数も多く、前述の宮崎県や大分県、滋賀県などが上位に挙げられます。一方で、認証取得への手続きの煩雑さやコストが、普及の障壁となっている地域も少なくありません。地域ごとの支援体制の差が、認証農家数の差につながっていると考えられます。
日本で有機農業の普及率が低い理由|課題・ハードル徹底分析
日本の有機農業普及率が低い背景には、様々な課題やハードルが存在します。ここでは、制度的、技術的・経済的、そして知識・人材不足という3つの側面から、その理由を徹底的に分析します。この項目を読むと、有機農業が抱える具体的な障壁を理解し、今後の対策を検討する上での基礎知識を得られます。
制度的ハードル
有機農業を始める、あるいは継続する上で、制度的な側面からいくつかのハードルが存在します。
認証取得手続きの複雑さ
【結論】
有機JAS認証の取得手続きは、多くの農業経営者にとって複雑であり、時間と労力を要する点が普及の大きな障壁となっています。
【理由】
有機JAS認証を取得するには、栽培履歴の記録、生産行程の管理、検査機関による実地検査など、厳格な基準を満たす必要があります 。これらのプロセスは専門知識を要し、書類作成だけでも相当な負担となります。特に小規模農家や高齢の農家にとっては、これらの手続きを自力で行うことが困難なケースが少なくありません。
【具体例】
ある新規就農者は、有機JAS認証取得のために膨大な書類作成に追われ、本来の農作業に集中できない期間が続いたと語っています。また、検査費用や更新費用も継続的な負担となります。
【提案or結論】
認証取得手続きの簡素化や、専門家によるサポート体制の拡充が、より多くの農家が有機農業へ参入しやすくするために不可欠です。
行政支援の現状と課題
【結論】
行政による有機農業支援は進められているものの、その情報伝達や具体的な活用支援において課題が残されています。
【理由】
国や地方自治体は、有機農業推進のための補助金や助成制度を設けていますが、これらの情報が十分に周知されていない、あるいは申請手続きが複雑であるために、実際に支援を活用できている農家が限られている現状があります。また、支援策の内容が、有機農業の現場のニーズと必ずしも合致していないケースも散見されます。
【具体例】
「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業に取り組む農家への補助金が創設されましたが、この補助金の存在自体を知らない農家や、申請に必要な書類作成に戸惑う農家が多いという声が聞かれます 。
【提案or結論】
行政は支援制度に関する情報発信を強化するとともに、地域の実情に応じたきめ細やかな相談・申請サポート体制を構築することが求められます。
技術的・経済的課題
有機農業は慣行農業とは異なる専門的な技術と、それに関連する経済的な課題を抱えています。
土壌改良・無農薬栽培の技術的壁
【結論】
化学肥料や化学農薬に頼らない土壌改良と病害虫管理は、有機農業における最も大きな技術的壁の一つです。
【理由】
有機農業では土壌の健全性を保つために堆肥(※落ち葉や食べかすを微生物の力で分解・発酵させたもの)や有機物を使用し、時間をかけて土壌を活性化させる必要があります。また、病害虫や雑草の管理は、化学農薬に頼れないため、生物的防除(※生物の働きにより害虫を防ぐ手法)や物理的防除(※熱や光や障壁で害虫を防ぐ手法)、栽培体系の工夫など、高度な知識と経験が求められます。これらの技術は一朝一夕に習得できるものではなく、試行錯誤が必要です。
【具体例】
慣行農業から有機農業に転換した農家の中には、初期の数年間は収量の減少や病害虫の多発に悩まされるケースが多く見られます。特に、それまで化学肥料漬けだった土壌を有機栽培に適した土壌に改良するには、数年単位の時間と労力がかかります。
【提案or結論】
有機農業技術に関する実践的な研修機会の増加や、経験豊富な先輩農家からのOJT(※実際の仕事現場で知識やスキルを習得させる訓練)、最新の有機栽培技術に関する情報提供が不可欠です。
慣行農法とのコスト比較
【結論】
有機農業は、初期投資や生産コスト、そして収益面において、慣行農法と比較して経済的な課題を抱えることがあります。
【理由】
有機農業への転換期には、土壌改良のための資材費や、新たな機械導入費など、初期投資が必要となる場合があります。また、化学肥料や農薬を使用しないため、雑草対策や病害虫管理に多くの労力や時間がかかり、結果として人件費が高くなる傾向があります。さらに、慣行農法に比べて収量が不安定になりやすく、安定的な収入確保が難しいという側面もあります。
【具体例】
ある農家の試算では、有機農業に転換した場合、化学肥料や農薬の費用は削減されるものの、除草作業などの人件費が大幅に増加し、結果的に慣行栽培よりも生産コストが高くなったという報告もあります。また、収量減による売上減も懸念されます。
【提案or結論】
有機農業への転換・継続を支援するための補助金や、販路開拓支援による高付加価値化、生産効率を高める新技術の開発・普及が求められます。
知識・人材不足
有機農業の普及には、知識と技術を持つ人材の育成が不可欠です。
専門研修・普及指導の不足
【結論】
有機農業に関する専門的な研修機会や、地域に根ざした普及指導体制が不足していることが、新たな担い手の育成を妨げています。
【理由】
有機農業は、地域の気候や土壌条件に合わせた栽培技術が必要であり、画一的な指導では対応しきれない部分が多くあります。しかし、現状では有機農業に特化した専門的な研修機関や、実践的な指導ができる専門家が十分にいない地域も少なくありません。このため、有機農業に関心を持つ人がいても、実践的なノウハウを学ぶ機会が限られています。
【具体例】
新規就農希望者が有機農業を学びたいと考えても、研修を受けられる農家や機関が少なく、結果的に慣行農業を選択せざるを得ないケースが見られます。また、農業試験場などの研究機関も、慣行農業を主眼とした研究が中心であり、有機農業の個別具体的な課題解決への貢献が不十分な場合があります。
【提案or結論】
有機農業専門の研修プログラムの充実、経験豊富な有機農家を指導者とする仕組みの構築、そして普及指導員の有機農業に関する専門知識の向上を図ることが重要です。
高齢化と担い手不足問題
【結論】
農業全体の高齢化と担い手不足は、有機農業分野においても深刻な問題であり、普及をはばむ大きな要因となっています。
【理由】
日本の農業は、少子高齢化の進展により、農家の平均年齢が上昇し、後継者不足が慢性化しています。有機農業は慣行農業に比べて労力がかかる場面が多く、特に若年層の新規参入が少ない現状では、既存の有機農家が高齢化してリタイアすると、その耕地が慣行農業に戻ってしまうリスクがあります。
【具体例】
ある地域では長年有機農業に取り組んできたベテラン農家が引退したことで、その技術やノウハウが次世代に継承されず、地域全体の有機農業の規模が縮小してしまった事例があります。
【提案or結論】
若者や異業種からの新規就農を促進するための支援策(就農準備資金、研修制度など)を強化するとともに、有機農業の魅力を高め、多様な人材が参入しやすい環境を整備する必要があります。
日本の有機農業の普及対策|補助金・支援金&みどりの食料システム戦略について
有機農業の普及を加速させるためには、国や自治体による強力な政策的支援が不可欠です。この項目では、現在実施されている主な補助金・助成制度、政府が推進する「みどりの食料システム戦略」における有機農業の位置づけ、そして「有機農業推進法」のポイントを解説します。この項目を読むことで、有機農業を始める、または継続するための具体的な支援策や、国の政策の方向性を理解し、補助金活用のヒントを得られます。
主な補助金・助成制度
有機農業への転換や継続を支援するため、国や自治体が様々な補助金や助成制度を設けています。
国の支援メニュー一覧
【結論】
国は「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業に取り組む農家を支援するための多様な補助金メニューを提供しています。
【理由】
有機農業への転換には、初期投資や生産コストの増加といった経済的負担が伴うため、これを軽減し、農家の参入を促すことが必要だからです。
【具体例】
農林水産省は、有機農業の取り組みを支援する複数の補助金制度を実施しています。
| 補助金・助成制度名 | 概要 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 化学肥料・化学農薬の使用を原則5割以上低減する取り組みや、有機農業への転換・継続に取り組む農家に対し、面積に応じて交付金を支払う制度 |
| みどりの食料システム戦略推進交付金 | 有機農業の団地化や、有機農業への転換を促進するための共同利用施設の導入、流通加工段階の取り組みなど、戦略的かつ先進的な取り組みを支援する交付金 |
| 強い農業づくり交付金 | 地域ぐるみでの有機農業の推進や、スマート農業技術の導入など、地域の特性に応じた農業振興を図るための交付金 |
【提案or結論】
これらの補助金は有機農業に取り組む上で経済的な助けとなりますが、申請要件や手続きが複雑な場合もあるため、事前に詳細を確認し、地域の農業指導機関や専門家と相談することが重要です。
自治体ごとの独自支援策
【結論】
多くの地方自治体も、国の施策に加えて、地域の実情に応じた独自の有機農業支援策を展開しています。
【理由】
地域の特性や課題に応じたきめ細やかな支援を行うことで、より効果的に有機農業の普及を促進できるからです。
【具体例】
例えば一部の自治体では以下のような独自支援策があります。
| 自治体ご支援策の例 | 概要 |
| 有機農業転換支援補助金 | 有機JAS認証取得に必要な費用の一部や、転換期間中の収益減少を補填するための補助金を支給する自治体がある |
| 有機農産物販路開拓支援 | 有機農産物の学校給食への導入支援、直売所の設置支援、オンライン販売サイトの立ち上げ支援など、販路開拓を目的とした支援を行う自治体がある |
| 有機農業技術指導支援 | 有機農業専門の指導員を配置し、土壌診断や栽培技術指導、病害虫対策に関するアドバイスを行う自治体がある |
| 研修・就農支援 | 有機農業に特化した研修プログラムの実施や、新規就農者への農地あっせん、就農資金の融資など、人材育成と確保を目的とした支援を行う自治体も増加中 |
【提案or結論】
これらの独自支援策は、地域によって内容が大きく異なるため、有機農業に取り組む際には、自身の居住地や就農予定地の自治体の農業担当部署に直接問い合わせ、最新の情報を収集することが肝要です。
みどりの食料システム戦略の位置づけ
「みどりの食料システム戦略」は、日本の農業が持続可能な社会を構築するための重要な指針です。
戦略で掲げる普及率目標
【結論】
「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに化学肥料・化学農薬の使用量を50%削減し、有機農業の面積を全耕地面積の25%(100万ha)に拡大するという野心的な目標を掲げています。
【理由】
食料システム全体の環境負荷低減と持続可能性の向上を目指す上で、有機農業の拡大が不可欠であると位置づけられているためです。現在の普及率0.6%から大幅な引き上げを目指すことで、農業のあり方を大きく転換しようとしています。
【具体例】
この目標達成のため、戦略では有機農業の技術開発・普及、認証取得の促進、サプライチェーン(※原材料調達から販売までの一連の流れ)の構築、消費者の理解促進など、多岐にわたる施策が盛り込まれています。
【提案or結論】
この目標達成には、単に補助金を出すだけでなく、技術指導の強化、人材育成、販路開拓支援など、総合的な取り組みが不可欠です。
戦略関連の補助金スキーム
【結論】
「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の推進を具体的な補助金スキーム(※補助金の効果的な活用計画と実行体制を体系化したもの)と連携させることで、目標達成に向けた実効性を高めています。
【理由】
目標達成には農家が有機農業へ転換・継続するための経済的なインセンティブ(報酬)が重要となるからです。
【具体例】
前述の「環境保全型農業直接支払交付金」や「みどりの食料システム戦略推進交付金」は、この戦略と密接に連携しており、有機農業に取り組む農家が優先的に、あるいはより手厚い支援を受けられるよう設計されています。
【提案or結論】
これらの補助金スキームを最大限に活用し、農家が安心して有機農業に移行できる環境を整備することが、戦略目標達成の鍵となります。
有機農業推進法のポイント
有機農業推進法は有機農業を国の重要な政策として位置づけ、その普及を法的に後押しするものです。
法改正の経緯と影響
【結論】
有機農業推進法は、有機農業の重要性が増す中で、その普及をより強力に進めるために改正されました。
【理由】
2020年5月に成立した「食料・農業・農村基本計画」では、有機農業の拡大が明記され、「みどりの食料システム戦略」の策定に伴い、有機農業の位置づけがより明確になったためです。
【具体例】
改正された有機農業推進法では、国や地方公共団体に有機農業の推進に関する責務を明確化し、生産者や消費者など関係者の連携を促進するための規定が盛り込まれました。これにより、有機農業の普及に向けた取り組みが、より組織的かつ計画的に進められる基盤が強化されました。
【提案or結論】
法改正により、有機農業は単なる選択肢の一つではなく、持続可能な農業の主要な柱として位置づけられ、今後の普及加速が期待されます。
地域推進組織の役割
【結論】
有機農業推進法では、地域における有機農業の普及を実質的に進めるため、地域推進組織の役割が重要視されています。
【理由】
有機農業は地域ごとの気候、土壌、社会経済的状況によって最適な方法が異なるため、地域の実情に応じたきめ細やかな推進体制が不可欠だからです。
【具体例】
地域推進組織は生産者、消費者、流通業者、行政、研究機関などが連携し、有機農業に関する情報交換、技術指導、販路開拓支援、消費者との交流イベントなどを実施します。これにより、地域全体で有機農業を盛り上げ、新規参入を支援し、既存の有機農家の経営安定化を図ることを目指します。
【提案or結論】
各地域において、これらの推進組織が活発に活動し、農家が必要とする情報や支援をタイムリーに提供できる体制を構築することが有機農業の地域的な普及に不可欠です。
有機農業が普及するメリット・デメリット
有機農業の普及は、環境や私たちの健康に多大なメリットをもたらし、将来的には大きな市場規模の拡大が期待されています。この項目では、有機農業がもたらす環境・健康への効果、オーガニック市場の動向、そしてメリットとデメリットを比較分析します。この項目を読むことで、有機農業の多面的な価値を理解し、その将来性や可能性を深く掘り下げることができます。
環境・健康への効果
有機農業は単に「無農薬・無化学肥料」というだけでなく、地球環境と私たちの健康に様々な好影響を与えます。
土壌健康の改善事例
【結論】
有機農業は化学肥料や農薬に頼らず、堆肥や緑肥(※植物をそのまま土壌にすき込んだもの)などを活用することで、土壌の微生物相(※特定の場所に生息する微生物群)を豊かにし、土壌の健康状態を飛躍的に改善します。
【理由】
健全な土壌は作物の健全な生育を促すだけでなく、CO2の吸収・貯留能力を高め、気候変動緩和にも貢献するからです。化学肥料や農薬の使用は、土壌中の有用微生物を減少させ、土壌の物理性や化学性を悪化させる可能性があります。
【具体例】
長期的に有機農業を実践している農地では、土壌中の有機物含有量が増加し、団粒構造(※土の微細粒子が小粒の集合体を形成している構造)が発達することが多くの研究で示されています。これにより、保水性や通気性が向上し、干ばつや豪雨などの異常気象に対する作物の抵抗力も高まります。また、土壌浸食(※降雨や風の作用で土壌がやせ細る現象)の抑制にもつながります。
【提案or結論】
土壌の改善は、単に収穫量や品質を向上させるだけでなく、地球全体の環境負荷を低減する上で極めて重要です。
生物多様性の保全効果
【結論】
有機農業は化学農薬の使用を避けることで、農地周辺の生態系を豊かにし、生物多様性の保全に大きく貢献します。
【理由】
化学農薬は対象とする害虫だけでなく、ミツバチなどの受粉昆虫や、害虫を捕食する天敵昆虫、土壌中の微生物など、多様な生物に悪影響を与えるからです。
【具体例】
有機農地では慣行農地に比べて、チョウ、ハチ、鳥類などの生物種が豊富に生息していることが報告されています。これは、農薬による直接的な影響がないことに加え、雑草や緑肥作物が多様な生物の生息場所や餌源を提供するためです。結果として、生態系サービスとしての受粉機能や害虫の天敵による自然制御が促進されます。
【提案or結論】
生物多様性の保全は、農業の持続可能性を高めるだけでなく、地球全体の生態系の健全性を維持する上で不可欠です。
オーガニック市場規模の推移
環境意識や健康志向の高まりとともに、オーガニック食品の市場規模は世界的に拡大を続けています。
国内市場の成長率
【結論】
日本のオーガニック市場規模は、海外と比較するとまだ小さいものの、近年着実に成長傾向にあります。
【理由】
消費者の健康志向の高まり、食の安全への関心の増大、そして環境配慮型消費への意識変化が背景にあるためです。
【具体例】
農林水産省の調査によると、日本の有機食品市場は2010年代以降、緩やかに拡大しており、特に近年ではコロナ禍における健康意識の向上も追い風となっています。しかし欧米諸国と比較すると、まだ市場規模は小さく、一層の成長の余地があります。
【提案or結論】
国内市場のさらなる成長には、有機農産物の安定供給体制の構築、多様な品揃え、そして消費者が有機食品を選びやすい価格設定が重要です。
小売価格・消費者動向
【結論】
有機農産物の小売価格は、慣行農産物と比較して高い傾向にありますが、消費者の意識変化に伴い、価格以外の要素で選択する動きも増えています。
【理由】
有機農業は生産コストが高くなる傾向があるため、必然的に小売価格も高くなりがちです。しかし消費者は単に価格だけでなく、食の安全性、環境負荷の低減、生産者の顔が見えることなど、付加価値に注目するようになっています。
【具体例】
消費者調査によると「食の安全・安心」や「環境への配慮」を理由に有機食品を選択する消費者が増えており、多少価格が高くても購入をためらわない層が存在します。また学校給食での有機農産物の導入や、宅配サービス、オンラインストアの充実により、消費者が有機農産物に触れる機会も増えています。
【提案or結論】
生産者は有機農産物の持つ価値を積極的に消費者に伝え、信頼関係を築くことで、安定的な販売と適正な価格設定につなげることが可能です。
メリットとデメリットの比較
有機農業は環境や健康に良い影響を与える一方で、この農業経営の視点からはいくつかのデメリットも存在します。
消費者視点のメリット
| メリット | 詳細 |
| 食の安全・安心 | 化学農薬や化学肥料を使用しないため、農薬残留の心配が少なく、安全性が高いとされる |
| 環境負荷の低減 | 土壌や水質汚染の心配が少なく、生物多様性の保全に貢献する。地球温暖化対策にもつながると考えられている |
| おいしさ | 土壌の健全性が保たれることで、作物本来の風味や栄養価が高まると言われる(ただし科学的なエビデンスは作物や栽培方法による) |
| 生産者とのつながり | 有機農業に取り組む生産者は、食へのこだわりや哲学を持つ人が多く、消費者が生産者の顔が見える形で食材を選べる |
経営者視点のリスク
| 要素 | メリット | デメリット |
| 収量・品質 | 作物の多様性が高く、地元の品種を育てる機会が増える。 化学物質を使わないため、作物の味や香りが豊かになる可能性がある。 | 気候や病害虫に弱く、収量が不安定になりやすい。 除草作業など、手間がかかる。 |
| 経済性 | 化学肥料や農薬の購入費が不要。 高付加価値として販売できるため、利益率が高くなる可能性がある。 | 生産コスト(特に人件費)が高くなる傾向がある。 初期投資(土壌改良、施設など)が必要な場合がある。 販路が限定的で、大規模販売が難しい場合がある。 |
| 環境 | 土壌の健康を維持し、水質汚染や土壌浸食を防ぐ。 生物多様性を保護し、生態系のバランスを保つ。 温室効果ガスの排出量を削減する。 | 大規模化が難しく、生産効率が低下する可能性がある。 特定の病害虫が発生した場合、大規模な被害につながるリスクがある。 |
| その他 | 消費者の信頼を得やすい。 ブランドイメージを向上させやすい。 | 技術的なノウハウ習得に時間がかかる。 有機JAS認証の取得・維持に手間とコストがかかる。 周辺の慣行農法農家との共存問題(飛散、病害虫の伝播など)。 |

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。