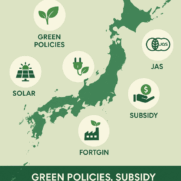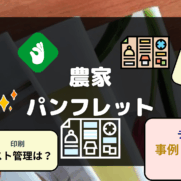「有機農業に興味はあるけれど、病害虫対策ってどうすればいいんだろう?」 「無農薬じゃないと有機って言えないの?」「有機JAS認証って複雑そう…」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?有機農業は環境に優しく、安心・安全な作物を育てる魅力的な栽培方法ですが、一般的な化学合成農薬が使えないため、病害虫や雑草の対策に頭を悩ませる方も少なくありません。
本記事では、有機JAS規格で認められている「使える農薬」の種類、具体的な使い方、有機JAS認証の基準や取得方法まで、有機農業を実践する上で知っておきたいノウハウを徹底的に解説します。
この記事を読めば、あなたは有機農業における病害虫対策の選択肢を広げ、安心して有機栽培に取り組むための具体的な知識と方法を手に入れることができます。有機JAS適合資材リストの活用方法や、代替防除手法との組み合わせもわかるので、収量を安定させながら環境負荷の低い農業経営を実現する一歩を踏み出せるでしょう。
逆に、この記事を読まなければ、有機JAS認証の基準を誤解して意図せず違反してしまったり、病害虫の被害に有効な対策を講じられず、時間と労力を無駄にしてしまうかもしれません。結果的に有機農業の継続が困難になったり、期待する収量が得られないといった事態に陥る可能性もあります。
ぜひこの記事を最後まで読んで、あなたの有機農業を成功に導くための確かな知識と情報を手に入れてください。
目次
有機農業で「使える農薬」とは?定義・メリット・デメリットを解説
有機農業と聞くと、「無農薬」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実は有機JAS規格で認められた、ごく一部の農薬は有機農業でも使えるものがあります。これは、自然由来の成分や、特定の微生物を利用したもので、化学合成農薬とは一線を画します。
有機農業で使える農薬に関するポイントは以下の通りです。
- 有機JAS規格が定める厳格な基準に適合した農薬のみが許可されています。
- 一般的な農薬とは異なり、天然由来の成分や微生物を利用したものが中心です。
- 病害虫や雑草への対策として、あくまで最終手段として使われるものです。
この項目を読むと、有機農業における「使える農薬」の基本的な考え方と、そのメリット・デメリットを正確に理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、「無農薬」との違いや有機JAS認証の要件について誤解したまま作業を進め、後で後悔する可能性があるので、次の項目から詳細を見ていきましょう。
有機JAS規格と「使える農薬」の定義
有機JAS規格における農薬の位置づけ
有機JAS規格は、有機農産物や有機加工食品の生産基準を定めた日本の国家規格です。この規格では、化学合成農薬や化学肥料の使用を原則として禁止しています。しかし、病害虫や雑草の防除が困難な場合に限り、有機JAS規格の「別表B.1」に掲載されている農薬(特定防除資材)の使用が例外的に認められています。これは、自然由来であること、環境負荷が低いこと、人や生態系への影響が少ないことなどを考慮したものです。
「無農薬」と「有機」の違い
| 項目 | 無農薬 | 有機JAS認証 |
| 農薬使用 | 化学農薬を一切使用しない(自己申告) | 有機JAS規格の使える農薬のみ使用可 |
| 化学肥料使用 | 原則使用しない | 原則使用しない |
| 認証制度 | なし | 国の認証制度あり |
| 法的表示 | 「無農薬」表示は禁止 | 「有機JASマーク」表示が可能 |
無農薬は農薬を使用しない栽培方法を示す言葉で、法的な表示基準はありません。「有機」は、有機JAS規格に則り、第三者機関の認証を受けた農産物にのみ付けられる表示です。つまり、有機の農産物は「使える農薬」を使用することが許可されている場合があるため、無農薬とイコールではありません。
有機農業で「使える農薬」のメリット・デメリット
メリット(最小限の防除と環境負荷低減)
有機農業で使える農薬の最大のメリットは、病害虫や雑草による被害が深刻化し、通常の対策だけでは困難な場合に、作物の全滅を防ぐための最終手段として機能する点です。これにより、安定した収量を確保しやすくなり、経営のリスクを軽減できます。また、天然由来の成分であるため、化学合成農薬に比べて環境負荷が低く、安全性が高いという特徴があります。
デメリット(限定的な効果とコスト)
一方で、有機農業で使える農薬は、化学合成農薬と比較して効果が限定的である場合が多いです。即効性が低かったり、特定の病害虫にしか効かなかったりするため、使用方法やタイミングを厳密に守る必要があります。また、一般的な農薬に比べてコストが高い傾向にある点もデメリットとして挙げられます。
経済性評価と使用のバランス
有機農業における農薬使用は、収量の安定化とコストのバランスを考慮する必要があります。安易に頼るのではなく、あくまで耕種的防除や物理的防除などの代替防除手法を優先し、それらで解決できない場合にのみ使える農薬の使用を検討することが、持続可能な経営と有機JAS認証の維持には不可欠です。
初心者向け!有機JASで「使える農薬」一覧と活用のポイント
有機農業で使える農薬について理解を深めたら、具体的にどのような種類の農薬が許可されているのか、そしてそれらをどう活用すれば良いのかを知ることが重要です。特に初心者の方は、その種類の多さや使い方に戸惑うかもしれません。
有機JASで使える農薬活用のポイントは以下の通りです。
- 農林水産省が公表する有機JAS規格の「別表B.1」に掲載されている農薬のみが使用できます。
- 天然由来成分や微生物を利用したものが多く、特定の病害虫や病気に対して効果を発揮します。
- 使用に際しては、適用作物や時期、希釈倍率などの注意点を必ず確認する必要があります。
この項目を読むと、有機JAS規格で使える農薬の具体的な種類と、その効果的な使い方を把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機JAS認証を取り消されるリスクや、期待する効果が得られない可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。
有機JAS規格「別表B.1」に掲載の農薬一覧
農林水産省の有機JAS規格「別表B.1」には、有機農業で使用が認められている特定防除資材の種類が記載されています。主なものは以下の通りです。
| 農薬の種類 | 主な成分・特徴 | 効果の対象 |
| 天然物農薬 | 除虫菊、ニームオイルなど、植物由来の殺虫成分 | 害虫 |
| 微生物農薬 | BT剤(バチルス・チューリンゲンシス菌)など、微生物が産生する毒素や微生物そのもの | 害虫、病原菌 |
| 無機化合物 | 銅水和剤、石灰硫黄合剤、硫黄など | 病気(菌類) |
| その他 | 木酢液(土壌改良・忌避効果)、性フェロモン剤(害虫の誘引) | 害虫、土壌の活性化 |
主な特定防除資材の用途と注意点
天然物農薬(除虫菊・ニームオイルなど)の使い方
- 除虫菊:天然の殺虫成分であるピレトリンを含み、幅広い害虫に効果があります。即効性がありますが、光に弱く分解されやすいため、夕方以降の散布が推奨されます。
- ニームオイル:インド原産のニームの木から抽出される油で、害虫の食害を抑制したり、成長を阻害する効果があります。定期的な散布が効果的です。
微生物農薬(BT剤など)の効果と活用
BT剤は、特定の害虫の幼虫にのみ作用する微生物農薬です。チョウ目害虫(アオムシ、ハスモンヨトウなど)の食害を防ぎます。人や天敵には無害で、環境負荷が低いのが特徴です。効果を発揮するまでに時間がかかるため、害虫の発生初期に散布することが重要です。
無機化合物(石灰硫黄合剤・銅水和剤など)の適用
- 石灰硫黄合剤:殺菌・殺虫効果があり、特に冬季の病害虫対策に用いられます。強アルカリ性のため、使用上の注意点(肌への付着、他の農薬との混用不可など)が多いです。
- 銅水和剤:殺菌効果があり、べと病や疫病などの病気に適用されます。耐性菌の発生を抑えるため、他の農薬とのローテーションも検討されます。
その他の有機JAS適合資材:性フェロモン剤・木酢液
- 性フェロモン剤:害虫が持つ性フェロモンを利用し、雄を誘引して捕獲することで、交尾や繁殖を阻害します。特定の害虫に特化した対策として有効です。
- 木酢液:木炭を作る過程で得られる液体で、土壌の活性化や病害虫の忌避効果があると言われています。希釈して土壌に散布したり、葉面散布に利用されます。
農薬使用上の注意点と法規制遵守
有機JAS認証を受けた農家は、使える農薬を使用する際にも厳格なルールを遵守する必要があります。
- JAS規格に適合した資材であることのラベル確認を徹底する。
- 使用目的が「病害虫の防除が困難な場合」に限られる。
- 使用量や使用回数、使用時期などが適切であること。
- 使用履歴を詳細に記録し、認証機関の検査に備える。
これらのルールを破ると、有機JAS認証が取り消される可能性があります。
有機農業における病害虫対策:使える農薬と代替防除の組み合わせ
有機農業では、使える農薬に頼りきることなく、様々な代替防除手法を組み合わせた総合的な病害虫対策(IPM:Integrated Pest Management)が非常に重要です。これにより、病害虫の発生を未然に防ぎ、農薬の使用を最小限に抑えることができます。
病害虫対策と収量アップのポイントは以下の通りです。
- 土作りや品種選びなど、耕種的防除で病害虫に強い作物環境を作ります。
- 物理的防除や生物的防除を積極的に活用し、農薬の使用を減らします。
- 病害虫の種類に応じた対策と、早期発見・早期防除が成功の鍵です。
この項目を読むと、有機農業で使える農薬と、それ以外の代替防除手法を効果的に組み合わせるノウハウを習得し、病害虫の被害を最小限に抑えながら収量を安定させるコツを学べます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、病害虫による被害が深刻化し、収量が大幅に減少する可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。
耕種的防除:土作りと健全育成で病害虫に強くする
土壌改善と施肥管理
健康な土壌は、病害虫に強い作物を育てる基本です。堆肥や緑肥を活用した土作りにより、土壌の物理性、化学性、生物性を改善し、微生物の多様性を高めます。これにより、作物の根張りが良くなり、養分吸収が促進され、抵抗力のある健全な作物に育ちます。適切な施肥管理も、作物が過剰に生長して病害虫の標的となるのを防ぎます。
品種選定と輪作
病害虫に強い品種や、地域の気候に適した品種を選ぶことも重要な対策です。また、同じ作物を連作せずに、異なる作物を順番に栽培する「輪作」を行うことで、特定の病害虫や病気が土壌中に蓄積するのを防ぎます。
コンパニオンプランツの活用
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いに良い影響を与え合う植物のことです。例えば、特定の害虫を忌避したり、天敵を誘引したりする効果があります。マリーゴールドやネギ類などが代表的です。
物理的防除:侵入阻止と捕獲
防虫ネット・シルバーマルチの利用
- 防虫ネット:物理的に害虫の侵入を防ぐ最も直接的な対策です。作物の種類や害虫のサイズに合わせて、網目の大きさを選びます。
- シルバーマルチ:地面に張ることで、害虫が嫌がる光を反射させ、忌避効果を発揮します。また、地温を調整し、雑草の発生を抑制するメリットもあります。
粘着トラップ・捕獲器の設置
粘着トラップは、色や光で害虫を誘引し、粘着シートで捕獲する物理的防除手段です。特にアブラムシやコナジラミなど、飛翔性の害虫に効果があります。性フェロモン剤を組み合わせた捕獲器も、特定の害虫の個体数を減らすのに役立ちます。
生物的防除:天敵の活用
天敵利用の促進と効果
生物的防除は、病害虫の天敵(捕食性昆虫、寄生蜂、病原微生物など)を圃場に放飼したり、天敵が住みやすい環境を整えたりすることで、病害虫の発生を抑制する方法です。これにより、農薬の使用量を減らし、環境負荷を低減できるメリットがあります。
有機農業における天敵の保護・誘引
有機農業では、農薬の使用が制限されるため、天敵の保護・誘引が特に重要です。具体的には、天敵の隠れ場所となる植物(草本類や花卉類)を圃場周辺に植えたり、天敵の餌となる花粉や蜜を供給する植物を導入したりします。
総合的病害虫・雑草管理(IPM)の重要性
有機農業における病害虫対策の最終目標は、IPM(Integrated Pest Management)を実践することです。これは、耕種的防除、物理的防除、生物的防除、そして使える農薬の使用を組み合わせ、病害虫の発生を総合的に管理するアプローチです。一つの対策に偏らず、多様な方法を組み合わせることで、持続可能で効果的な防除が可能になります。
有機JAS認証の取得・維持と、よくあるQ&A
有機農業で生産した農産物を「有機JAS」として販売するためには、認証の取得が不可欠です。この認証プロセスと、使える農薬に関するよくある疑問を解決することで、安心して有機農業に取り組めるでしょう。
有機JAS認証取得・維持のポイントは以下の通りです。
- 有機JAS規格に則った栽培計画と記録が重要です。
- 認証機関による厳正な検査を経て、認証が与えられます。
- 「使える農薬」に関する疑問を解消し、適切な知識を身につけましょう。
この項目を読むと、有機JAS認証の取得方法から、農薬に関するよくある質問とその回答まで、有機農業を実践する上で知っておきたい重要な情報を把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、認証の取り消しや、誤った農薬の使用をしてしまう可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。
有機JAS認証の取得プロセスと注意点
認証要件と栽培計画の重要性
有機JAS認証を取得するには、最低2年間(多年生作物の場合は3年間)以上、有機JAS規格に則った栽培方法で管理された圃場で生産されている必要があります。この期間中、化学合成農薬や化学肥料の使用は厳禁です。認証のためには、詳細な栽培計画を策定し、使用する資材や農薬の種類、量、使用時期などを明確に記録することが求められます。
認証機関の選び方と申請フロー
有機JAS認証は、農林水産大臣の登録を受けた認証機関が検査・認証を行います。複数の認証機関が存在するため、費用、サポート体制、実績などを比較検討し、自社に合った機関を選びましょう。
申請フローは以下の通りです。
- 認証機関への問い合わせ・相談
- 申請書類の準備・提出(栽培計画、圃場図、資材購入記録など)
- 実地検査(圃場、施設、記録の確認)
- 認証の可否決定
- 認証取得、有機JASマークの表示開始
認証後の維持管理と検査
一度有機JAS認証を取得した後も、毎年定期的な検査を受けることで認証を維持する必要があります。日々の栽培記録、資材の購入記録、農薬の使用履歴などをきちんと残し、いつでも検査に対応できるよう準備しておくことが重要です。
よくあるQ&A(再検索キーワードから)
Q1: 有機JAS適合資材リストはどこで確認できますか?
A1: 農林水産省のウェブサイトで「有機JASの特定農薬等(適合資材)リスト」として公開されています。また、一部の農薬メーカーや農業資材販売会社も、有機JAS適合製品の一覧をウェブサイトで提供していますので、「有機JAS 適合資材 農薬 メーカー」で検索すると見つけることができます。
Q2: 有機農業でアブラムシやうどんこ病が発生した際の具体的な対策は?
A2: アブラムシには、ニームオイルや除虫菊といった天然物農薬の散布が考えられます。また、物理的防除として、セロハンテープで取り除く、水で洗い流すなどの方法も有効です。うどんこ病には、銅水和剤や硫黄剤が使える農薬として知られています。さらに、木酢液の希釈液を散布する方法もありますが、これは農薬ではなく、忌避効果や植物の活性化を目的としたものです。いずれも発生初期の対策が重要です。
Q3: 有機農業における雑草対策で使える農薬はありますか?
A3: 有機JAS規格で認められた除草剤は非常に限られています。基本的には、耕種的防除(土作り、輪作、品種選び)や物理的防除(手取り除草、機械除草、防虫ネット、マルチング)が主要な雑草対策となります。ただし、特定農薬の一部で雑草に効果があるものが存在しないわけではありません。具体的な種類については別表B.1を確認してください。
Q4: 家庭菜園で無農薬を目指していますが、病害虫に困っています。何か使える農薬はありますか?
A4: 家庭菜園の場合、有機JAS認証の取得は通常行いませんが、有機JASで許可されている農薬は、環境負荷が低く、安全性が高いものが多いため、選択肢の一つになります。例えば、除虫菊やニームオイル、BT剤などは、ホームセンターや園芸店でも入手可能なものがあります。ただし、使用の際は必ず製品の使い方と注意点をよく読んでください。木酢液や忌避剤も、比較的気軽に試せる対策です。
成功への一歩!有機農業での病害虫対策と持続可能な農業経営
有機農業は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献する、未来志向の農業です。使える農薬の知識を深め、それらを代替防除手法と組み合わせることで、病害虫の課題を乗り越え、収量と品質を両立させることが可能です。
この項目を読むと、有機農業で病害虫対策を成功させ、持続可能な農業経営へと繋げるための具体的なステップを理解できます。
有機農業の課題を乗り越えるためのポイント
- 使える農薬を正しく理解し、適切なタイミングで活用する。
- 耕種的防除、物理的防除、生物的防除を組み合わせたIPMを実践する。
- 土作りを徹底し、作物の抵抗力を高める。
継続的な学習と情報共有で、より良い有機農業を目指そう
有機農業の技術やノウハウは常に進化しています。新しい使える農薬の情報や、より効果的な代替防除手法を学ぶために、農業研修やセミナーへの参加、農家仲間との情報交換を積極的に行いましょう。
有機農業は、地球と私たちの子どもたちの未来を守るための重要な農業です。使える農薬を正しく理解し、賢く活用することで、あなたの有機農業が成功し、持続可能な農業経営への道が開かれることを願っています。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。